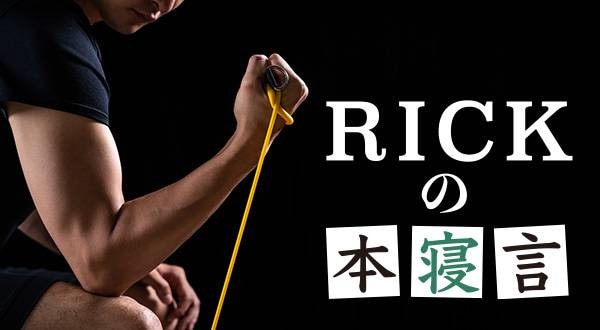会社が成長し続け、皆が高い給料をもらって豊かに幸せになるというのは、儚い夢なのか。時には現実のように思えても、ふと気が付くとやはり妄想だったのか、霞のように脳裏から消え去っていく。何故なら、現実は厳しい競争社会の坩堝であり、サウンドハウスもその、ど真ん中にいるからだ。願わくは、社員一同幸せな人生を過ごしてもらいたい。そのベースにサウンドハウスが存在してくれるならば、それにこしたことはない。
創業以来およそ30年間、これまでサウンドハウスはかろうじて成長路線を歩んできたが、もはやその勢いはなくなりつつある。周辺の社会環境が激変し続け、過去に蓄積された経験則というものが通じなくなってきたからだ。「より良いものを、より安く」という創業時代からのメッセージさえ、過去の産物になりつつある。最近のはやりの言葉であるDX、AI、果てはSDGsなど、とかくアルファベットが平然とどこでも飛び交う昨今に象徴されるように、時代は大きく変わりつつある。そして日本で培われてきた素晴らしい伝統と古典的な文化が根底から覆されかねないような風潮が漂いはじめていることを危惧するのは、自分だけだろうか。
サウンドハウスは「義理と人情」という、誰もが聞いたことのあるモットーを掲げながら、創業当初から今日までの経営方針を貫いてきた。ところがそんな言葉は今の世代には通じないのだろう。日本文化特有の「配慮」、「思いやり」、「気配り」、「気遣い」そして「謙虚」、「敬虔」などという、人の心を象徴する大切な言葉がいつしかそっぽをむかれてしまっているように思えてならない。音楽を通して何等かの社会貢献ができれば本望だ。しかしながら、そんなことにこだわっていては、競争社会からとりのこされるだけと思う人も多い。今風の社会の在り方と、その急激な変化に常に順応していかなければ、会社も滅びてしまうのだろうか。
何はともあれ、原点は企業のサバイバル、サウンドハウスの存続だ。そのベースがあってこそ、初めて自分やスタッフ一同が、社会に対して「もの言い」できる。サウンドハウスの事業が成功し続け、収益力を維持することにより、みんなの生活が楽になり、人生の日々を、自信をもって楽しく過ごせるようになる。それがゆとりにつながり、社会貢献の働きにも加担できるようになる。では、どうしたら、それが実現できるのだろうか。会社が存続して、皆が幸せな人生を送るためには、何をするべきなのだろうか。結論はただひとつ。みんなが一生懸命、知恵を尽くしながら働くことにつきる。しかも自己中心の思いからではなく、周りと協力しながらひとつ思いになって、会社のため、みんなのため、そしてお客さんのために頑張ろう、という思いが大事なのだ。つまるところ、みんなの努力があり、みんなの思いが繋がって、素晴らしい結果を出すことができるようになるのだ。
サウンドハウスは今や、国内最大級の会社だ。ちょっとやそっとでは、こけない。が、ここからの成長は、極めて難しい。何故なら、社会環境が激変しているだけでなく、みんなの協力や、ひとつ思い、という大切な心構えさえ実現できないでいるからだ。以前のように、「全員、右へならえ!」「突撃!」と言って、大将にみんながついてくる時代は終焉した。今では振り返ると、誰もいないような状況は不思議ではない。それがごく当たり前の現象なのだ。ではどうやって、みんなをまとめることができるのだろうか?周囲の競争は激化し、競合他社はもっとハードに、サウンドハウスを撃沈するためにあらゆる細工を凝らしているのは間違いない。このままでは会社の存続さえ危ぶまれる。
行きつくところ、サウンドハウスも米国テスラ社のトップ、イーロン・マスク氏率いる米ツイッター社から施策を学ぶべきなのかもしれない。マスク氏は世界の時流に逆行して、会社が赤字から脱出し、収益体質を改善して末長く存続するために、社員に対して全員が長時間の猛烈な労働を受け入れるか、退社するかの選択を求めた。すごいことだ。その結果、11月17日の時点でツイッター社の正社員7,500人のうち、少なくとも1,200人が退社したと言われている。
このマスク氏の横暴とも言える発言を機に、ツイッター社が衰退し、こけてしまうと思う人が世間では少なくない。何しろ多くの社員から会社が見放されてしまったのだから。しかし、どうもそうは思えないのだ。むしろ、これを機にツイッター社が思いもよらぬ方向に変貌し、成長路線を走ることになるのではないだろうか。マスク氏は経営の天才だ。その彼が黙って会社の衰退を見過ごす訳がない。多額の投資もしているからには、思いもよらぬ多くの施策を手玉にして、彼が持つビジョンのとおりにこれから実行していくとみている。
いずれにしても、残された社員は猛烈に働くことを承知したうえで残留し、しかも他の社員がいなくなった分まで働かなければならない。それは大変な時間の拘束にもつながるが、それに応じて手取り収入も大幅にアップする。それだけがインセンティブとは言えないが、実際に給料が増えるわけだから、仕事にも熱が入る。つまり、本当に会社のため、ユーザーのために一生懸命働きたい人が残った会社になるので、結果を出せる可能性がより高くなったと言える。
今日のサウンドハウスは、ゆるキャラ感にあふれ始め、昔と比較すると緊張感がなくなってきたように見える。まさに大企業病のはじまりだ。やるべきことがたくさんあっても、責任をもって完結しようという気構えで、周囲と相談しながらひたすら仕事に取り組むスタッフが少なくなってしまった。上下関係も希薄になり、特に人に教えることができる人、他人に積極的に関わっていくことを苦にしないスタッフが激減してしまった。ありきたりの与えられた仕事しかこなすことをせず、何ら意見も言わず、改善案も出さず、同じ仕事を毎日こなしていくだけのスタッフが多くなった今、もはや結末は見えている。行きつくところは赤字決算、そして組織のほころびであり、それを回避する手立てがなかなか見当たらない。
だからこそ、今、改革が必要なのだ。その改革とは、もっと、もっと、猛烈に仕事しよう、結果を出そう、一緒に社会を変えていこう、という力強いメッセージに尽きる。マスク氏の考え方に共感を覚えるのは決して自分だけではないはずだ。やるべきことがあれば、今、やってしまう。それを実行できる会社のみが、成長できる。これが鉄則なのだ。しかしふと、考えてしまう。これも果たしてはかない妄想にすぎないのだろうか。