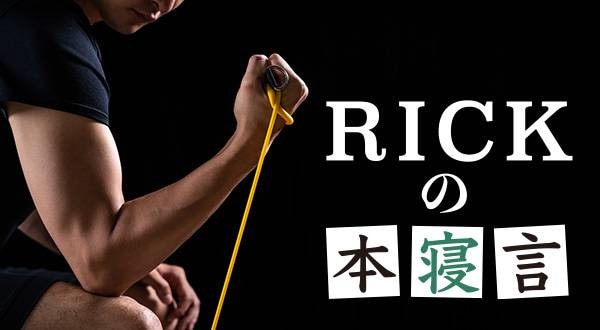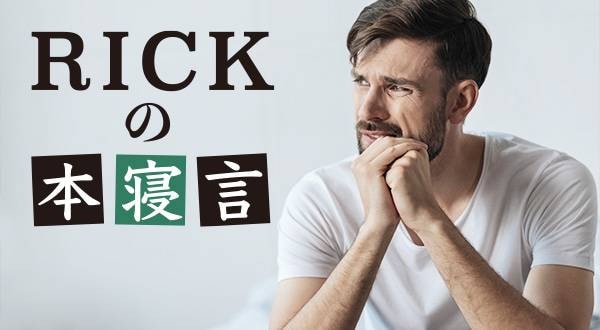8月29日、昨今、テレビでも大人気のお笑いコンビ、サンドウィッチマンが女川のシーパルピアにて番組の収録をする際、サウンドハウスの女川ショールームにも来られることになった。しかもその後、我が社が誇る女川ロジスティクス・センター、旧女川中学校も訪ねてくださるとのこと。嬉しい限りである。そもそもサンドウィッチマンのコンビは、2人とも宮城県仙台市の出身だ。よって同じ宮城県民として、震災で壊滅的な被害を受けた女川町にもさまざまな思い入れがあるはずだ。そんな彼らが、サウンドハウスが構築した女川の施設を訪ねてくださるというので、ありがたい。
8月29日、昨今、テレビでも大人気のお笑いコンビ、サンドウィッチマンが女川のシーパルピアにて番組の収録をする際、サウンドハウスの女川ショールームにも来られることになった。しかもその後、我が社が誇る女川ロジスティクス・センター、旧女川中学校も訪ねてくださるとのこと。嬉しい限りである。そもそもサンドウィッチマンのコンビは、2人とも宮城県仙台市の出身だ。よって同じ宮城県民として、震災で壊滅的な被害を受けた女川町にもさまざまな思い入れがあるはずだ。そんな彼らが、サウンドハウスが構築した女川の施設を訪ねてくださるというので、ありがたい。
そもそも何故、サウンドハウスは女川に進出したのだろうか。今一度、これまでの経緯を振り返り、社員みんなの理解を深めたいと思う。サウンドハウス創業者である自分と女川との出会いは、運命的なつながりの連鎖にある。その原点は、東北地方の山々を登山していたことから始まった。2020年の秋、毎週のように東北地方の田舎を訪ねて回り、そのついでに青森県から山形県、岩手県の最高峰となる山々をトレイルランしていた。自分の足で山々を登り、頂上からの景色を見渡して大自然の地勢を自分の目で確かめることにより、古代の人々の思いに寄り添うことができるような気持になる。
その東北地方の山々を一巡した最後の登山が、宮城県の金華山となった。金華山は沖合の島にあり、標高は444mしかない小高い山である。しかしながら、島には金華山黄金山神社があり、その神社を3年続けてお参りすると、一生お金に困らないという伝承があることから、毎年、大勢の観光客が船に乗って訪れる。その黄金山神社の裏山が御神体となる金華山だ。その山に何としても登って、2020年を締めくくりたいと願っていた。そして11月も下旬になり、冬の到来が早い地域でもあることから、もう登山は諦めるしかないと思っていた矢先、23日、突然、夏日のような暖かい日が訪れることがわかり、これはしめたと、金華山にはせ参じた。
金華山の登山が無事、終了した1週間後、ノーアポで見知らぬ2人のビジターが成田本社を訪ねてきた。聞くところによると、宮城県でギターリペアショップを経営している方が、サウンドハウスと業務提携したいということだ。そこで2人にお会いすると、一人は銀行の支店長。もう一人は、その会社のオーナーさんだった。そして「どちらからおいでですか?」と訊ねると、なんと「女川から来ました!」と言うのです。とっさに自分は、「え!!1週間前、僕も女川にいましたよ!」と答えた。そう、金華山に行くには、女川から船に乗ることから、自分も女川にて時間を過ごしていたのです。
 そこから話はとんとん拍子に進み、彼らは自分が何故、金華山に登ったかという理由に耳を傾けてくれた。それは単なる登山でもなく、探索でもなかった。震災の被害にあった山の状況をこの目で確認し、必要に応じて島の整備に協力しようと思っての登山であり、目的は明確であった。実際、金華山で目にしたのは、震災後に全く手をつけられていない倒木の数々であり、それらの多くが登山道と周遊道を塞いでいる光景だった。「これでは登山客が来れるわけがない!」。そこで木の伐採を得意とする自分がボランティアで木を伐るしかないと思い立ち、年内にもう一度、金華山を訪ねるプランを立てることにした。その話を2人にすると、何と銀行の支店長は、「自分もボランティアとして手伝わせてください!」と言うのだ。大木が200本近く倒れている道を切り開いていくのは生半可な仕事ではなく、肉体的にとてもきついですよ、と忠告はしたものの、是非とも、ということで、その1週間後、2人で一緒に船をチャーターして、金華山に行くことになった。
そこから話はとんとん拍子に進み、彼らは自分が何故、金華山に登ったかという理由に耳を傾けてくれた。それは単なる登山でもなく、探索でもなかった。震災の被害にあった山の状況をこの目で確認し、必要に応じて島の整備に協力しようと思っての登山であり、目的は明確であった。実際、金華山で目にしたのは、震災後に全く手をつけられていない倒木の数々であり、それらの多くが登山道と周遊道を塞いでいる光景だった。「これでは登山客が来れるわけがない!」。そこで木の伐採を得意とする自分がボランティアで木を伐るしかないと思い立ち、年内にもう一度、金華山を訪ねるプランを立てることにした。その話を2人にすると、何と銀行の支店長は、「自分もボランティアとして手伝わせてください!」と言うのだ。大木が200本近く倒れている道を切り開いていくのは生半可な仕事ではなく、肉体的にとてもきついですよ、と忠告はしたものの、是非とも、ということで、その1週間後、2人で一緒に船をチャーターして、金華山に行くことになった。
そのボランティアの旅の途中、支店長といろいろな話をしている中で語られた話が、旧女川中学校の一件である。女川町が、震災で残された校舎のいくつかを売却することが広告されているということだった。何故か、その話に無性に興味を惹かれたのだった。そもそもサウンドハウスの歴史は、すべて居抜きの古屋をそのまま使用してきている。創業当初は山田洋服店の8畳間バラック小屋。その後は、民家の1Fガレージと2F、次は建物が傾きかけたディスカウントストアーを丸ごと借りている。その次は、閉店したスーパーマーケットの2階建ての建物を、そのまま使わせていただいた。そして今の本社は、アメリカの半導体メーカーの工場であったビルを、中を壊して空にして使っている。こんな社歴を踏まえてのことなので、女川でもサウンドハウスが廃校利用して進出する可能性があるのではと思えてきたのだった。
 確かにロケーションは浮かばれない。何しろ遠隔地なる沿岸の田舎町。しかもそこにいくには道路1本しかなく、電車もディーゼル車の汽車に乗って仙台からは石巻経由で乗り継がなければならない。よって、全国に商品を出荷する我が社の物流拠点としては、あまり芳しいセッティングとは思えなかった。それでも、いくつもの魅力が浮かんできた。まず、旧女川中学校の規模が、成田本社の土地建物と同等であるということだ。広い土地は将来的な拡張性の余裕があることを意味する。これが重要だ。そして女川で会社を運営することにより、過疎化が進む地域での雇用を創生し、地方社会において会社として貢献することができる。これが極めて重要なポイントに思えた。また、音楽を通じた子どもたちの育成と教育にも関心があったことから、女川を音楽のまち、と位置付けて、まちづくりができる可能性に魅了された。
確かにロケーションは浮かばれない。何しろ遠隔地なる沿岸の田舎町。しかもそこにいくには道路1本しかなく、電車もディーゼル車の汽車に乗って仙台からは石巻経由で乗り継がなければならない。よって、全国に商品を出荷する我が社の物流拠点としては、あまり芳しいセッティングとは思えなかった。それでも、いくつもの魅力が浮かんできた。まず、旧女川中学校の規模が、成田本社の土地建物と同等であるということだ。広い土地は将来的な拡張性の余裕があることを意味する。これが重要だ。そして女川で会社を運営することにより、過疎化が進む地域での雇用を創生し、地方社会において会社として貢献することができる。これが極めて重要なポイントに思えた。また、音楽を通じた子どもたちの育成と教育にも関心があったことから、女川を音楽のまち、と位置付けて、まちづくりができる可能性に魅了された。
決断は自分がするしかない。創業者として、サウンドハウスオーナーとして、洋服店のバラックから会社をはじめ、その後、ディスカウントストア、スーパーマーケット、半導体工場と、点々と社屋を移転しながら会社を大きくしてきたが、その最終ゴールに旧女川中学校があったのか!と不思議に思えてきたのだ。しかしながら、そこを物流センターにするには、ハードルが高い。建物の修繕費も想像を絶するほどかかるだろうし、宅配の輸送コストも成田や徳島よりは高くなることが想定された。しかも4階建ての校舎には当然ながら、エレベーターもない。これは物流作業にとって、大きなハンデとなる。そして多くの人を雇用しなければならないのだが、女川界隈では誰も知らず、つてもない。よって普通だったら諦めてしまうだろう。それを諦めきれずにやっちまえ!というのが、サウンドハウスの良い所だ。その責任はすべて自分にある。正に命をかける戦いとなることは覚悟のうえで、勇断に踏み切った。
その後、女川のオペレーションは、物流系のロジスティクスセンターを旧女川中学校に構築するだけでなく、駅前のシーパルピア・ショッピングセンターには、サウンドハウスの女川ショールームもオープンした。子どもたちのための無料音楽教室の運営も順調に進んでいる。どちらもまだ、よちよち歩きの状態だが、これからの成長が楽しみである。
普通の会社なら絶対に手をつけないようなことを、堂々と展開し、しかもそこから想像を超える結果を出していく。それが我が社の醍醐味であると自負している。日本の音楽業界を変えてきたサウンドハウスならではの、最後のチャレンジになるかもしれない女川での働きから、目が離せない。そこから連日、1,000件の出荷がある日は、そう遠くはないかもしれない。

旧女川中学校に構築された物流センター