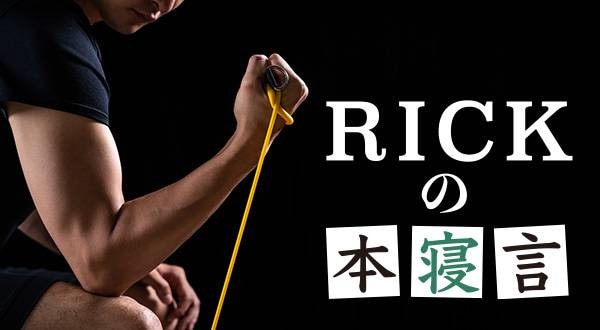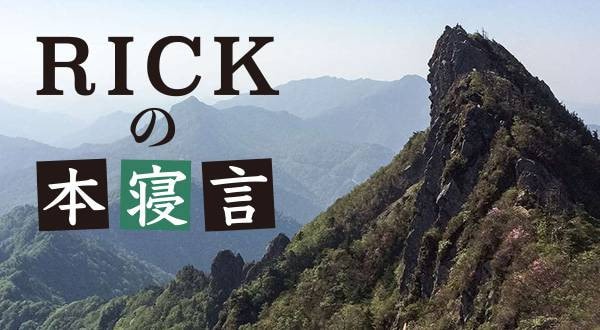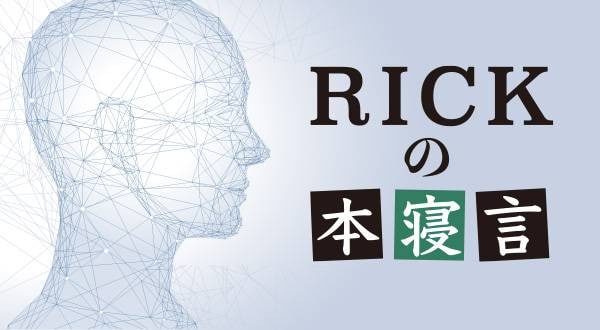「人はうわべを見るが、神は心を見る」、こんな言葉が旧約聖書のサミュエル記上に書かれている。世の中、お互いが神様のように心のうちを見通すことができるならば、コミュニケーションがスムースに進み、余計な争いがなくなるのでないか。ところが現実は違う。相手の思いや心中を察することは難しく、話し合いを持ちながらお互いが理解を深めていくようなケースは稀だ。そして残念なことに多くの場合、人は見た目と、他人から聞いた噂話のような風評に流されて、思い込みのままに相手を判断して決めつけてしまうことが多いのだ。
例えば筆者は、この2か月間で2度、自分のことをあまり良く知らない、ほとんど話さえしたこともない人から、「会長はワンマンだから!」と言われてしまった。ひとりは初対面の方で、たまたまちょっとだけ会社を訪ねてきた人。もうひとりは音楽業界以外の方だ。大変、残念なことだ。何故なら事実と全く相違するからだ。ワンマンな会社経営者とは、独善的に自分勝手にひとりで何でも決めて、会社を先導していく、いわば強引な経営者のことを指す。どこからどう見ても、そのようなワンマンと言われる筋合いはないほど、自分の経営スタイルは似ても似つかない。けれども、見た目から、そう思われてしまうのだろうか?
そもそも自分はワンマン経営者になれる訳がない。何故ならコロナ禍により、一層、身の回りのテレワーク化が進み、その結果、会社に顔を出すことも少なくなったからだ。現場の仕事にはあまり関わることがなくなったので、そもそも会社に行く必要がないのだ。日々、スタッフと関わらない、自分にしかできない仕事を経営者としてこつこつとこなしている。また、何か用があれば、メールかLINE、電話で十分なことから、大半の部署管理はほぼすべて、管理職の立場にあるリーダーにお任せしている。こうして物流も、システムも、技術も、WEBも、経理もほぼ、完全に任せっきりの状態が長年続いているのだ。
自分が会社の経営者として関わる業務の中には、みんなができないこと、決められないこと、わからないことを率先して実践することが含まれる。決して自慢話をする訳でもないが、自分が直接手掛ける仕事の中には、時にはそれは誰もがやりたがらない、一番汚く、大変な仕事がある。そのような醜い仕事をスタッフに押し付けることなく我慢してやることが、自分の役目だ。よってこれまで屋根上のヘドロ掃除、大型倉庫に溜まった5年分の大型ゴミの片付け、樹木の伐採をはじめ、時差があるための夜中の海外業務、スタッフのための細かいマニュアルの執筆など、自ら率先してこなしてきた。時にはなんで自分がしなければならないのか、と思うこともあるが、まあ、仕方ない、といつも割り切っている。
それでも営業系の一部業務に限っては、未だに口出しをすることにしている。別に関わりたいわけでもないが、自分がやらなければ処理が滞ると判断したら、ぱっと手を付けて自分でやってしまうか、またはアドバイス、指示をだして、なるはやで仕事が終えられるように導くことが大切だと考えている。営業リーダー間でさえ、時にはもたもたして決断できずに遅延している業務が散見されることから、相手方に迷惑がかかるなと思えば、あえて介入し、判断を促すか、自分で決めてあげている。そうすることによって、スタッフは自己責任から解放され、「会長が決めたのだから、もう大丈夫」と安堵することだろう。そういう一部だけの姿を見て、ワンマンと思うスタッフもいるかもしれない。迷惑なことだ。
いずれにしても、ワンマン経営者になるには、自分の敷居があまりにも低すぎるのではないか。そもそも自分はスタッフ、社員一同との距離があまりない。そういう距離感や肩書を好まないから、それでいいのだ。よって頻繁にいろいろな部署のスタッフとご飯や飲み会に行き、さまざまイベントにも一緒に参加して騒いでいる。時には一緒に旅行もする。特にここ最近は若手20代のスタッフと行動を共にすることが多くなった。一緒にお酒を飲んでも今の若い連中はお酌をしてくれるわけでもない。あえて手酌が当たり前とわきまえている。それでもいいと思っている。多くのスタッフとのLINEやメールのやりとりも頻繁にあること自体、それも敷居が低いことの証ではなかろうか。
そのような実態があるにも関わらず、ワンマンに見られがちな理由がひとつある。それは新規事業やプロジェクトはスタッフの手が足りず、また、教育にも時間がかかるため、自分しか率先してやる人がいないことだ。現状では新規事業にまで手が回るほど、社員数が潤っていないのだ。よって、新規事業においては自分が先導して何でもてきぱきと仕切ることになり、端から見ると、会長がワンマンにすべてそのように経営管理していると思われるのだろう。特に新規事業とは音楽関連とは程遠い業務内容が多く、その管理を任せられるような経験をもっているスタッフがいないことがほとんどだ。
例えば昨今の女川での展開を振り返ってみよう。サウンドハウスは旧女川中学校を取得した。震災の被害にもあった築55年以上の建物で、凄まじい状況になっていた。よって取得後の仕事と言えば、その校舎の清掃、側溝の掃除、雨漏りの修繕、アスファルト舗装の補修、トイレの水回り修復、断水の調査、および、諸行政とのやりとりだ。そんな経験をもっている若手社員がいる訳がない。よって、以前デベロッパーとして不動産業に携わっていた自分がひとりでコツコツとこなしていくことになる。そのうえ、校舎の窓掃除、床掃除、となると、気が遠くなるような量の肉体労働になる。そこで単純作業の場合は現地の新人スタッフを集め、自らが陣頭指揮するしかない。こういう一面を外部の人が見ると、女川で雇用したスタッフも含め、会長はワンマン、ということになるのだろう。
つい昨日も、旧女川中学校の校舎裏側に、高台の方から雑木と雑草が、トラックが通れないほど道路にはみ出していた。ものすごい量だ。ワンマン経営者ならば、「おい、君、これらをすぐに切りなさい!今すぐだ!」と言うでしょう。が、そこにいた2人のスタッフは荷物の荷下ろしでくたくたな顔をしている。よって当然ながら自らチェーンソーを倉庫から持ち出し、2mの梯子をまっ直ぐに伸ばして4mにし、その高台にまで登って枝を伐る作業をした。これは実は、大変危険な作業である。足場も悪いし、なんの準備もしてなかったのだが、幸い着替えだけはあったので、作業靴に履き替えて、木の枝と雑草を汗だくになって伐っていった。野ダニに襲われる心配もあり、バラの棘も痛く、そんな姿をみて哀れに思われたのか、荷下ろしを終えた2人が下からサポートしてくれ、伐った枝を片付けたり梯子を動かしてくれたので、一気に仕事は進んだ。が、強烈に体力を消耗した。
人がやらないこと、できないことをやる。決められないことを決めてあげる。そして結果をすぐに出す。それが経営者としての自分の使命だと思っている。よって、会社の仕事9割以上、全く関わっていないが、最後の1割弱において、会長としての義務として、責任もって対応している。内心、それも特にやりたいことではない。できればやりたくないというのが本音だ。しかし会社のことを考えると、自分がそこで介入しなければ、お客様や、対業者に迷惑がかかってしまう、と思うと、またしても責任感から手を出すことになる。それが会長業としての自分の宿命だ。
いつか社員みんなが英語もできるようになり、海外業者とのお付き合いも個々に信頼関係を深めることができ、社内コミュニケーションも活性化し、単に人との話し合いが上手になるだけでなく、リーダー格の人がどんどんと物事を提案して決めていくようになってくれればと思う。そして営業スタッフみんなが商品知識をまんべんなく習得し、自分たちで新製品の提言をして続々と市場に投入できるようになり、なおかつ、新しい技術を駆使して業務の効率化を実現できるようなシステム改善の企画を積極的に立案、実践することができれば、自分は本来の会長職として、それらの報告を受け、時には説明をしてもらい、うなずく程度となる。まさにそれが自分の夢だ。