こんにちは、Cheenaです。今回は、私の本業、中学・高校の吹奏楽部におけるエレキベースの演奏について書いていきます。
エレキベースの演奏について入る前に、まず、吹奏楽の編成についてざっくりと説明していきましょう。
吹奏楽におけるエレキベースの存在
吹奏楽は基本的に管楽器を主体に、少数の打楽器と弦楽器、そしてそれ以外の楽器を追加して演奏されます。
各楽器の人数や楽器の種類は国や地域によって異なり、日本では基本的にフルート、クラリネット、オーボエ、サックスから成る木管群とトランペット、ホルン、トロンボーン、ユーフォニウム、チューバからなる金管群、バスドラムやティンパニ、スネアドラム、シンバル、グロッケンシュピール、マリンバなどの打楽器群とコントラバス、ピアノ、ハープなどのわずかな鍵盤楽器、弦楽器などを使用します。

お気づきの通り、この編成の中にエレキベース、エレキギターはありません。ポップスなどを吹奏楽に編曲した楽曲では使われることが多いのですが、全日本吹奏楽コンクールでエレキギター/エレキベースの使用は認められていません。
コンクールなどではない学園祭や定期演奏会ではギターは曲に合わせて弾ける人が、ベースはコントラバスの持ち替えとして演奏されることが多いです。
しかし、ごく一部の楽団にはコントラバスがないこともあり、コントラバスを使わずにエレキベースを演奏する人もいます。そのような場合はコントラバス以外の低音楽器からの持ち替えを行うことが多いです。私もその一人で、チューバとエレキベースの掛け持ちで演奏していました。
さて、編成上は、エレキベースは低音楽器に入ります。しかし、リズム隊に入るか、メロディ隊なのか、ハーモニー担当なのかと言われると微妙なところがあります。
こういう時は、総譜を見て考えましょう。(著作権的な問題から画像を載せることはできませんが、頑張って説明します。)
エレキベースのパートがあるほとんどの総譜の中では、エレキベースはチューバの下、パーカッションの上にコントラバスと統合され、C.Ba(E.Ba.)と書かれています。又は、コントラバスの下に単独でE.Ba.と書かれています。記譜はチューバなどの低音管楽器とほぼ同じで、E以下の音は一オクターブ上げるなどして書かれています。場所により、チューバよりも細かい連符を弾くように書かれていますが、ウォーキングベースやポップスでベースが動き回る曲以外でコード進行の基音から外れていくことはほとんどなく、メロディに食い込んでいくことは全くと言っていいほどありません。
なお、8分音符などの動きが多い部分のスコアを読み込んでみると、アクセントや山形アクセントが書かれている場所は大抵その他低音楽器の音符の開始位置と一致します。これは低音楽器側のリズム感を把握するために(又は、他に低音隊がいない場合でもリズム感を失わないように)あると予想できますね。
オーケストラ曲にありがちな「1つの譜面に1st、2nd、3rdなどが書いてあり、1つの楽器隊の中での和音を要求される」ということもなく、多少動きがありながらも基音が基本、という原則は維持されています。
つまり、吹奏楽におけるエレキベースはリズム隊の一環で、チューバやコントラバスにはできない細やかな動きをさせる、パートの要求人数は1名、ということが考えられます。
では、吹奏楽の中でエレキベースはどのように演奏すればよいのでしょう。
チューバとバリトンサックスは音量と音圧に優れ、低音楽器の主軸として扱われます。バスクラリネットやファゴット、ユーフォニウムは前述のものと比べて音量には劣るものの、機動性の高さからリズムとメロディ、そしてハーモニーを全て演奏できます。エレキベースに良く似た、というより先祖であるコントラバスは「演奏全体の雰囲気を変えてしまう楽器」と言われます。音量は少ないものの、共鳴胴を持ち、弓を使ったアタックのない、そしてほぼ無限に長い余韻を持つ音は管楽器には出せないサウンドを提供します。しかし、これはエレキベースではE-BowかFernandes Sustainerでも使わない限りは出せません。
強いアタックと高い機動性を併せ持ったエレキベースは、ロックミュージックにおけるエレキベースと同じように純粋なリズム隊であり、サイレントベースやコントラバス、その他管楽器には代用の効かない独自性の高い楽器なのです。
実際に、エレキベースをリズム隊に仕立て上げる方法
吹奏楽で、エレキベースを使用した演奏を聴くと、「これがベースだ」と言える音は聴こえないことがほとんどです。そこで実際に演奏を見たり、動画を確認すると、9割以上はJazz Bassを使っています。本体のセッティングは、基本的にトーン含めてオール10。アンプは50W程度のもので、イコライザーが全て5、ゲインとボリュームは適時のことが多いでしょうか。そして、ほぼ確実にアンプ直結です。Marshallアンプにセミアコベースを投入したり、RolandのJazz ChorusにJaguar Bassという渋いセレクトの人もいますが、そのような人は軽音楽部とのつながりがある、バンドを組んでいるなどの要因で楽器にこだわっていると考えられますが、ごく少数です。

話が逸れました。Jazz Bassは2つのピックアップとトーン回路により、多彩なサウンドを出せることが魅力ですが、先程のようなセットアップでは残念ながら高い音圧と大音量を持つ管楽器の中では聴こえないでしょう。しかし、コントラバスの音量に慣れてしまっているのか、エレキベースの音量が小さすぎると指摘されることはありません。必要な部分の音量を上げていく必要があります。
ただし、単純に全体音量を上げていくとベースの金属質な音は管楽器とぶつかり、削ろうにも音量以外削れないということになります。JazzBassであればフロントに全振りする、トーンを絞る、アンプのMidやBassを上げる、TrebleやPresenceを下げるなどして柔らかく太い低音を出せるようにします。
しかし、これにも限界はあります。軽音楽などとは環境があまりにも違いすぎるためにエフェクターを導入する必要があります。
エフェクターからの音作り
「エフェクターを導入する」と書きましたが、当然一般的なバンドや軽音楽におけるエフェクター構成とは異なってきます。
必須となるのは、コンプレッサーやプリアンプ、ペダルチューナー、ボリュームペダルでしょうか。マルチエフェクターでも問題ないですし、その方が安価ですが、それぞれをペダルで集めると調整や演奏中の切り替えが楽という利点があります。
ただし、飛び道具系エフェクターはほぼ使わないので設定が整ったマルチを置いておくだけでも問題ありません。

一応、小型でも9V電池を導入可能なOne Controlなどのエフェクター、あるいは9V電池をDC入力に変換するプラグもあるにはあります。
コンプレッサーの調整
コンプレッサー、又はリミッターは音量を揃えるのに使いますから、曲を問わずずっと掛けていて問題ありません。いわゆるDynacomp系コンプ(アタックが遅く、ポコポコした音になるコンプレッサー)
はかなり目立つ音質になるため、その逆に「ナチュラル系」で「滑らか」などと言った音を売りにするものを選びます。慣れればこれ1台で済むUrei 1176(Universal Audio 1176)インスパイア系のリミッターは独特の味のある音質になり、「ご機嫌な音」と評される太さが扱いやすいですが、高価です。 圧縮は強めに、管楽器のロングトーンを出すイメージを持って調整します。最終的には、後述のノイズリダクションと合わせて太く、切った瞬間にスパッと切れる音になるのが理想的です。音質調整の際はサウンドハウスの最強コンプレッサーマニュアルを参考にするとよいです。
なおコンプレッサーとリミッターの違いについては、小さい音を大きく大きい音を小さくするのがコンプレッサー、大きい部分を切り捨てるのがリミッターと考えて問題ありません。ただ、リミッターにもゲインやサチュレーションといった音量増加回路はありますし、コンプレッサーでも圧縮率を∞に設定すればリミッターと同じ出力になります。どちらが良いというものではないので好きに選びましょう。
確実に言えるのは、リミッターを使用すると前述のアクセントは全て潰れるということになります。が、その他の楽器が補うためそこまで問題はありません。
プリアンプの設定
プリアンプは前述のアンプの調整と同じように、演奏の中での聴こえ方を改善することができます。コンプレッサーとイコライザーとプリアンプが一つにまとまったタイプのものでもいいでしょう。プリアンプ単独ではTech21 Sansamp、Ampeg Classic Analong Bass Preampなどがあり、コンプレッサーを内蔵したものにはElectro-Harmonix BattalionやVivie Owlmightyがあります。歪みは軽く掛けておくと管楽器への馴染みがよくなりますが、深すぎると悪目立ちし、ノイズも増え、音量制御も難しくなるので本当に軽くにしましょう。
が混ざっています。こちらは単独型プリアンプに近い機能ですが、当然音質が独特なので注意しましょう。
ボリュームペダルの必要性
ボリュームペダルは吹奏楽を演奏するうえで絶対に必要と言っても過言ではありません。演奏中に頻繁に音量が変わる、特にSub.pfなどの指示がある吹奏楽曲の中で、エレキベースだけが音量変化に付いて行けず目立ってしまうようでは逆効果ですし、ピッキングの強さや本体ボリュームで音量を調整するのにも限界があります。MC中にノイズが流れることも防げます。
ボリュームペダルを選ぶ際、パッシブベース・ギターなど電池を使用しないものから直接繋ぐ場合は高インピーダンスのものを、電池を使用するアクティブベースやエフェクターから繋ぐ場合は低インピーダンスのものを選びます。分からない場合はBossのFVシリーズを選び、高インピーダンスにはH、低インピーダンスにはLが型番に入った方を選びます。エクスプレッションペダルは外部エフェクターを制御するためのものなので必要ありません。こちらはピッチシフターやトレモロなどの制御に用います。
ノイズリダクションの使用
必要に応じて、ノイズリダクションでホワイトノイズ(サー音)を消していきましょう。楽器本体からノイズが出る時は最初に、エフェクターから出る時は該当エフェクターの後段、又はSend/Returnに接続します。
少し上級者向けの調整になりますが、深めのノイズリダクションとコンプレッサーを組み合わせることで「音の立ち上がりにはある程度の息の流量を要し、小さい音はある一点ですっと消える」通常の管楽器と同じような音量の挙動をさせることが可能です。音の消え方をノイズリダクションのカットで再現することで、ノイズに混ざりながらも鳴り続ける弦の余韻を殺すことができます。
上記のうちノイズリダクションを除いた3つがベースの音を自然に聴こえるようにするための最小構成でしょう。ベースを極めればボリュームペダル1個で参戦もできますが、単純に難易度が高いです。
チューニングについて
また、演奏していると温まってチューニングが上がる管楽器と違い、エレキベースは演奏を長くしているとペグの緩みと弦の熱膨張によりチューニングが下がる楽器です。ステージ上でもチューニングを行いましょう。カードチューナーはステージ上ではお勧めしません。マイクを繋ぐのがまず面倒ですし、ライン入力する場合にはシールドを抜く作業が発生します。楽器側のVolを下げてクリップチューナーを使うか、ペダルチューナーを踏んで出力をキルする、というのが安全かつ円滑な作業ができる選択肢です。
なお、チューナーの選択時に基準ピッチが変更可能か、という問題は非常に重要です。
一般的にはA4=440Hzを採用することが多いものの、楽団によっては442Hzなどを選択することもあるため基準ピッチが変更可能なチューナーを使用しましょう。 大抵は変更可能ですが、異様に安価なものでは変更不可ということもあります。簡単な見分け方としては、クリップチューナーにボタンが1つならオンオフのみ、2つ以上なら基準ピッチ変更を含む何かしらの機能(Drop Dや半音下げチューニングする対応など)がある、となります。ペダルチューナーの場合はフットスイッチ(ON/OFF操作)以外に1つあれば基準ピッチ変更可能なものが大半です。2つ以上ボタンがあるならディスプレイ表示変更や半音下げ対応などの機能も付きます。ちなみにRowinのPOWER TUNERやTUNER、MooreのBaby Tunerはボタンが無く、基準ピッチ変更ができませんので注意しましょう。
また、電源喪失状態でも基準ピッチなどの設定が保持されるかどうかというところも大きな論点となり、BOSS TU-3やtc electronic PolyTuneといった少々高価なチューナーが好まれる要因の一つでもあります。
とはいえ、これ以外の機能を持っていたりいなかったりするのがチューナーの世界。説明書を読んだり、問い合わせや店頭での確認などを行って正しく楽にチューニングしましょう。
閑話休題。ロックの吹奏楽編曲などでベースに目立つことが許された場合はどのような構成にするのか、考えていきましょう。
このような編曲では同時にギターを導入したりドラムセットを設置したりするため、ベースも追随することができます。
ここで導入するのは、オーバードライブやイコライザー、さらなる低音のためのオクターバーなどでしょう。歪みを使って音量と音圧を稼ぎます。あまり歪ませすぎるとリズム隊としての役割を果たせなくなる、またアンプ側のワット数が小さいとそちらでも歪むため注意してください。リズムギターは重めのクランチ~オーバードライブがお勧めですが、リードプレイが必要な場合は思い切りディストーションを掛けてもいいでしょう。
ベースの方は中低音を盛って太い音で前面に出るか、低音と高音を追加したドンシャリで派手に決めるかは楽団・部ごとの編成や曲調と合わせて考えましょう。
Deep Purple Medleyなどでドラムスが強く、トランペットも一緒に暴れているような状態なら先ほどのDynacomp系コンプレッサーやエキスパンダーなどのアタックを強調するエフェクターを解禁し、ドンシャリにしたセッティングで輪郭のはっきりしたパーカッシブなサウンドにしてもいいですし、Queen Medleyなどおとなしめのブリティッシュロック系の曲であれば中低音強めのセッティングで正確なリズムを刻みます。
ジャズ編曲などではコントラバスが優先されるでしょうが、エレキベースが必要になった場合はマルチエフェクターのパッチを使用するのが手っ取り早いでしょう。
One ControlのCrimson Red Bass Preampで再現も可能ですが、このためだけに用意するには少々高い買い物になります。
ベース用マルチエフェクターではフレットレスシミュレーターやアコースティックシミュレーターなどでコントラバスに近いサウンドにするか、高域を減らしたジャズギター風の甘いサウンドに寄せてウォーキングベースを弾くというのもできます。
「エアー感」と一般に称されるコントラバスやフレットレスベースの浮遊感を出す際にはコーラスが有効になる場合があります。ただし、音程が揺れてしまうのには注意しましょう。揺れを減らしたディメンションコーラスというものもありますが、高音域に掛かって威力を発揮するエフェクターのため、ベースではよく分からないということもあります。
逆に、採用すべきでないエフェクターも幾つかあります。
まずロングリバーブ。一見自然な音を出すように見えても、演奏のキレをなくす要因になります。
そもそもホール自体が余韻を残すように作られていて、かつピアノやバスドラム、ティンパニにも反響すると考えるとベースが能動的に余韻を残す意味はありません。
コントラバス的奏法を狙ってビブラートを掛けておくというのも、あまり良くはないですね。EXP端子から揺れ幅を調整するのも大変です。
その他、オクターブファズなどの飛び道具に近いエフェクターは譜面に明記されていない場合、あるいは原曲で使われていない場合には使用しないようにしましょう。
アンプからの音作り
アンプ側はできればある程度の大きさがあり、大音量でも歪まない(ヘッドルームが大きい)ものを使用したいところです。
ヘッドとキャビネットが分離している必要はなく、コンボアンプでクリーンの音が良いVOX ACやRoland Jazz-Chorusなどが簡便でしょう。
ベース専用アンプでなくてもまあ問題なく使えますが、あまりにも出力が大きかったりスラップしたりするとスピーカーコーンの破損、あるいは配線焼損の原因になります。また、イコライザーがベース帯域に寄せられていないことがあり、手元・足元での調整を精密に行う必要が出てきます。
ちょっとした遊び方としては、アンプ2台をステレオで使用することにより音の広がりと音量を同時に得られます。似たタイプの歪み2種類やステレオアウトの空間系エフェクターを使用する際には検討しましょう。
奏法からの音作り
一般的にはベースは2フィンガー奏法で演奏しますが、それ以外の奏法で硬い音、柔らかい音を作り上げることも可能です。例えば、時折ピックガード右側に付いているフィンガーレストを使用したサムピッキングや、ピックを使った硬めのサウンドなどもできますが、直感に反した音を作ることもできます。
例えば、一般的なピックを使うとスクラッチノイズによりアタックが際立ってしまいますが、動物の骨や角、木材、最近人気の超高分子量ポリエチレンなどの分厚いピックを使うと柔らかいながらも太く、強い鳴りを生み出すことができます。逆に指弾きでもリアピックアップに親指を置いてはっきりとした音を作るなどできます。
ハーモニクス音を使用する際は案外指弾きと聞き分けられないことが多いです。が、低音隊含めたほかの楽器がいない場所では投入してもいいサウンドです。
たとえば秋吹版おジャ魔女カーニバル終盤サックスソロの裏など、あまり乱用するのではなく緊張感とリズム感を保つ目的で使用すると捉えましょう。
楽器からの音作り
シングルコイル以外のピックアップを搭載したベースを使うことも音作りの一環です。例えば、Precision Bassに搭載される柔らかな低音とはっきりした高音を併せ持つスプリットコイル、Stingray Bassに搭載される極太の低音と高いノイズ耐性が特長のハムバッカーなどがあります。また、配線を変えることによりJazz Bassを疑似的にハムバッカー搭載のように使用したり、いくつかのピックアップをミックスしたりして使うこともできます。
弦に関しては、通常のニッケルラウンドワウンドもいいですが、コントラバスライクなフラットワウンド、あるいは低域が強調されるナイロンワウンドなどが落ち着いたサウンドを見せてくれるでしょう。
逆に、長く張り替えないことを見越してのステンレスフラットワウンドやコーティング弦なども魅力的ですが、価格が高いため及第点、といったところです。
弦を交換する際、張力を落としたい(抑えやすくなるが、音も細く繊細になる)場合は細く、上げたい(抑えづらいが、音が太く持続しやすい)時は太くします。ただ、ナットの溝に弦が入らない時に無理やりそのまま使用するとナットが削れたり、割れたりの原因になります。面倒ですが加工は必須です。一応WarwickのJust-A-Nut、AtlansiaのADJUSTABLE NUTなどを使えば削らなくても調整できますが……
ピックアップの高さ調整はかなり音質調整に寄与します。簡単にいじれてすぐに戻せる割に音量や音質の変化が多いため試す価値はあるでしょう。
なお、ペグやブリッジなどのパーツを変えるより、コンデンサの容量や可変抵抗の抵抗値などの電気的な定数を変える方が音質の変化は分かりやすくなります。ただし、弦とパーツは直接奏者と触れ合う部分なので、演奏性に直接関わる部分になります。
カスタムしたくなったら、ネットや本を参考にしつつ何を重視して改造したいのか考えてみましょう。
お勧めの楽器
結局、どんな楽器も改造やエフェクター含めて十分に調整すればどんなジャンルでも演奏できます。
物理的な機能に問題がない限り、自分の好きな楽器を長く使うのが最も良い、ということは覚えておいてください。
その上で、どんな楽器がいいか分からない、という時はここに例示するベースから好きなものを見つけてみてください。
Squier Classic Vibe 50s Precision Bass(4弦)
1ピックアップに1V1Tの非常にシンプルな構造、しかしスプリットコイルの音の太さは健在。
どのように味を付けてもいいし、逆に味付けをほぼせずToneを絞って甘いサウンドを投入してもいい。
上位機種であるStingrayからミッドを調整するノブを抜いたのが特徴で、案外に調整が楽で直感的に音作りができる便利なベース。
以前紹介したときには「Stingrayが吹奏楽に合うわけがない」という意見もあったが、イメージ通りのStingrayだけではない出音がある。
どちらも2ハムにアクティブ回路搭載で「最悪、これとボリュームペダルさえあれば問題のない演奏が可能」というベースの一角。
安価ながら高クオリティなことから愛用者は多く、全ジャンルで採用されている。
GRETSCH Electromatic Junior Jet Bass II(4弦)
ここまでレギュラースケール(34inch)を紹介してきたが、初のショートスケール(30.3inch)ベースが憧れのGRETSCHから。
ショートスケールにより弦は抑えやすくなり、また柔らかい低音が多少出やすい(悪く言えば、輪郭がぼやついて締まらない)独特のサウンドが魅力的。
Jet Bassと同じくショートスケール、そしてフルアコのバイオリンベース。
小型軽量の取り回しの良さが利点と言われることが多いが、サウンド面でもマイルドな音から重低音セットアップまで幅広い音質に調整可能。
他のベースと違う独特な操作系統を持つ点には注意。
お勧めのエフェクター組み合わせ・編成
汎用・ローエンド
ベース→Zoom B1→Boss FV-50L→KORG PB-CS→アンプ
価格:¥19260
パッチケーブル本数:3
電池数:単3×4、006P×1
パワーサプライ不要、誤操作しがちなB1のチューナーの代わりにボリュームペダルのTUNER OUTからチューナーに投入。
電池駆動となるためKORGのPB-CSでも基準ピッチはリセットされない。
ある程度足元操作に慣れている、あるいは逆に演奏中に操作しないならB1X単独でも問題ない。
中価格帯・汎用
ベース→tc electronic Forcefield Compressor→Electro-Harmonix Bass Soul Food→Boss GEB-7→Boss FV-50L→Boss TU-3→アンプ
価格:¥46560
パッチケーブル本数:4
電池数:006P×4
滑らかなForcefieldのコンプレッションで抑えつつ、Bass Soul Foodの軽い歪みで馴染ませるという方向性。味付けの薄いそれぞれをグライコで調整するのが音作りの要。
費用を削りたい場合はチューナーかイコライザーのグレードを下げること。どれも100mAセンターマイナスで駆動可能なので、パワーサプライを用意してもいい。
マルチエフェクター
・Zoom B1 Four/Zoom B1X Four
軽量小型、これ1つでだいたいのエフェクトは賄える上に、初期パッチを適当に選択するだけで整ったサウンドになる。
少し慣れたらより小型なMS-60Bでもいいが、こちらは駆動時間が少々短く、またプリセットがないという問題点がある。
B1Xに付いたエクスプレッションペダルはかなり軽い動きなので、ワウやピッチベンダーを使わないならB1にBossのFV-50Lなどの重めのペダル単品で音量調節というのが便利。
お勧めエフェクト:ZNR→LMT-76→Splitter
最後に・練習時に注意すること
基本的には、練習時は低音隊と同じようなメニューから基礎練習のロングトーンを抜き、リズム通りの演奏を心掛けるためメトロノームに合わせたピッキング練習を行います。 ギター・ベース教本で何度も言われている通り、アンプには繋いだ方が絶対に良いです。そもそもエレキベースは生音が客席に届く楽器ではないですし、アンプに通すことによりまるで全く別の繊細なタッチを持つ楽器のようにサスティンは何倍も伸び、ミュートは難しくなり、聴覚上ピッキングノイズは減ります。 エフェクターを練習中使用するかどうかは、できれば使用した方がいいが、音価と音量に関係ないものなら使わなくても(掛けなくても)良いとだけ言っておきます。コンプレッサーや歪みは音価に関わるものなので使用しましょう。
吹奏楽におけるエレキベースの音作りに関して、楽器本体、奏法、エフェクターとアンプの3方面からの考察を書いてみました。エレキベースも楽器ですので、音楽を演奏しているのに聴こえないというのは非常に残念です。これを機に、音作りについて考えてみるのはいかがでしょうか? それでは、良い吹奏楽ライフを!
参考リンク:サウンドハウス
➡︎ 最強コンプレッサー・マニュアル
➡︎ 最強イコライジング・マニュアル
※価格は2022年3月現在のもの


















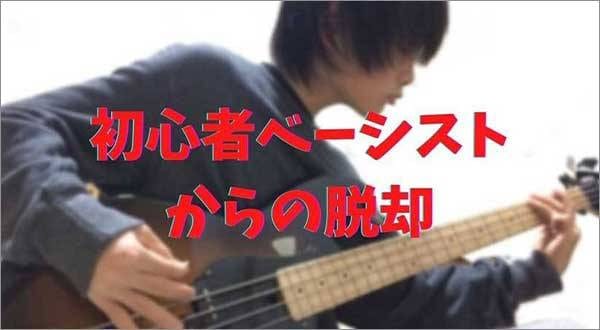


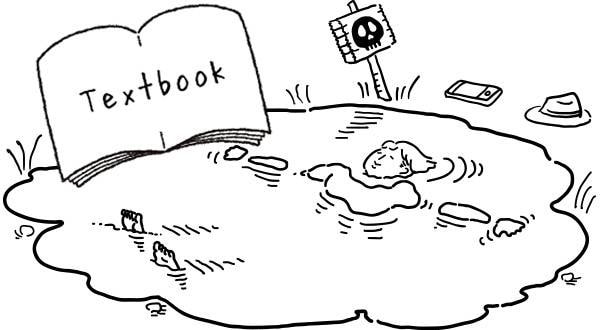


 ベース弦の選び方
ベース弦の選び方
 ベーススタートガイド
ベーススタートガイド
 ベースとベースアンプ(練習編)
ベースとベースアンプ(練習編)
 ベース奏法(指弾き編)
ベース奏法(指弾き編)
 ベース奏法(ピック弾き編)
ベース奏法(ピック弾き編)
 ベース初心者講座
ベース初心者講座

















