前回の予告通り今回はコンデンサーについて。
ただ本気ではない、なぜかと言うとギターやベースに使用する前提での話だから。
これがアンプやエフェクターに使うコンデンサーの話になると一気に本気モードになるのだが話が長くなりすぎるので、またいずれ。
さて、ギターのコンデンサーがリプレスメント用部品として注目され始めたのはいつ頃だろうか?
わたしの記憶では2000年~2003年ごろだと思う。
それまでオレンジドロップやビタミンQなど、名前は何となく知っていても見た事も触った事も無かった人がほとんどだった時代。
GibsonのLPヒストリックコレクションが所狭しと楽器店の店頭に並んでいても、その中に使用されていたのは小さなセラミックコンデンサーだった。
当時細かくビンテージLPを再現したと謳っているにも関わらずハードウエアの部分は現行部品のままだったことは残念。
コンデンサーの種類はかなり多いが今回はギターのトーン用に絞って紹介していく。

セラミックコンデンサー、フィルムコンデンサー、オイルコンデンサー、オイルペーパーコンデンサー、マイカコンデンサー、スチロールコンデンサー、大体これらが良く使用されていると思う。
実際はこの中のフィルムだけでもポリプロピレンやポリエチレン、ポリカーボネイトなど、さらに細かく分けられて覚えるのも大変なぐらいだ。
個人的な趣味と独断と偏見でギター用に使用したいコンデンサーをピンポイントで紹介しよう。
まずはオイルペーパーコンデンサーだ。
SPURAGUE社の古いバンブルビー(正式名称ではないので注意)もオイルペーパーコンデンサーだが、現在入手できるものは中のオイルが枯渇(ドライアップ)してしまって
静電容量も絶縁抵抗も劣化している物が多いので良いのか悪いのか判断できない。
しかし50年代後半のオリジナルLPに使用されていたと聞くと多少高価でも試してみたくなるのが人情ってなもんだがこれがまた入手が難しい。
そこで現在入手出来るオイルペーパーコンデンサーのこれをお勧めする。

ハーメチックシールオイルコンデンサーと呼ばれるものである。
本来ならば楽器用に使用すべき物ではない。
性能、耐久性、いずれも一般的な汎用品とは比べ物にならない。それもそのはず、もともと軍隊や過酷な環境において間違いなくその性能を発揮できるように開発された部品なのだから。
画像のコンデンサーはUSAのASTRONというメーカーのコンデンサーだが40年以上前の代物だ。
静電容量を測定してみると0.043uF表記で、実測0.0423uFであった。その容量誤差は驚愕の2%だ。
通常コンデンサーの容量誤差は5%~10%、ましてや40年前の性能では20%が当たり前だった。
それにしても40年前の製造品で現在の容量誤差がわずか2%と言うのは驚きだ。
これはひとえにハーメチックシールと言う構造に秘密がある。
ハーメチックとは外気を完全に遮断する気密封止構造の事を指す。ただ、大変に手間のかかるやり方なので当然製造上の手間もコストも掛かり、そんじょそこらの部品屋さんの店先にポイッと放置してあるような物ではない(していた店も有ったが今はもう廃業している)。
そのハーメチックゆえに内部のオイルがドライアップする事も無く何十年も性能を維持できる。

抜群の耐久力と精密な容量誤差で大変信頼度が高い。最近はあまり見かけなくなったが
SPRAGUE社のビタミンQ(通称ビタQ)もこのタイプ。
次に最も種類が多いと思われるフィルムコンデンサー。
誘電体に使うフィルムの種類と構造が大変多く、また自己回復作用があるため、様々な場面でお目にかかる機会が多い。
ひと昔前の国産ギターは99%フィルムコンデンサーが付いていた(主にマイラーフィルム)。
見たことが有るかもしれないあの緑色の安っぽいやつだ。
いや、君の考えは間違っていない、あれはホントに安いのだ。
ただ、経年劣化で外側の緑色塗膜がパキパキに割れてしまう物も有り耐久性は良いとは言えない。
それを防ぐためSPRAGUE社のオレンジドロップはフィルムの一番外側に網状のコットンを巻きその上に塗膜を乗せたものまである。(全部ではない)
30年ほど前に秋葉原には「シルキーキャップ」なる高価なコンデンサーが出現した。
シーメンス社の積層フィルムコンデンサー(単価100円以下)の両端にある足を一旦取り除き新たに真横に足を取り付け、全体を絹糸でしっかり巻きその上からエポキシでがっちり固めた代物である。 これがオーディオファンにめちゃくちゃ支持された。
で、私がお勧めしたいフィルムコンデンサーはERO(Roederstein社 現Vishay)のMKT-1813というコンデンサーだ。
主にヨーロッパ方面の楽器に使用されている、ヘフナーのバイオリンベースに使用されている事も20年前に確認した。
現在では比較的入手しやすいコンデンサーなので試してみると良い。

ちなみに画像は同じEROのKT-1800というペーパーフィルムコンデンサー。
次はセラミックコンデンサーだが、どうも昔の安っぽさのイメージが有り好んで使用したことがない。
要は好きじゃないだけ。
巷では70年代のUSA‐Fenderに使用されていたと言う理由でダイレクトロンのコンデンサーが人気らしいが、このコンデンサーが嫌で取り外し違う物に交換していた時代が確かにあったと知っていて欲しい。

※ちなみに「サークルD」とか、どっから誰が言い出したのかは知らないがそんな名称は部品屋には通用しないし完全な造語である。
SPRAGUE社やCornell Dubilier社はコンデンサー本体に正式な名称を入れている。
例)ROYAL TIGERやBLACK CAT、YELLOW JACKETなど。
もう一つ、USA‐Fenderに使用されていたダイレクトロン以前のコンデンサーを知っているかな?
これが意外と知られていない、なぜなら誰も確かめないで憶測や聞いただけの話を知識として振りかざすからだ。
初めて聞く人も多いだろう。答えはPACKTRON社のフィルムコンデンサーだ。

現在ではほぼ入手できない。
やっぱりコンデンサーの話になると終わりが見えてこないので、一旦ここで終了したい。
最後に私の好きなコンデンサーを何個か紹介したい。
音質的な特徴や構造、材質なども書いておくので参考にされたし。

NCC(松尾電機)CMP-T
私の最も好きなコンデンサーでもある。
容量耐圧の割に大きい。その理由は通常のペーパーコンデンサーをセラミックの筒に入れハーメチック封入したため。
昭和の時代その音質と性能で世界を凌駕したSONYのテレコや自衛隊の通信機や機器にガンガン使用されていた。
それだけ耐久力、音質、性能に優れ、正に「モノづくり日本ここに有り!」と世界に誇れるコンデンサーなのだ。
これを通した音は太い。しかも低音で高音が潰される事もなく、それぞれの音に艶と明確な存在感が付加される。
先に紹介したERO KT-1800も似たような印象だが、EROの方は若干低音が固い。
しかし中音域に大変厚みが出る。
これも大変に魅力的なコンデンサーなのだ。

このブログを見て、少しでもこの愛すべき部品たちに興味を持ってもらえると嬉しい。
ギターだけでなく、アンプやエフェクターにもコンデンサーは沢山入っています。それを
自分好みの物に交換とか、考えただけでも興奮してきます。
ではまた。










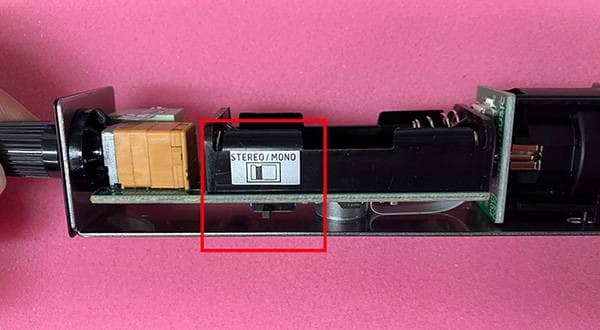






 DIY ギターメンテナンス
DIY ギターメンテナンス
 配線カスタマイズ 第1回
配線カスタマイズ 第1回
 パーツの配線を知ろう
パーツの配線を知ろう
 ピックアップの種類(エレキギター)
ピックアップの種類(エレキギター)
 ネックの調整方法
ネックの調整方法
 ギターの各部名称
ギターの各部名称
















