最近の物価高騰はギターにも波及している。10年前に高いっ!と思っていた50万のフェンダーマスタービルダー故ジョン・イングリッシュのギターが今では200万円近くする時代だ。
しかし、あなたがお持ちのリーズナブルなギターでも、かなり良い音になる方法を伝授しよう。
今回モディファイしたのは、富士弦楽器製造の80年代中期フェンダージャパンST72ー65SCだ。7年前中古で59,000円で購入した。前オーナーが使い込んだ様子で塗装は充分黄ばんでおり、ナチュラルレリックの雰囲気タップリの風格である。ナット、フレットが交換されており、ネックは新品と同じ状態であった。
ボディ材はバスウッド。この材の特質は『クセがないのがクセ。』である。よってパーツによる音の変化が反映されやすい。安価な材だが決してクオリティの低い木材ではない。
VintageのSTARTOCASTERでもバスウッドを使用していた時期がある。
ではいってみよう。
■ ペグ
SCHALLER ( シャーラー ) / M6 mini CH 6L / M6L mini-C
リッチーはこれを1980年前後から愛用していた。ファンならお馴染みの余った弦を丸めておくと 物凄くリッチーらしくなる。やや重いぶん、物理的にサステインが伸びると言われている。弦の巻き方がオリジナルフェンダーと異なるが慣れてしまえばこちらも楽だろう。
弦の先端がペグに収まらないので、短く切るなりしないと危険である。切らないまま長い余った弦でステージに立つギタリストもいるが、中途半端に弦を切っていると、指先はもとよりステージアクションで目に刺さる可能性があり危険だ。Gibson系然りだが。(写真参照)

ヘッド 。シャーラーM6ミニ。よりメカニカルな印象になる。

シャーラーM6ミニ ペグの後ろ側。オリジナルペグと取り付けネジの位置が異なるため埋木してある。
また再結成レインボー前後からシュパーゼルに再度交換したが、これはチューニングの精度をアップ・デートしたと思われる。
■ フレット
これには中古を購入した時点で ジムダンロップ6105にリフレットされていた。最近の定番はジェスカーだろう。以前、ブラックモア本人はギブソン製と公言していたが、彼のインタビューはジョークでかわされる事が多いので詳細は不明と思われる。ジェスカーのナロージャンボ系(細身でクラウン=ビードの高い)フレットが最適だろうと思う。
またフレットが磨耗するのを嫌い、ステンレス・フレットに交換したいプレイヤーもいるが、ステンレスは音色がかなり変わる。ステンレス・フレットに換えるならその音色はリペアマンとよく相談してから決めるのが良いと思う。そしてステンレスと普通のフレットの中間の製品もある。(写真参照、ミディアムジャンボは初めに付いていた日本製フレットより明らかにクラウンが高い)

■ ナット
ブラックモアは90年代あたりからカーボンナットを愛用していたが、この素材は現在あまり使われない物なので好みが分かれるだろう。一般的には牛骨で背の低いナットに付け替えたら良いと思う。
ナットの溝切りはギター職人の腕の見せ所だ。単にスケールで測って溝を切るのではなくて、『職人の勘』がものを言う。1mmでも狂うとプレイアビリティに影響が出るシビアな箇所だ。
特に一弦と六弦。少しのずれがビブラートしにくかったり、最悪フレットから弦が落ちてしまう事があるので、取り付けてもらう時は自分のクセをリペアマンに伝えておいた方が良い。取り付け費用は、リペアショップごとに異なるので要確認だ。
■ ピックガード
1960年代風ミントグリーンピックガード
MONTREUX ( モントルー ) / USA SC 62 MINT GREEN 3PLY ※インチ規格
MONTREUX ( モントルー ) / JPN SC 62 MINT GREEN 3PLY [8097] ※ミリ規格
これはあまり音に関係がないと思うが、かのエリック・ジョンソンはオールドのピックガードを交換して、その音色が気に入らなくて、結局そのギターを手放したという逸話もある。そこまで音の違いがわかるギタリストはまずいないと思う。このミントグリーン・ピックガードを着けると雰囲気ががらっと変化し、風格が増すだろう。
ブラックモアは1982年の来日時、ピックガードをこのミント・グリーン・ピックガードに代えている。白いボディカラーに程よくマッチして味わい深い、より使い込まれた雰囲気がでている。(ギター全体写真参照。ピックガードのカラーはホワイトより若干違う)

モディファイしたストラトの全体像。ストラップもブラックモア使用と同じリユニオン・ブルース社製(色・長さは異なるが、デザインと質感は同じ) アームは1984年仕様(次回詳しく述べる予定)
■ セレクタースイッチ
車で言えばギアチェンジに例えられるだろうか。お世辞にも5、6万円台のストラトに耐久性のあるパーツがついているわけがない。一曲に何度も(Child in Time の様に長い曲なら数十回も!)スイッチを動かすブラックモアのように使いたいのなら、地味な交換だがしっかりとした品質のパーツを勧める。米国製で耐久性があるのはCRLが定番だろう。ブラックモアは三点式で事足りるが五点式にしても音質に変化はないし、後々便利なので、どちらでも良いと思う。
■ ボリューム ポット・トーンポット
CTS ( シーティーエス ) / Custom A250 カスタムコントロールポット
ブラックモアはボリュームをこまめに調節する。またストラトのシングルコイルピックアップはノイズを出しやすいので弾かないときはできるだけ音を絞りたい。1,000円以下で手に入るので、なるべく安価な物は避けて良いものを選びたい。CTS製が定番だ。
国産のオリジナルにこだわる気持ちもわからない訳ではないが、耐久性が全く違う。故障してから修理すると費用がかかるので、最初から交換を勧める。
※ ナットを1枚噛まさないとノブとピックガードの底面がぴったりにならないので注意。
■ ストラップ ・ピン
ジム・ダンロップ真鍮カラー
JIM DUNLOP ( ジムダンロップ ) / SLS1402BR Straplok Flush Mount Brass
本来ならクロームがベスト。
ブラックモアはステージアクションが激しいので、ストラップをロック式にしないとたやすく外れる。シャーラー製とジム・ダンロップ製が二大ブランドで、ブラックモアは後者を使っている。長年使用してきたメインギターにはギター本体側が埋まったタイプを使用していた。
■ スキャロップ指板
帆立て貝の殻の形のように指板を削る仕様だ。ルックスにも影響があり、昨今はこの指板を施すギタリストも珍しくないが、有名にしたのはブラックモアだ。
利点はフレットと弦の接点のみで弾けるため、指使いに摩擦が減るので早弾きに適する。また、深いビブラートが掛けやすい。(写真参照)

スキャロップ指板。低音弦側は浅く、高音弦側は深く削られているのがわかる。
欠点として強く押弦すると音程がシャープする。指板を削るため、音質の変化もあるだろう。そして万が一、売却する時に指板が削られていたら、査定額に大きなマイナスとなるはずだ。特に貴重なオールドギターに施すのはプロフェッショナルではない限りおすすめしない。
■ ピック・アップ
SEYMOUR DUNCAN ( セイモアダンカン ) / SSL-4 Quarter-Pound Flat
ギタリストなら一番気にするパーツだ。
ブラックモアのサウンドはアルバム『DOWN TO EARTH』の頃から大きく変化した。一言で言えばトレブリーになった。
当初シェクター製『F-500』を使用し、後にセイモアダンカン SSL-4に換えた可能性もある。シグネイチャーモデルも、SSL-4が装着されている。
私はSSL-7を勧める。
SEYMOUR DUNCAN ( セイモアダンカン ) / SSL-7 Quarter-Pound Starggered
全体にパワーを求めるなら『4』が適していると思われる。『7』はより輪郭があり、ピッキング・ニュアンスを出しやすいストラトサウンドだ。高域にフォーカスするのでサウンドに好みが分かれる可能性があるが、試してみる価値はあるだろう。ルックスはポールピースがスタガードになる以外、正面からは『4』と変わらない。LIVEの際、オーディエンスにはまず分からないと思うので御自身の判断に委ねる。(写真参照)

ピック・アップ セイモアダンカンSSL-7。センターはピックアップのパワーを変化させる米国製パーツ『ADDER』(現在入手不可能)を両面テープで着け固定している。
--前編おわり--
⇒ サウンドハウスの商品でRITCHIE BLACKMORE STARTOCASTER モディファイ をやってみた 後編
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら







![MONTREUX ( モントルー ) / JPN SC 62 MINT GREEN 3PLY [8097]](https://www.soundhouse.co.jp/images/shop/prod_img/m/montreux_8097.jpg)








![MONTREUX / JPN SC 62 MINT GREEN 3PLY [8097]](/images/shop/prod_img/m/montreux_8097.jpg)





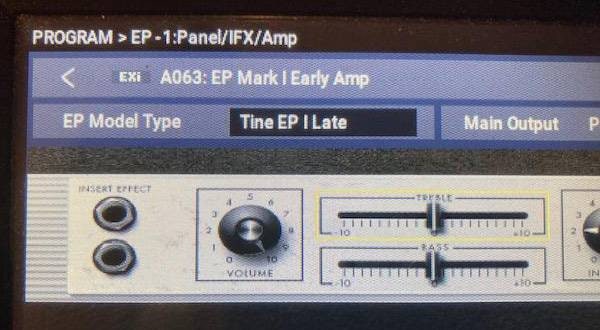










 DIY ギターメンテナンス
DIY ギターメンテナンス
 ギターの種類
ギターの種類
 ピックアップの種類(アコースティックギター)
ピックアップの種類(アコースティックギター)
 ピックアップの種類(エレキギター)
ピックアップの種類(エレキギター)
 ギターのお手入れ
ギターのお手入れ
 ギターの各部名称
ギターの各部名称















