昨今のマルチエフェクター(以下マルチ)は、価格帯の幅も広く、コンパクトで多機能なモデルが次々と登場しています。BOSS、LINE6、ZOOMなど各社から手軽に扱えるモデルが出ており、初めてのエフェクターとしてマルチを選ぶ初心者も多いのではないでしょうか。
ZOOM ( ズーム ) / G2 FOUR ギター用マルチエフェクター
Line 6 ( ライン6 ) / HX Stomp マルチエフェクター
ところで、家で一人で弾いているときは気持ちのいい音なのに、スタジオでバンドメンバーと一緒に音を出すと「自分の音が聞こえない」「なんだかこもってしまう」と感じた経験はありませんか?
マルチを使ったことのある人なら、一度はバンドアンサンブル上での“音抜けの悪さ”に悩んだことがあると思います。
今回は、そんな悩みを抱える初心者の方向けに、マルチエフェクターで音抜けを良くするための実践的なポイントをいくつかご紹介していきます。

1. アンプシミュレーターを使う場合は「リターン挿し」がおすすめ
マルチ内蔵のアンプシミュレーター(アンシミュ)を使う場合は、リターン挿しがおすすめです。
リターン挿しとは、アンプの「センドリターン端子」のリターン側にマルチを接続する方法です。これにより、アンプ内蔵のプリアンプ(音色を作る部分)をバイパスし、マルチ内で作ったサウンドをそのままパワーアンプに送ることができます。
この方法を使うと、マルチで設計した音作りが崩れにくく、サウンドの再現性が高まります。アンプモデリングを搭載したマルチでは、リターン挿しが非常に効果的です。

スタジオのアンプの背面を見るとこのようなセンドリターン端子が搭載されているものが多いです。
また、キャビネットシミュレーター(スピーカーシミュレーター)をOFFにすると、アンプの実際のスピーカーで鳴らす際に音がこもりにくくなります。キャビシミュはライン録音やヘッドホン練習時には便利ですが、スタジオのアンプで鳴らすときには音抜けを悪くする場合があります。
2. 歪ませすぎない
自宅での練習では、深く歪ませたサウンドが気持ちよく感じることがあります。しかし、バンドでの音作りでは歪ませすぎが音抜けの悪さの原因になることが多いです。
歪みを深くするとコンプレッション効果が強まり、音の立ち上がりが潰れてしまいます。また、レンジが狭くなるので単体で聞くと派手な音でもアンサンブル上だと他の楽器に埋もれやすい音になってしまいます。
さらにスタジオでは音量が上がるため、自宅で作った設定のままだと「想定以上に歪んでいる」ケースがほとんど。特にハイゲイン系アンプモデリングを使っている場合は、GainやDriveを下げてみてください。
3. ディレイ/リバーブをかけすぎない
ディレイやリバーブはサウンドに広がりを与えてくれる非常に魅力的なエフェクトですが、多用しすぎると音の輪郭がぼやけて抜けが悪くなります。
特にマルチのプリセットは、ヘッドホンや小型アンプで「気持ちいい音」に聞こえるよう設計されているため、空間系がやや強めに設定されていることが多いです。スタジオやライブで使う際は、控えめな設定にすることを意識しましょう。
また、リバーブを「ルーム」や「プレート」に変えるなど、残響時間が短いタイプにすることで音の輪郭を保ちながら空間感を演出できます。ライブやスタジオでは、空間そのものがリバーブを生み出すため、過剰なエフェクトは不要です。
4. 不要な帯域をEQで削る
家庭用アンプやヘッドホンなど小口径スピーカーで音作りした場合、スタジオの大型キャビネットで鳴らすと、低域や中域が過剰に出て他の楽器とぶつかることがあります。
代表的な対策として、以下のような帯域カットを試してみてください。
- ベースと干渉している場合 → 250Hz以下をカット
- ボーカルとぶつかる場合 → 1kHz付近を抑える
- 耳に痛い音が出ている場合 → 2〜3kHzを控えめに
ただEQを大胆にカットすると音が細くなり、かえって埋もれることがあります。調整後は必ずバンド全体で鳴らしてバランスを確認しましょう。
5. 入出力設定を確認する
意外と見落としがちなのが、マルチの入出力設定です。モデルによっては接続先に応じた最適化機能があり、これを設定するだけで音抜けが劇的に改善することもあります。
たとえば、BOSSの人気モデル「GT-1」では、Output Selectという項目で「LINE/PHONES」「JC-120」「STACK RETURN」など接続先を選ぶことができます。これを正しく設定することで、内部EQやレベルバランスが自動的に最適化されます。
他メーカーでも似た機能を搭載している場合があるので、マニュアルを一度確認してみましょう。
実機を触って“本物の音”を知ろう
マルチエフェクターには、有名なエフェクターやアンプのサウンドを再現したモデリングが数多く搭載されています。もしその中で気に入ったモデルがあれば、実際の機材を触ってみることを強くおすすめします。
例えば、「TS系オーバードライブ」や「Marshall Plexi」など、定番モデルを実機で試すと、どの帯域が特徴的なのか、実際の反応感やエフェクトのかかり方を体感することで、マルチでのエディット精度が格段に上がります。
レンタルスタジオによってはアンプやエフェクターの貸し出しも行っているので、休日に比較実験してみるのも良い勉強になります。
まとめ
マルチエフェクターは万能ではありますが、環境によって音の聞こえ方は大きく変わります。
「家では最高なのに、スタジオだと抜けない」という悩みは、多くの場合設定や接続方法の問題で解決できます。
ぜひ今回のポイントを参考に、スタジオでもしっかり抜けるサウンドを作ってみてください。
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら




















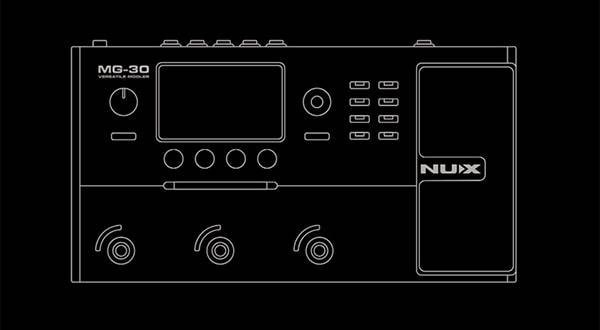


 はじめてのエフェクターは GT-1 にしよう
はじめてのエフェクターは GT-1 にしよう
 zoom ブランドサイト
zoom ブランドサイト
 【初心者向け】エフェクター講座
【初心者向け】エフェクター講座
 ベース用エフェクターの種類
ベース用エフェクターの種類
 エフェクターのつなぎ方
エフェクターのつなぎ方
 エフェクターの種類
エフェクターの種類
















