大学生の頃、母校の学園祭で出会ったバンドのお話をします。
学園祭は学生にとって自分のバンドの発表会である一方、キャンパス内に設置された大きな野外ステージはプロやそれに近いミュージシャンも数多く出演します。プロのミュージシャンを目の当たりにすることで自身のバンドの不甲斐なさや良い面などを確認できる貴重なイベントでもありました。
私が所属していた軽音楽部は学部の中心にある学生食堂を借り切り、各バンドのプログラムを組みライブを繰り広げていましたが、いつかはあの野外ステージで演奏したいと思ったものです。
そんな大学1年生の時に、当時クロスオーバーと称されていたジャズ・フュージョンバンドに心を奪われました。
スペース・サーカスという超ハイテクニックバンド
私がそのバンドのライブを目にしたのは1978年の学園祭の中庭ステージでした。ポップアートの旗手であったピーター・マックスの大きなグラフィックが描かれた中庭ステージにスペース・サーカスは登場しました。
音が出た瞬間から驚愕しました。なんといってもベースが凄かったのです。ベーシストのチョッパーベースがスペース・サーカスの奏でる音楽の骨格を作っていることは一聴して理解できました。
当時、私達はチョッパーやスラップベースのことを「パチベ」と言っていました。親指でベース弦を叩いたり、はじいたりするとベース音がパチパチと聞こえるので「パチベ」と誰かが表現したのだと思います。チョッパーという言葉も当時聞いたことがなかったですし、スラップという表現も随分後になって出てきた言葉です。それだけチョッパーやスラップベースの奏法というのも普及していませんでしたし、実際の演奏を聴いたことがないというのが当時の実情でした。認識していたといえばチック・コリアのバンド、「リターン・トゥ・フォーエバー」のメンバーであるスタンリー・クラークがやっている奏法くらい。周囲も見よう見まねでコピーらしきことはしていましたが、見たことのないチョッパー奏法へのアプローチは暗中模索といったところでした。軽音楽部でもパチベにトライしているのはたった1人の先輩だけでした。
スペース・サーカスのベーシスト岡野ハジメさんは、グラハム・セントラル・ステイションのベーシスト、ラリー・グラハムの演奏を耳コピしたといいます。インターネットなんて無い時代のお話です。
岡野ハジメさんの超強力なチョッパーベースを生で聴いた私は目が白黒してしまいました。状況把握ができず目の前で何が起きているのか、バンド名がスペース・サーカスなだけに曲芸?軽業師?を見ているような気持ちでした。
スペース・サーカスの音楽は岡野ハジメさんのチョッパーベースを骨格にしたジャズ・フュージョンバンド(当時はフュージョンという文言もない時代)で、細かなキメやユニゾンパートなどの仕掛けが多くあり、高度な演奏テクニックに裏打ちされていました。当時チョッパーという新しい音楽的な演奏手法を全面に出したバンドはスペース・サーカスくらいしか存在していなかったのです。
渋谷のライブハウス「屋根裏」でのこぼれ話
当時、渋谷や下北沢は音楽が盛んで多くのライブハウスが点在していました。渋谷の「ヘッドパワー」や「屋根裏」、下北沢の「ロフト」や「レディジェーン」などです。
私はスペース・サーカスのファンになり、渋谷のライブハウス「屋根裏」に仲間とよく聴きにいきました。キャバレーの2階にある「屋根裏」は、狭く熱気に溢れていました。大きなステージよりもライブハウスの方がミュージシャンの姿が間近で見ることができ、演奏やアンプのチューニングまでも見ることができます。音楽好きなアマチュアは、プロがどんなチューニングをしているのかにまで興味があるのです。
ちなみにギタリストの佐野行直さんが私と同じBOSSのアナログ・ディレイを使っていたことに気付き、そのチューニングを覚えて帰りました。現在のエフェクターの2倍以上の大きさの機器です。とっても重宝したチューニングだったことを記憶しています。
面白い話があります。P‐MODELのライブに「屋根裏」に行った時、キーボーディストがコルグのシンセサイザー800DVから、プラスティックでコキコキとした今でいうデジタルライクな面白い音を出していました。チューニングを見ようとした時、シンセサイザーの操作パネル全面には黒い紙が貼られ見ることができませんでした。操作をするパネル上のスイッチ1カ所だけには2㎝四方の小さな穴が空けられていたのを記憶しています(笑)。パネルのチューニングさえ覚えれば音を盗める時代でした。
とはいえ、ミュージシャンの出す音は演奏技術が伴わなければそのプロの音にはならないわけですし、いくらプロの真似をしても大した意味がないということを当時の私は分かっていませんでした。プロは音だけではなく数多の要素を習得した上でのプロフェッショナルなのですから…。
翌年の学園祭に呼んだビジーフォーの話。学園祭実行委員だった友人ギタリストがライブ中にステージ裏からモト冬樹さんのエフェクターのチューニングを見ようとした際、モト冬樹さんがそれに気付いてしまい演奏中にもかかわらず、わざと見えない位置に足でエフェクターを移動させ見ることができなかったと友人が嘆いていました。皆さんそれだけ自分の音を大切にしていたのですね。
■ 推薦アルバム:スペース・サーカス『ファンキー・キャラバン』(1978年)
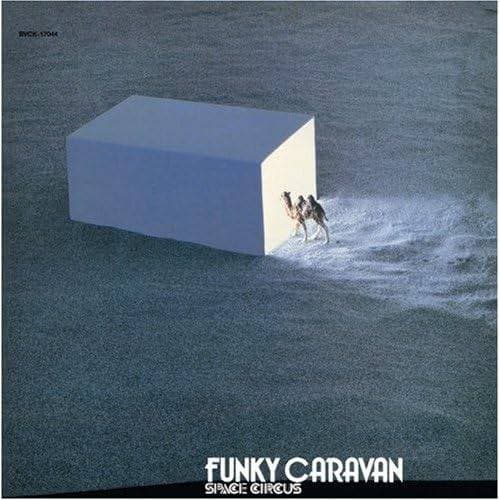
スペース・サーカスの傑作ファーストアルバム。1970年代後半に人気を博した日本のクロスオーバーバンド。テクニカルでファンキーな先進的サウンドは以前の国内バンドでは聴くことができなかった。岡野ハジメのハイテクニックチョッパーベースを中心にメンバーの高い演奏技術が売り物だった。楽曲制作能力も高く、アルバムとしても聴きごたえは十分。岡野さんのインタビューなどによればアルバムのほとんどがファーストテイクかセカンドテイクだったという。恐るべき演奏力を20歳そこそこのメンバーが持っていたのは驚愕すべき事実だ。
推薦曲:「アリババ」
岡野ハジメのチョッパーベースがウネリまくるスペース・サーカスの代表曲。ベース、ギター、ドラム、キーボード4人によるキメキメのアンサンブルが秀逸。楽曲各所に各プレイヤーの聴かせどころがある。後半のアコースティック・ピアノソロが美しい。
ライブハウス「屋根裏」のライブではキーボーディストの山際築さんはフェンダ・ローズステージピアノの上にコルグのモノフォニックシンセサイザー、ミニコルグ700Sを乗せテクニカルに演奏していた。
今回取り上げたミュージシャン、アルバム、推薦曲
- アーティスト:岡野ハジメ、佐野行直、山際築など
- アルバム:『ファンキー・キャラバン』
- 曲名:「アリババ」
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら











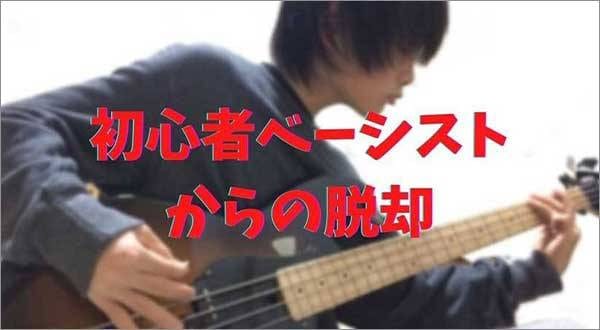

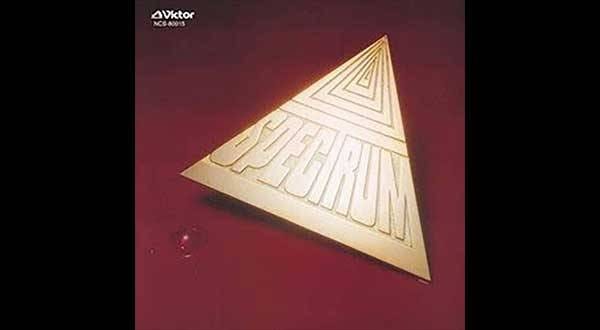
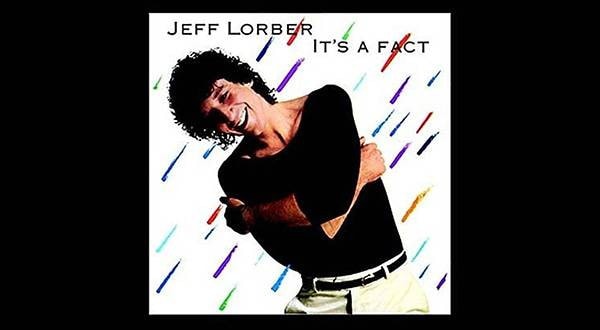

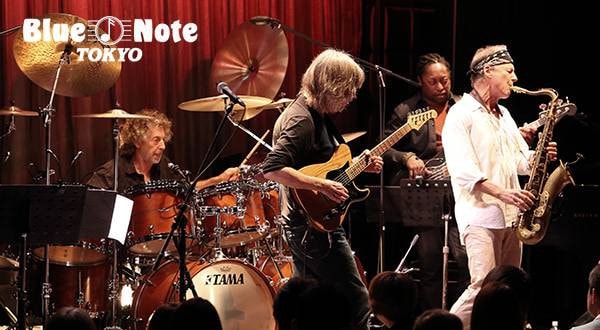
 ベーススタートガイド
ベーススタートガイド
 ベース用エフェクターの種類
ベース用エフェクターの種類
 ベース奏法(指弾き編)
ベース奏法(指弾き編)
 ベースの選び方
ベースの選び方
 ベースを始めるのに必要なものは?
ベースを始めるのに必要なものは?
 ベース初心者講座
ベース初心者講座















