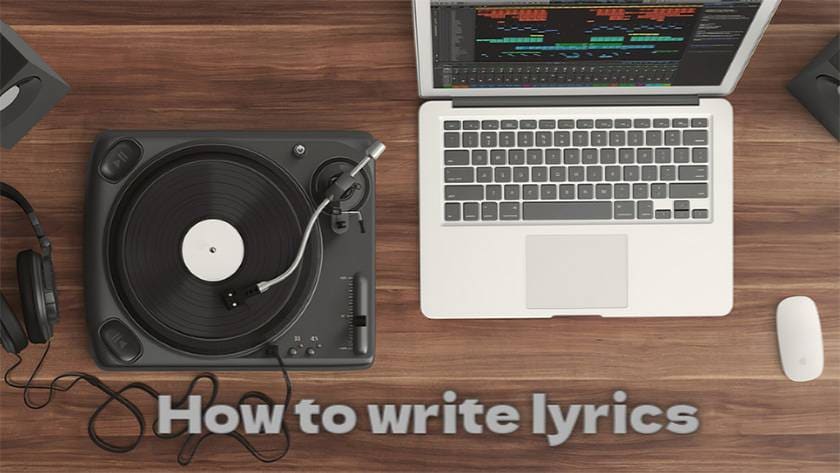
はじめに
こんにちは。
サウンドハウスを利用している方の中には、自身のオリジナル曲や他アーティストへの提供曲を制作するために、作詞をしている方もいると思います。そんなみなさん、どうやって歌詞のアイデアを出していますか?
今回は、筆者がよく使っている作詞法を4つ紹介します。使えそうなものを選んだり、ご自身のスタイルと組み合わせて活用してみてください。
項目ごとに、筆者がその方法で作詞した楽曲を掲載しますので、参考にしてくださいね。
作詞法4選
● セルフタイアップ
筆者イチオシの方法がこれです。コマーシャルやアニメ、映画、あるいはイベントなど、何らかのコンテンツに合わせて楽曲を制作することを、タイアップと言いますよね。セルフタイアップは、「依頼されてはいないけれど勝手にタイアップ曲を作ってしまおう」という方法です。
セルフタイアップは大きく2つに分けられます。1つは、既存の作品に提供するつもりで作詞する方法。世界観がすでに固まっているので、歌詞のイメージが湧きやすいという利点があります。
ある意味で二次創作的な手法なので、オタクの在り方としても面白いと思います。
もう1つは、タイアップ先のコンテンツまで自分で作ってしまうというやり方。もちろん最後まで作り上げる必要はなく、ある程度の設定を練り上げられたら十分といえます。
この方法のメリットは、歌詞の抽象度を高められる点にあります。作詞をしていると、言いたいことを詰め込みすぎて、説明文的な歌詞になってしまうことってありませんか?歌詞だけですべて伝えようとすると、どうしても情報過多になりがちです。
しかし、タイアップ曲はそうではありません。例えば、アニメのオープニング曲は、そのアニメのあらすじを紹介するものではありませんよね。世界観を表現したり、あるキャラクターの心情にフォーカスしたり、あるいはキャラクターの魅力をアピールしたり……。このようにタイアップの形式にすることで、歌詞での「説明しすぎ」を防ぐことができるのです。
■ oct -『ダブルピース』
この曲は、架空の「ジャンプの王道、バトル・冒険アニメ」のテーマソングとして作ってみたものです。アニメ主人公の相棒となるキャラクターの目線で書かれた歌詞になっています。
主人公はこんな性格で、こんなに強くて、最後にはこんな敵と戦って……というような設定は決めているのですが、そこまで詳しくは歌詞にしていません。「あらすじ」を歌詞にしても仕方がないからです。
それでも、途中で鳴っている金属音や、「君だけが世界の頭から爪先まで駆け抜けていけるから」という歌詞から、戦闘シーンっぽい雰囲気や、友情、主人公の真っ直ぐさは、十分に感じ取れると思います。
絶対に表現したい部分と、受け取り手に任せたい部分のバランスを取れるのが、セルフタイアップの利点です。
● 体験談から
文字通り、自分や友人の体験をもとに、歌詞を書き上げる方法です。
この方法で出来上がる歌詞は、良く言えば普遍的に、悪く言えばありきたりになる傾向があります。ドラマティックな体験をいくつも持っている人はそう多くないでしょうから、無理もありません。恋愛、青春、卒業など、多くの人が経験する出来事についての楽曲って、沢山ありますよね。
この「ありきたり問題」の解決策としておすすめなのは、具体的な描写を組み込むことです。「普遍的なテーマ」に対して「個別的な内容」をぶつけることで、バランスを取っています。出来事、時間や地名、場合によっては人名を入れても効果的かもしれません(個人情報の扱いには気をつけて!)。
■ oct -『days』
正直なところ、この曲ではあまり具体的なワードは出てきていませんが……。この曲は、次に紹介する方法との合わせ技で制作した曲でもあるのです。
● キラーフレーズから
これは、筆者が一番良く使う方法かもしれません。印象的なフレーズが思い浮かんだら、そこから膨らませるようにして前後を埋めていくやり方です。
楽曲制作のプロセスは、大きくは詞先・曲先に分けられます。歌詞かメロディのどちらを先に作るかという分類ですね。ただし、これは厳密な区分ではなく、制作途中に順番が入れ替わることは往々にしてあります。
筆者は最初に浮かんだワンフレーズ(歌詞とメロディ合わせて)を中心として構築することが多いので、「キラーフレーズから作る」という方法を良く用います。
コツとしては、普段から多くの優れた表現と出会うことが挙げられます。映画や小説、キャッチコピー、さらには哲学など、何かビビッとくる言葉を見つけてストックしておくと、いざというときに役立ちます。
■ oct -『La:Birds』
この曲は、はじめに思いついた「そうね、吝かでもないわ」というフレーズから膨らませて作りました。
吝(やぶさ)かではない、とは「喜んで」という意味ですが、さて、このセリフを口にするのはどんな人物で、どんなシチュエーションでしょうか?ここから頭の中で物語が広がります。
例えば、あるパーティーで偶然に出逢った女性。大人びていて、周りの人とは違って見えます。彼女に振り向いてほしい主人公は、なんとか口説き落とそうと苦心します。はじめは自信がなく、オドオドとしていましたが、最後には気持ちをストレートにさらけ出して……?
あとはこの物語を歌詞に落とし込むだけです。
ちなみに、少し似た方法で、「タイトルから作る」というのもあります。タイトルに合わせてゼロから作詞するときにはもちろん、方向性が定まってきたところで、世界観を確立するために活用するのも有効です。
筆者はこの方法も使っています。タイトルにしたい言葉のリストを作っておくと便利ですよ。
● 韻を踏む
作詞のテクニックの1つとして、押韻、すなわち韻を踏むというものがあります。これは歌詞にリズム感を与える上で非常に重要な技法です。ここでは、「押韻」を中核において作詞する方法について紹介します。
韻を踏むことが重視される歌詞の代表はラップでしょう。しかし、ラップではないゆったりとした曲調でも、押韻は効果的に作用します。
■ oct -『にわか雪』
筆者が制作したこの曲では、サビの頭で何度も韻を踏んでいます。例えば「きらり、光り、視界に」「淡い、光、みたいに、抱いた」の部分では、何度も「アイ」または「イアイ」の母音で韻が踏まれています。
この方法では作詞がスムーズに進みました。なぜならば、「韻を踏むこと」を前提条件にすることで、使用する言葉を絞り込むことができるから。選択肢が多いと、人は悩みます。適度に制約を設けることで、限られた候補の中から最も良いものを選び抜く意識が高まるのです。
インターネットで押韻ツールを調べてみると、いくつか便利なものがヒットします。言葉を入力すると、韻を踏めるワードが表示されるというものです。押韻ありきで歌詞を書いてみたいときは、活用してみると良いでしょう。
おわりに
ここまで筆者なりの作詞法を紹介してきましたが、利用できそうなものは見つかりましたか?みなさんの楽曲制作の一助となれば幸いです。
今回もありがとうございました。
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら











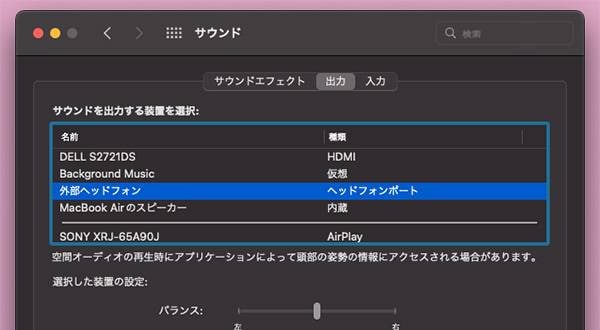

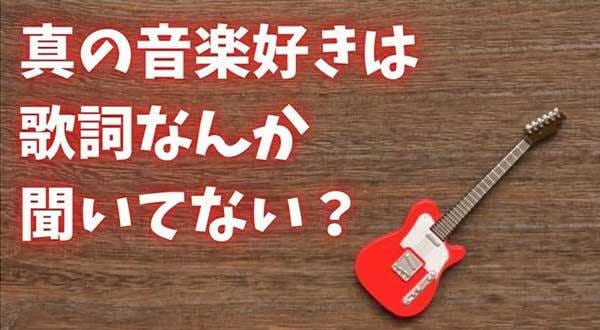
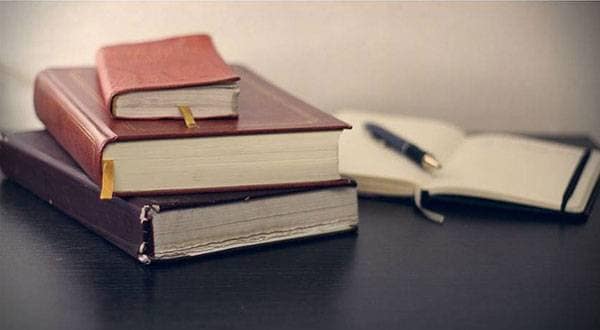


 推し機材SPECIAL!! VOCALOID
推し機材SPECIAL!! VOCALOID
 DTMセール情報まとめ
DTMセール情報まとめ
 ミュージックビデオ撮影テクニック!
ミュージックビデオ撮影テクニック!
 USB接続MIDIインターフェイス
USB接続MIDIインターフェイス
 DTMに必要な機材
DTMに必要な機材
 DTM・DAW購入ガイド
DTM・DAW購入ガイド
















