■ ノーチラス、エレピシミュレート音源EP-1検証の前に
今回はコルグのワークステーション・シンセサイザー、ノーチラスのエレクトリックピアノシミュレート音源を取り上げる予定でした。
しかしその前にエレクトリックピアノの変遷やローズピアノの周辺ネタを書き、それを理解した後にこのシミュレート音源の話を書いた方がエレクトリックピアノの音についての想いが深まるのではないかと考え、急遽クロニクルというよりも私自身のフィルターを通したエレクトリックピアノの周辺材料を書くことにします。
ノーチラスに搭載されているエレクトリックピアノのシミュレート音源はコルグが開発したEP-1 MDS ElectricPianoです。
MDSとはマルチ・ディメンショナル・シンセシスの略でエレピの音をピッチ部分とノイズ成分に分けてそれぞれの成分をコントロールすることでこれまでのサンプリング方式では得ることのできないエレピの自然なサウンドを実現できるのだそうです。
実際にそのプリセット音を聴いた時にエレクトリックピアノの音もここまで来たのかという感想を持ちました。
ここまで来たといっても年齢が若い方からは「どこまで来たのか?」と言われてしまいます。
ますは私が最初に弾いた、エレクトリックピアノの黎明期とも言える1977年辺りまでタイムスリップし、当時の状況を振り返りたいと思います。
KORG ( コルグ ) / ノーチラス NAUTILUS-61
■ 紆余曲折あったエレクトリック・ピアノの歴史
私が学生だった70年代後半にはコロンビアのエレピアンやヤマハのCP-30(電子式)、CP-70、機種名は忘れましたがローランドのエレピを弾いていました。
しかし、CP-70を除いてはエレピらしい音がした楽器は殆どありません。極端な表現をするなら「エレクトリックピアノの音ではない」「エレピとは似て非なるもの」そんなレベルでした。プロになった私の友人は、コロンビアのエレピのことを「ボロンビア」などと揶揄していました。
当時のエレクトリックピアノは、ローズピアノの様にトーンジェネレーターを打弦してトーンバーを響かせる機械的タイプの構造を模したコロンビアのエレピアンのようなタイプと、電気的な発振器や半導体メモリーを使い発音するタイプに分かれていました。
前者はまだましだったと思いますが、後者はどうしようもないと言ってもいい代物でした。しかし当時はそんな時代。「電気ピアノなんてそんなものだ」くらいに我々は考えていました。
DX7がリリースされた1983年以降、ローズピアノの代替機としてDXエレピが世界を席巻します。これによりローズピアノの求心力は低下し、DXエレピにローズピアノが駆逐されかけますが、ローズピアノはそんな状況の中でも消滅することはありませんでした。
エレクトリックピアノの音質向上に寄与したのは、その233でも書いたフェアライトに代表されるサンプリング技術です。アコースティックピアノやローズピアノ等をサンプリングした音源を搭載した機種が各社からリリースされました。
サンプリング音は実機をサンプリング(コピー)するのでそっくりに決まっています。一方でサンプリング・レートの問題もありキータッチに対応しての微妙な表現力を持つ実際のローズピアノとは似て非なるものという評価も相次ぎました。
ナチュラルな実機の音に近付くにはもう少しテクノロジー向上に伴う時間が必要になります。
私もローランドのRD-600というエレクトリックピアノを購入しました。しかし音が良かったのはやはり本物のローズピアノでした。
■ 私が購入したローズピアノ
次はローズピアノの実機の話です。
ノーチラスに搭載されているローズピアノの音源は4種類あります。ローズピアノはそれぞれの時代で音やトーンバーを覆う蓋の構造、鍵盤の仕様などが異なります。
MarkⅠはトーンバーを覆う黒い蓋(カバー)が蒲鉾状でアール型になっています。そのためシンセサイザーなので鍵盤を乗せるとグラグラしてしまい、不安定で弾きにくい状況になります。鍵盤は木製鍵盤でタッチはそれなりの重さがあり、ローズの中では弾きやすい方です。
MarkⅡは不安定な蒲鉾型の蓋(カバー)が改良され、カバーの上部の両サイドを平たくして凸凹を作り、シンセサイザーなどを置きやすくしました。MarkⅡにも木製の鍵盤もありましたが、私の弾いた鍵盤はコストカットのためかプラスチック製になり、タッチも軽く弾きにくかったです。
私はローズピアノの購入の際に選択肢が3つありました。
88Key MarkⅠのスーツケースタイプか、カバーの上部の両サイドを平たくしたMarkⅡの73Keyステージタイプと73Keyスーツケースタイプのいずれかでした。
ローズピアノの特徴は中低音部でキーを強めに叩くと綺麗に音が歪むことです。私が弾いたMarkⅡタイプの2台は中低音が綺麗に歪まず、音自体に奥行き感が希薄でチータッチも良くなかったと記憶しています。
私は旧いMarkⅠの88Keyスーツケースタイプを選択しました。綺麗な歪が印象的でキータッチも良く、とてもいい音が出ました。
今も私が求めるローズピアノの音は中低音部で綺麗に歪むローズの音です。
エレクトリックピアノには様々な評価や好みがあると思いますが、結局エレピで一番普遍性が高いのはローズピアノであることは歴史が証明しています。
ローズピアノは一時的にはDXローズ音にその席を渡しかけましたが、時代は一回りをして今もローズの音は支持され続けています。
ローズピアノにも欠点はあります。
ローズピアノは私が運んだLM系楽器の中では、ハモンド、レスリースピーカーに次いで重い楽器でした。バンドをやっている私ですが、ローズピアノは重すぎて1人では運ぶことができません。トーンジェネレーターが折れることもあります。取り換えや調整も必要です。88Key分のトーンジェネレーターを保存するのも現実的ではありません。残念でしたが数年所有し、売却してしまいました。
実際に蓋を開けてみるとローズにはギッシリとトーンバーやトーンジェネレーターといった部品が詰めこまれていました。ローズの重さも音の一部だったのでしょう。機械的装置の誤魔化しのなさが、いい音を作ったのだと思います。
あの時代から40年以上が経過し、エレクトリックピアノの現状には隔世の感があります。機械的で、実際に空気を揺らす機構から発音される「音」の説得力は、集積回路を通った音よりも秀でている…。そしてそれは今も変わることはありません。
果たしてノーチラスの様なシンセサイザー・イン・エレピのビンテージ音が、どこまでその本質に抗うことができるのか…次回はいよいよノーチラス・エレピの検証です。
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら














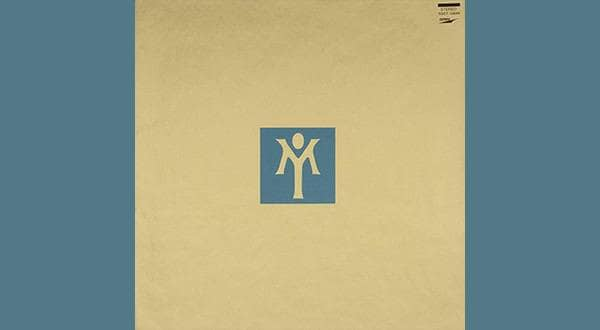




 エレクトリックピアノ 入門ガイド
エレクトリックピアノ 入門ガイド
 シンセサイザー 入門ガイド
シンセサイザー 入門ガイド
 VISCOUNT特集ページ
VISCOUNT特集ページ
 PLAYTECH 鍵盤特集
PLAYTECH 鍵盤特集
 おすすめの電子ピアノ
おすすめの電子ピアノ
 キーボードスタートガイド
キーボードスタートガイド















