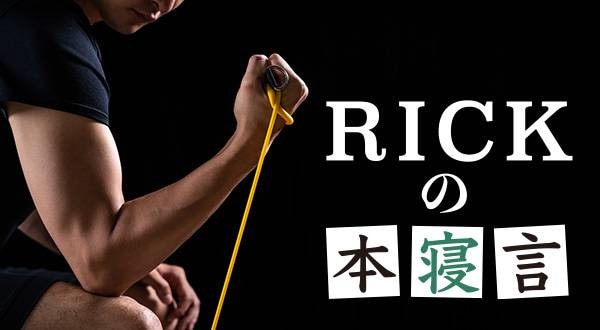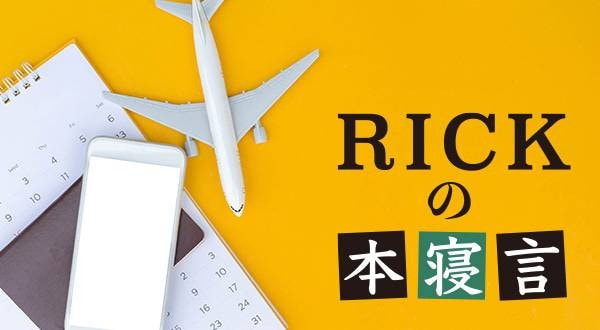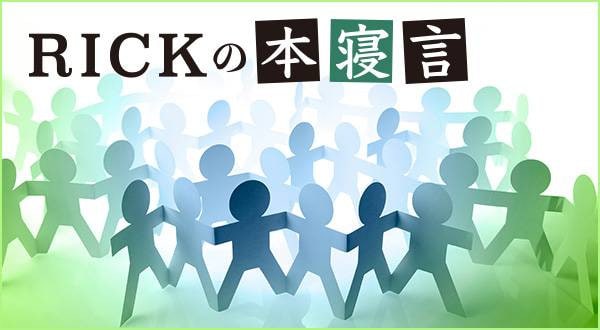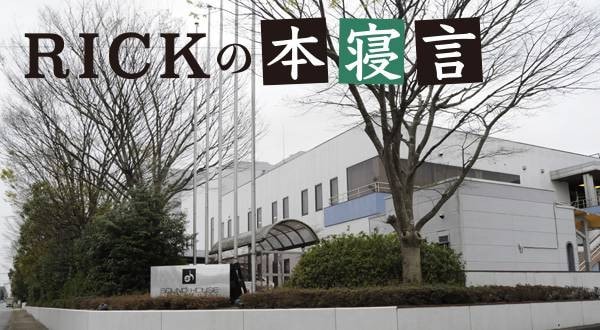小さな古びたプレハブ小屋から始まったサウンドハウスという会社は、いつの間にか巨大な会社となった。創業者として今日、会長職を務めているが、その責務は重く自分にのしかかってくる。否が応でも会社を存続させることが自分の使命だ。何故ならば200名を超える社員と、その家族、親族、合わせて1,000人の生活が、この会社から生み出される収益源にかかっているからだ。よって自分がいてもいなくても、会社がこなしていくべき業務が日々完結し、かつ、成長路線を走り続けることができる道筋が整えられるまでは、目を見張っていなければならない。これもつらい仕事だ。
その大変な仕事のバックボーンとなるのが、実は情報収集だ。「井の中の蛙大海を知らず」、ということわざがある。世の中で起きていることを何も知らなければ、そして周囲のことが気にならなければ、いつしか自己満足に陥り、現状に満足してしまうことになる。しかしながら、それはいつか周囲の怪物、敵に食われてしまうことを意味しており、仕事の世界においては大敗、そして会社の倒産を意味する。その原因は、周囲を見渡すことを怠り、社会環境の変化に気づかず、また、競合が何をしているのかということについても深い関心が払われなかったことにある。自分の世界観をもっと広げていかない限り、大海の情報は伝わってこない。
よって会長職として大事なことは、正確な情報の収集にある。世界の政治経済情勢を見極め、日本経済の未来を見据え、自社の立ち位置を鋭く分析したうえで、マーケティングの構想を打ち出し、適時に事業展開を繰り広げることが課題となる。ちょっと難しい話になってきた。おそらく社員の半分以上はここで読むのをやめてしまうだろう。でもそれが、残念なことなのだ。なぜなら、情報の収集が命であり、自分の人生を支える基礎をつくりあげていく原動力となることを説明しているにも関らず、その大切さに気が付いてない証拠だからだ。
情報の収集とは、できるだけ多くの情報網、すなわちさまざまなメディアから、いろいろなことを学ぶことを意味する。自分の人生を振り返ってみた。中学生の頃から学校の勧めもあり、新聞を読み始めた。また、週刊誌も時折読むようになった。新聞を読む癖は、アメリカの高校でも続き、大学に入ってビジネス科の授業をとるようになると、Wall Street Journalのような社会経済と企業経営に特化した新聞にも目を通すようになった。こうしていつしか新聞と自分の生活は切り離せなくなり、テレビから得る情報源と共に、今日まで大切にしてきた。だからこそ、例えば、1週間出張して家をあけてしまっても、帰宅後は一生懸命になって一週間分も積み重なった新聞を読みこなしている。そこから得る情報の中には、思いもよらぬ大切な内容が、必ずと言っていいほどいくつもあるからだ。
昨今では、いくつかの経済誌にも目を通すことを心掛けている。週刊ダイヤモンド、日経ビジネス、東洋経済などは勿論、機会さえあれば、何でも読んでいる。何故ならば、そこに掲載されている情報をベースに、自らがとるべき行動、そして会社の経営戦略が見えてくるからだ。これらの情報が無ければ、どうやって企業を導いていくことができるのだろうか。地図がなければ、どうやって見知らぬジャングルを通り抜けて旅することができるのだろうか。正しい情報があって、はじめて進むべき道筋が見えてくる。だから、自分にとって、情報収集に徹するということは、サウンドハウスという会社を経営するために不可欠な、根本道場なのだ。
無論、今日では紙媒体だけでなく、デジタル系の情報も、いくつも活用している。多くの経済誌も今ではデジタル版が存在し、日経ビジネスなどは雑誌だけでなく、デジタル版も購読している。また、新聞もデジタル化している。よって読売新聞と徳島新聞のデジタル版も購読し、連日のようにニュースがメール配信されてくる。だったら、「全部デジタルにしてしまい、紙なんかやめちまえ!」という声が聞こえてきそうだ。しかしながら、一概にそうとも言えない。例えば新聞を例にとってみよう。日本経済新聞をバッと開いてみる。すると新聞の斜め読みに慣れた自分だと、1面全体に10〜20の細かい記事があったとしても、ものの数秒で斜め読みして、およその内容を把握できる。じっくりと読む記事は1ページあたり1~2件しかないのが普通だ。このざっくりとした読み方は新聞では可能だが、デジタル版ではできない。つまり紙の新聞の方が圧倒的に効率が良いのだ。この利点に今の若い世代はおそらく気づいていないのだろう。むしろ、新聞のインクで指が黒くなることを嫌がる。気持ちはわからないわけではないが、これも時代の流れなのか。
つまるところ、企業が成功するためには正確な情報の収集が不可欠だ。だから声をあげて、会社のスタッフには最低でも日本経済新聞には目を通しなさい、と長年にわたり言い続けてきた。特に昨今の日経はサウンドハウスの事業に通じるネット通販関連、量販店の動向、支払いシステムのデジタル化やセキュリティー問題、物流大手の事業展開、そしてSNSからAIまで、大事なトピックが日々、掲載されている。特に昨今のAIに関連する記事と、その内容の劇的な変化、スピード感には目を見張るものがある。さらには日経の夕刊には連日、音楽系の記事が最後のページに掲載されている。これも購読者の興味をそそるため、そして、購読者の層を広げるための工夫なのだろう。ミュージシャンにとっても面白い記事が頻繁に掲載されている。こんなにも大事な日経なのだが、会長の指示、指導にも関わらず、最近の社員は日経を読もうともしない。彼らの育った環境や教育が問題なのだろうか。究極の上司であるはずの会長の言うことを聞かない社員が多いことは、嘆かわしいことだ。
よって、会長としての自分の職務は、今もって、情報の収集が極めて重要な位置を占めることになる。それはニュースをたくさん見聞きするだけでなく、海外の知人らからも、さまざまな情報をゲットすることにもつながっている。サウンドハウスの強みは、世界各地に自分と親しい同業界の知人がいることに他ならない。長年にわたり培われてきた海外ネットワークと人脈により、普通の人が知りえない情報も時折、入手することができる。それらの情報をベースに、新たなる事業戦略を構築できるのだ。しかしながら、この海外情報のベースを活用するには相当なる英語力と、日本人以外のさまざま人種の人たちとの交流が不可欠である。これもまた、自分以外の社員にとっては大きな負担となっている。何故なら、英語ができない人があまりに多いからだ。英語が大事だよ、といくら言っても勉強しようとしない、英語を学ぶことを楽しもうとしない、という社風を見るかぎり、もしかするとこの会社の未来はもう、限られているのかもしれない。
情報収集は大事だ!みんな、ニュースに目を留めよ!日経を読もう!英語も勉強しよう!これらはサウンドハウスがNo.1で居続けるための条件であり、全く難しいことではない、と声を大にして言いたい。が、いくら言っても、それを真剣に考えない人が多いことを危惧する。だれかがその大切さに気付くまで、あえて自ら情報の収集に努めることにする。そして海外の要人とのパイプは、だれかがとって代われるまで、すべて自分が仕切ることとする。ああ、この果てしなきチャレンジは、夢であってほしい。そして夢から目覚める時、これらの多重責務から解放されている自分がいる。それが実は、夢のまた夢なのだ。