
私は長年にわたり、ライブ音響エンジニアリング業界に深く関わってきました。子どもの頃から父の右腕として、ロードスタッフのような仕事「ケーブルを巻いたり、ステージやPAシステムの設営・撤収」を手伝っていました。しかし、技術的な作業以上に、私は父がショーを円滑に進めるためにしていたすべてを注意深く観察していたのです。
重要なのは音だけではありませんでした。演奏者一人ひとりの個性や期待を理解し、うまく付き合いながら協力するのも大切なことでした。父は技術的な面だけでなく、さまざまな気質の人々に対しても、プロフェッショナルに、そして自然に対応する術を持っていました。
私たちスタッフは皆、短いスローガンがプリントされたTシャツを着ていました。しかし、その言葉は単なる技術サービスを超えた意味を持っており、どのアーティストにも「ちゃんと伝わっている」と感じてもらい、納得してもらうための姿勢を表していました。そのスローガンとは“No Problem!”(問題ない!)です。
現在の私は、父の足跡をたどるように、さまざまなイベントや公演にプロフェッショナルな音響サポートを提供しています。
長年のライブ音響の経験を通じて私が学んだのは、技術的なスキルが仕事の50%にすぎず、残りの50%は人間関係と心理的サポートにある、ということです。
さまざまな個性との出会い
この仕事を通じて、私はじつに多様な性格の人たちと関わってきました。ここでは、私がこれまでに出会った人々の行動の傾向と、それぞれの性格と信頼関係を築きながら、最適な音づくりを実現するために用いてきた戦略をご紹介します。
ミュージシャンと仕事をする際、私たちのやりとりの中心になるのは、彼らのモニターミックスです。できる限り良い音の指標を提供して、彼らのパフォーマンスを最大限に引き出せるよう努めています。
中には「何も言わない=うまくいっている」というタイプのミュージシャンもいます。こうした人たちは自分の求めるものを明確に理解しており、自信を持って要望を伝えてくれます。一度ミックスに満足すれば、その後の調整はほとんど必要としません。私の目標は、ミュージシャンが安心して自分の希望を伝えられるような環境を整えることです。そうしていると、彼らのパフォーマンスを最大限に支える最適なミックスを作ることができます。
「無言の不満分子」と呼べるタイプの人もいます。このタイプは自分の不満を直接は口にせず、周囲の人にはこぼすという表現方法を取る傾向があります。彼らのニーズがはっきりしないため、対応が難しい場合もあります。要望がないからといって、必ずしも満足しているとは限らないのです。すべてのミュージシャンに最適なミックスを提供するため、私は特に口数の少ない人に対して積極的に声をかけ「何か調整が必要ですか?」と確認するようにしています。最も効果的だと感じている戦略のひとつは、ステージ上でミュージシャンと一緒に過ごしながら、iPadを使ってリアルタイムでミックスを調整することです。この方法により、ミュージシャンの感情の動きや表情を観察しながら、その場で必要な対応ができ、彼らの最高のパフォーマンスを引き出すために本気で取り組んでいるという姿勢を伝えられます。

自分の求めているものがはっきりしていないミュージシャンもいます。特にステージ経験が浅い人の場合、モニターに対する要望をうまく言葉にできない場合があります。周囲で鳴っているライブバンドの音に慣れておらず、PAからの反射音に戸惑ってしまう場合もあります。そのため、自分のミックスに何を求めているのかを明確に伝えるのが難しいのです。
こうした場合には、「どう聴こえますか?」と尋ねるよりも、「ミックスの感じはどうですか?」と聞くほうが効果的だと感じています。この問いかけによって、ミュージシャンは細かな技術的要素よりも、自分の全体的な感覚に意識を向けやすくなります。さらに、私は必ずミュージシャンのモニター位置に立ち、バンドの演奏を実際にその場で聴くようにしています。その場で自分の耳で確認しながら調整を行って、彼らの音の指標を明確で整ったものにします。その後もう一度「今の感じはどうですか?」と確認して、ミュージシャンが自分にとって最適なミックスに近づけるよう導いています。
細かい調整をたくさん求めるミュージシャンもいます。こうしたミュージシャンは自分の好みを明確に把握しているため、実は満足させやすいタイプでもあります。しかし問題となるのは、頻繁に細かい要望が入って、他のバンドメンバーに割くべき時間や注意が不足してしまう可能性がある点です。バランスよく全体を見ながらの対応が求められます。
こうした場面では、バランスを取るのが非常に重要です。私は、やさしく丁寧に「一度に対応できるのは一つのリクエストだけですが、必要に応じて必ず戻って細かい調整を行います」と伝えるようにしています。そうして、相手に安心感を与えながら誠実に対応していきます。同時に、あまり発言しないミュージシャンにも常に注意を払い、たまに出される要望にも迅速かつ丁寧に対応するよう心がけています。
突発的で要求の強い発言をするけど無害なミュージシャンもいます。プレッシャーのかかる場面では、ミュージシャンが突然強い口調で要望を出す場合があります。その言い方に配慮がない場合もありますが、私はそうした行動の背景には、ストレスや時間的な制約があるのを理解しています。
大切なのは、こうした場面を個人的なものとして受け取らない点です。その後に相手が礼儀正しく、丁寧に接してくれるのであれば、特に気にする必要はありません。ある程度の打たれ強さを持つことは、この仕事では欠かせない要素です。感情に流されず、冷静さと集中力を保って、一時的な緊張に左右されず、常に最善のサポートを提供し続けられるのです。
中には、ミックスの内容とは関係なく、どうしても満足しないミュージシャンもいます。実際に私がCampus JAXで経験したケースでは、補聴器を着用していたバンドメンバーが、フロアモニターのミックスに苦労していました。補聴器を使っている場合、フロアモニターからの音をうまく聞き分けるのが難しく、さまざまな音が混ざってしまって判別しにくくなるため、非常に特殊な対応が求められます。このような場合は、単なる音の調整では解決できない場合も多く、より慎重で柔軟な対応が求められます。
この問題に対応するため、私は彼に補聴器を外し、インイヤーモニターを使うことを提案しました。そうすれば、彼の聴覚の状況に合わせたより正確なミックスを提供できるからです。実際、バンドの他のメンバーはインイヤーを使用していましたが、彼は自分のものを使うのに強く抵抗を示しました。私は時間をかけてフロアモニターのミックスを細かく調整しましたが、どの設定も彼の期待には応えられませんでした。要望を出すたびに彼の苛立ちは増し、最終的には、どんな技術的な対応をしても満足させられないと感じました。その時点で、私は心から謝罪し、彼の使用環境の制限の中でできる限りの対応はすべて尽くしたと丁寧に説明しました。
残念ながら、彼は苛立ちのあまり会場を立ち去ってしまいました。こういった状況では、すべての問題が自分の手に負えるものではないのを、私は学びました。重要なのは、たとえ相手が感情的になっていても、自分は常にプロフェッショナルで冷静かつ思いやりを持った姿勢を保つ点です。落ち着いた態度を崩さずに対応すると、最善のサービスを提供し続けられ、自分ではどうにもできない問題を必要以上に引きずらず、健全に仕事に向き合えます。

少し知識があるつもりで、実はよく分かっていないミュージシャンもいます。「少しの知識は時に危険」と言われるように、ある程度の専門用語を使ってミックスの要望を伝えてくるものの、その言葉の意味を正確に理解していない場合があります。こうした場面で、相手を訂正したり知識不足を指摘したりすると、かえって気まずい雰囲気になってしまう場合があります。私はそういったとき、言葉の正確さにこだわるのではなく、その人が本当に求めている「意図」を読み取り、それに基づいて必要な調整を行うようにしています。結果として、ミュージシャンが望んでいる音に近づけられます。
たとえば、シンガーが「自分の声にもっと低音を加えてほしい」とリクエストしてきた場合、本来の低音域(60〜100Hz)は人の声域とは一致しない点を私は理解しています。単純にボーカルチャンネルの低音を上げても、彼らが求めている効果にはつながらない可能性が高いのです。そのような場合、私は他の要素とのバランスに注目します。たとえば、アコースティックギターのような楽器はロー・ミッド帯域に音を多く含んでおり、それがシンガーの声の下の成分をマスキングしてしまっている可能性があります。そういった周波数を調整して、結果的にシンガーの声の「太さ」や「深み」を際立たせられます。
調整を行ったあと、私は「どう聞こえますか?」ではなく、「今の感じはどうですか?」と尋ねるようにしています。この言い方によって、相手の意識を専門的な用語から自身の実際の聴覚体験へと自然に切り替えられます。その結果、より正確にミュージシャンのニーズを把握し、彼らが本当に求めているミックスを実現できるのです。同時に、こうした丁寧で協調的なやり取りが、良好な信頼関係を築くうえでも非常に効果的です。
「音が大きすぎる」と訴えてくる教会の会衆。ハウス・オブ・ワーシップ(礼拝会場)で音響を担当していると、「音が大きすぎる」と会衆から声をかけられることは珍しくありません。多くの場合、苦情を言ってくる時点でその人はすでにかなり不満を感じており、感情的になっている場合もあります。そうした場面では、私は共感と思いやりを持って冷静に対応し、状況を和らげるよう心がけています。同時に、会場全体における礼拝体験の質を守るのも大切な役割です。すべての人が心地よく礼拝に集中できる環境を保つために、バランスの取れた対応が求められます。
このような状況では、私はまず落ち着いて相手の不快感に共感を示し、実用的な解決策を提案します。たとえば、会場内の比較的静かな座席に案内したり、希望があれば耳栓をお渡しする場合もあります。また、私がときどき使うさりげなく効果的な方法に、「プラセボフェーダー」と呼んでいるテクニックがあります。これは、実際には全体の音量に影響しないフェーダーをあえて下げる動作を見せて、「音が小さくなった」と心理的に感じてもらうためのものです。この視覚的な操作によって、ミックスを犠牲にせず相手の不満を解消できる場合も多くあります。
「問題ない」
正直に言えば、長年の経験を積んだ今でも、ライブ音響エンジニアという役割に伴う多様な個性や状況に対応する力は、まだ成長の途中だと感じています。それでも、自分が苛立ちを感じたときには、一度立ち止まって気持ちを整え、父が私に教えてくれた「問題ない」の精神を思い出すようにしています。それは、柔軟に対応する姿勢、プロフェッショナルとしての自覚、そして何よりも人に対して丁寧に、思いやりをもって奉仕するという心構えです。









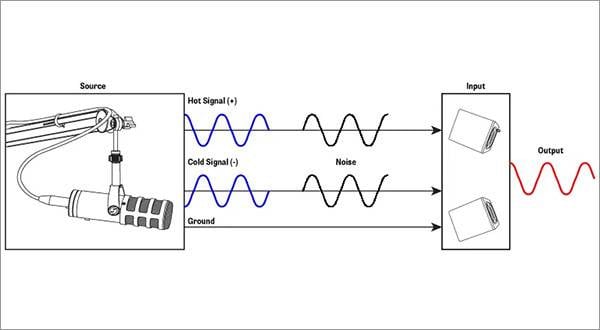
 QSC パワードスピーカー Kファミリー
QSC パワードスピーカー Kファミリー
 QSC パッシブスピーカー Eシリーズ
QSC パッシブスピーカー Eシリーズ
 QSC デジタルミキサー TouchMixシリーズ
QSC デジタルミキサー TouchMixシリーズ
 QSC Acoustic Designシリーズ
QSC Acoustic Designシリーズ
 QSC パワーアンプ特集
QSC パワーアンプ特集
 QSC
QSC

















