今回の記事は工作機械や技術が多く絡む内容となります。過去のPartはこちらから。
⇒ 大海の孤島を捜して~ATLANSIA~ Part1
⇒ 大海の孤島を捜して~ATLANSIA~ Part2
⇒ 大海の孤島を捜して~ATLANSIA~ Part3
~Part 4 Contents~
Cheena:前回は脱線してたのを切って終わりました。今回はどこから始めましょうか。
ネモト:そうねぇ。興味ある方は少なそうだけど、製法や工作機械なんかどうでしょう?
1 - ATLANSIA Crafts & Machines
Cheena:工作機械!いや、話が面白いことは間違いないですがどこから手を付けるべきか難しいですね。
とりあえず製法というか楽器関連技術から始めますか?
ネモト:そうだね。あっちこっちに話が飛ぶと思うから大事なところをまずやっておこう。
Cheena:トラスロッドの仕込み方、サポートロッドの採用、あたりからにしましょうか。
一般的にロッドはネック主材の表側に切り込みを入れて指板で覆うか、裏側から導入してスカンクライン状に塞ぐところ、アトランシアではネックエンドから真っ直ぐ穴を開けてロッドを導入しています。(No.3、PAT.1421968)これにより音響的に有利とのことですが、ロッド交換となると大変じゃないか…?と思ったり。
ネモト:私も初めて知った時はええ…?ってなったなー。ロッド交換は確かに面倒そうだけど、何かしら考えてあるのかな…。ネックの強度にはかなり自信があるからロッドを回し切ることなんてないとか思ってるかも。
Cheena:あとで、もしかしたら別記事になりますが、特許文書を出します。固定無しでも内部で振動しない何かしらの工作があるかもしれない。
ちなみにサポートは豪勢に2本、これはネック裏から、入っています。この強度に関しては、代表の林さんが水平に渡したネックにぶら下がっている写真は割と有名だと思います(笑)
※アトランシア公式Facebookから
https://www.facebook.com/334082209985909/photos/pb.100079886373939.-2207520000./522894467771348/?type=3
https://m.facebook.com/334082209985909/photos/a.342059922521471/1077211085673014/?type=3
あと購入者レビューを見ているとロッドが効くか不安なほど強靭とまで書かれていますね。
ネモト:あの画像はパッと見ギャグだよね。
サポートロッドが仕込まれた6弦のネックには(当たり前だけど)埋め木が2本あって、サポートロッドがあるのを知らなかったからなんだこれって驚いた。なんかいつも驚いている気がする。
しかし、ロッドが効くか不安って途轍もないね。
Cheena:効いたとしても、ゆっくり曲がってくるような効き方しそうですね…捩れもなさそう。
ネモト:後学のために、いつか買ったらネックが真っ直ぐでも試そう。
Cheena:もう終売してしまったはずですが、Fender OEMも気になるんですよね。さすがにアトランシアラインと比較したら強度は落ちると思いますが…
ネモト:フェンダージャパンの下請けをやってたんだよね。ウチで作ったネックは曲がらないぞって林さんが言ってた。いわゆる「当たり」の個体はアトランシア製かも。
Cheena:あり得ますね。
さて、このような独特の構造を作り出す機械やソフトウェアの方も、アトランシアでは制作していたりします。
ネモト:治具はじめ小さな工具の製作は珍しくないけど、CNCまでやっちゃうから凄い。
Cheena:最近は家庭用大型NCとしてエスラボ「黒い奴」だったり、もっと小型のもので(確か)オープンソースキットの「CNC 3018」などが市販されていますが、それらとは比にならないレベルでの製作ですからね。
なおアトランシアのホームページには工作機械のページ自体はあるのですが、個別の解説は作り途中のようです。2007年から更新されてない…
ネモト:面倒になったのか、企業秘密とすることにしたのか…。工作機械そのものはファナックってことは楽器製作用に細々とカスタムしたってところか。めっちゃ参考になるから詳しく見たい。
Cheena:あとは制御側の方、例えばフレットワークに関する計算ソフトも内製しているようですね。微分音階も計算可能だとか…Victoria 48がこれを使って作られたものでしょう。

ネモト:48フレットか。モノネオンが好きならみたいなところがあるかな。個人的に。
あとはルーターテーブルなんかも見てみたいなあ。どのくらいの大きさが適正なのかイマイチわからない。CNC持ってないから知ったところでどうなるって話ではあるが…。
Cheena:個人的な趣味も兼ねて言うと加工範囲が120cm×75cm×10cmあればかなり良いと思います。ここまであればスルーネックのベース(仕込み角無し)がざっくり成形できますし、そうじゃなくても普通にネックが作れますね。
ただ、アトランシアではスルーネックは作っていないみたいですし、ボディを作るとしてもPegasusのホーンを分割してるあたりそこまで大きくないんじゃないかな…
ネモト:ほうほう、なるほど。
確かにアトランシアはボルトオンばっかりだからもうちょい小さくてもいいのか。気になったんだけど、CAMソフトは何を使ってるのかな。これも知ったところでどうなの?って話なんだけど気になるものは気になる。Fusion360とかかな…。
Cheena:FANUCが提供するCAMを使っているというのが1番あり得ると思います。3Dプリンタ界隈では時々Gcode手打ちする恐ろしい人たちもいるけど、さすがにそこまではやってないでしょう…
※Fusion 360…Autodeskが提供する、3Dデータをデザインするためのソフトウェア(CAD)。非常に強力で、後述のCAMや各種シミュレータも兼ねる。
※CAM…CADで生成したデータを機械加工するためのコード群(Gcode)に変換するソフトウェア。Gcode自体は単純な文字列だが、座標指定では非常に面倒な「円弧」の軌道を1行で指定したり、エンドミルの直径や長さを補正できる。
ネモト:ボケてたー。確かにメーカー提供のソフトという選択肢が真っ先に来るべきだわ。色々と融通効く。しかし、手打ちとかウソだろ…コマンド手打ちで挙動制御してたLinuxユーザーの生き残りか…?
※今は便利にカスタマイズされたLinuxディストリビューションがたくさんあるので手打ちで色々やらなきゃいけないわけではないです。手打ちで色々やらなきゃいけない素のLinuxもあります。
Cheena:Gcode覗いてZ軸(高さ)変更前に一時停止挟むとか、そういうレベルでの話はよく聞きます。例えば3DPだと、空間の"天井"を作る前に停止することでナットや磁石を埋め込めるんですね。といっても1個間違えたらわりと簡単に崩壊するので大変です…
ネモト:そうだよね。ひとつ間違えたら…。昔ちょこっとだけプログラミング学んだけど、間違えたら終わるコード(この階層より上/下のデータ全部消すとか)あるからね。root権限怖いぜぇ…。
Cheena:だからこそCAMや仮想化環境が発達したんですね。文明最高。
ネモト:進化は止まらないなー。
ルータービットは何使ってるんだろう?無難にストレートかな?ちょっと高いけどコンプレッション?まぁ、全部使ってるんだろうし山ほど特殊ビット使ってると言われたらそれまでなんだけどさ。どれが多いのかなと少し気になった。
Cheena:これはビットの話からしておきましょうか…
ストレートというのは刃がビットの軸方向にまっすぐ着いているもので、安価ですが狭い空間での切り屑の排出という点では少し劣ります。ハンドルーターやトリマーで外周部を削るときにはこれが便利ですね。
コンプレッション、又はスパイラルは刃が螺旋状になっており、螺旋の方向によって
・切り屑が上がってくるため削りやすいが、フチが荒れやすい(上方向への螺旋、ドリル刃と同じ)
・フチが荒れづらいが、切り屑が押し込まれて削りづらい(下方向)
・フチも底も綺麗に仕上がるが、高価。また、螺旋の切り替わる高さに特有の切削跡がつく(下半分は上方向、上半分は下)
の3種類があります。
CNCから出してすぐの写真は見たことがないのでスパイラルかストレートかは分かりませんが、アトランシアで多用されていると思われるのは刃の底が球状のボールエンドミル、又は底の角が丸いラウンドエンドミルですね。ノブやネック、ピックアップの周りの落とし込み加工には底が四角いスクエアエンドミルでは大変ですし、時間もかかります。
もちろん、通常のネックポケットやピックアップキャビティにはスクエアを使用しているでしょう。
あと確実にあるだろうというのは軸より刃の径が大きい、T字型をしたコロ付きミゾビットの類です。ダボ穴を開けるための専用のビットですが、

Pegasusの継ぎ部分、ここの端が丸いダボ穴の形状はミゾビット特有のものです。
ネモト:細かく書いてもらってありがとう。ダボ穴から推察するとは流石だね。ビットって地味に高くて一般人だと揃えるのがキツい。
Cheena:一応、切削面を上に向けてスクエアビットで切断すれば作れない形状ではないですが位置合わせなどの面で現実的ではないということで…。5軸NCならいけます。
ビット、鉋や鑿や彫刻刀と違って研ぎづらいし、物によってはそもそも研げないし、ノコヤスリがいかに偉大か日々思い知っています。
あとアトランシアの製作で見ていて変な声が出たのはこれでしょうか。

ブッシュをエポキシで固めて、その上で飛び出した部分を削っているようですが…
ネモト:なんじゃこれ…?とんでもないことを…。
Cheena:こうなるようです。



※Victoriaの5弦仕様は4弦と同じヘッドの中央にペグを30度傾けて取り付けることが特徴となっています。そのままではブッシュと弦が干渉してしまうため、上2枚目の追加工で更に削り落としていて、その部分がわずかに見えています。
ネモト:やりたいことはわかるが本当にやるとは思わなかったって感じだ。
Cheena:材自体の割れ/欠け耐性、工作機械の精度、全てに自信がなければできない加工ですね…
少なくとも私はこれでツライチ出す作業をしたくないです。でもフラットヘッドだから作業台にきっちり押し付ければ大丈夫なのかな…
ネモト:なんらかの治具を使っているかもね。それでも不安だけどな…。端材でじっくり練習しても不安は拭い切れないと思う。私がチキンなだけかもしれないけど。
Cheena:一枚目を見る限り使っていなさそうですね。まあ高さ固定はしているでしょうが、金属と木材は切削条件が真逆(金属は低速回転、木材は高速)なのでプレーナーみたくまとめて削る訳にはいかないですね。
ネモト:いや、例えばネックを指定した角度で完全に固定したりして、リスクを下げられるようなもの…って治具じゃないわ。取付具だ。申し訳ない。まとめて削れたら便利なのになー。
Cheena:まとめて削るには…サンダーです。多分オービタルでもランダムアクションでも大丈夫…
ネモト:サンダーか。磨きがめんどそう…。といってもモノ次第だからおいそれとは言えないかな。
Cheena:金属と木材の複合材となると冷却が難しそうなのがネックですね。液体窒素吹くしかなさそう…
ネモト:あー…切削剤使うと木部に悪影響出そうだね。シミになりそう。
Cheena:切削加工に造詣の深い方には解説不要と思いますが、金属加工には摩擦低下と冷却を兼ねた液剤を使用します。これの成分は油脂を含む水で、木材が吸うとまずいので(そもそも木材加工には不要です)揮発性かつ非引火性のなにがしかを使うしかないという話ですね。
ただもちろん、液体窒素レベルでの冷却では金属を収縮させ木材も凍結し、最悪の場合両者を破壊するので危険な冗談と受け取ってくださいまし……
ネモト:液体窒素は気化に伴って爆発したり(気化すると750倍の体積になるので生半可な容器だと内圧に負ける。指定外の密閉容器に入れなければ大丈夫)同じく気化した液体窒素で酸欠のリスクもあります(密室にいなければ大丈夫)のでマジで真似しないでくださいね。
Cheena:ちなみに、一応費用を無視すれば個人で液体窒素の購入もできますが、液体窒素が蒸発するうちに液体酸素に置き換わることがありまして…木材加工の場にあってはならないですね。
さてそろそろ戻りましょうか。液体窒素はラッカーにクラック入れるのに使うぐらいにとどめておきましょう。
ネモト:OK、次は何にしよう?
2 - ATLANSIA STRING LOCK WINDER
Cheena:加工や技術関連で外すことができない話題として書いておきたかったのですが、情報が非常に少ないのです。どうしよう。
アトランシアオリジナルデザインペグ、No.15 STRING LOCK WINDER、No.97 STRING WINDER " SHIMESHIME " の2つのうち、問題は前者の方。
PDFしかない上に文字が潰れていますね。特許自体はトップロック式のペグです。
ネモト:封印されたんじゃなかったっけ?写真でしか見たことない。搭載されたのは相当レアだろうね。




Cheena:そうです。アトランシアのパテントページには、
「弦の緩みが防止出来、しかもSHAFTへの巻き数が 少なくてすむこのWINDERは1981年にPATENT申請、公開公報に発表され登録されました。 その後、日本のMAKER、M社による抵触の処理に追われている間に、米国の SP社が、BACKよりLOCKするTYPEを発表。その時点で係争を断念。 今では、象徴的存在となりましたが、現役で、ATLANSIAの 一部MODELに使用しております。日の目を見たとは程遠い、不完全燃焼の状態で終わりました。」
※出典:アトランシア公式サイト
とありますね。
ネモト:残念。使ってみたかった。
Cheena:ページ自体は2001年あたりに更新されたとあるので、当時の上位機種を入手する機会があればもしかしたら…。
PRSのPhase IIやPhase IIIは構造が一緒なので、ベースにこれが搭載されたら近いものになるはずですね。バックロックやマグナムロックより遥かに構造がシンプルなので通し穴シャフトの二次加工か交換で作れないこともないのかな。今度やってみます。
さてこの後も幾つかぶっ飛んだトークが続きますが…
一旦休憩としますか?
ネモト:そうしましょうか。なかなかの長さだし。
では解散!
※画像はATLANSIA公式サイト、公式Facebookより引用
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら

















 ベース弦の選び方
ベース弦の選び方
 ベーススタートガイド
ベーススタートガイド
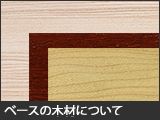 ベースの木材について
ベースの木材について
 ベースの各部名称
ベースの各部名称
 ベースの選び方
ベースの選び方
 ベース初心者講座
ベース初心者講座
















