エレキギターにとって切っても切れないエフェクター、ワウペダル。
筆者は初めて買ったエフェクターはオーバードライブでしたが(IbenezのTS-5だったなぁ~)次に買ったのが GCB-95 CRYBABY でした。
当時はビジュアル系ブーム真っ只中で、周りがグレイとかラルクアンシエルとかを聴いている中でエリッククラプトンやジミヘンドリックスにハマっていた中学生だったので案の定友達は少なかったです(笑)
足で音色が動かせるなんてカッコイイ!!と思って買ったものの、バンドやるようになったらそんなに出番はないし重いしでかいし、持ち出さなくなったのを覚えています。当時から『BOSSのコンパクトくらいのワウがあればいいのに!』とか思っていましたが、そこから20年後くらいにミニワウが発売された時は飛びつきましたね。
と、そんな話は置いておいて。
家を掃除していたらこんなものが出てきました。

15年くらい前のエフェクターを改造しまくっていたころに実験台になった可哀そうな VOX V845 です。
Mooerのフットスイッチキャップを横に無理やりくっつけてLEDのレンズみたいにしています(笑)

逆側は穴だらけ。
このような犠牲を伴いながらエフェクターの回路や改造方法を覚えていったわけです。
(なおVOX V845はそのままでいい音がします)
MOOER ( ムーアー ) / Mushroom Footswitch Hat FT-MTP 10pcs
そんなこんなで、以前はとあるショップでワウのモディファイ作業なども行ったりもしていました。
ワウペダルをいじっていて思っていたことがあります。
それは『多少の調整は誰でもできる』ということです。
もちろんワウ改造の定番のトゥルーバイパス化&LED取り付けやガリが出たからポットの交換なんて作業は、はんだ付けや穴あけなど多少の技術や知識や道具がないとできないので、改造を受けてくれるショップに依頼するなどした方がよい訳ですが、ちょっとした調整やメンテナンスはご自身でもできます。(人によって向き不向きはあるけれど……)
できるようになって損はないです。
今回は簡単にドライバーとスパナくらいでできる調整を挙げてみます。
ただし、パーツを外したりはしますので作業は自己責任で行ってください。
01. 可変域の調整
可変域をスイッチやつまみで変えることができる機種がありますが
JIM DUNLOP ( ジムダンロップ ) / CBM95 Crybaby Mini Wah
JIM DUNLOP ( ジムダンロップ ) / CRY BABY 95Q WAH
無くても調整はできます。
定番のGCB95を見てみましょう。
JIM DUNLOP ( ジムダンロップ ) / GCB-95 CRYBABY WAH WAH
現行品の裏蓋を開けるとこのようになっています。

現行の基板は赤いんですね。
まずギヤのシャフトを押さえているパーツのネジを外して

ギヤシャフトをずらします

高い方に変化させたければ反時計回りに、低い方にしたければ時計回りにポットをほんの少し回してください。
ギヤの噛み合わせ1つ分くらいでもかかり方が変わります。
シャフトを戻して完了です。

これだけ?と思うかもしれませんがこれだけです。
これだけで大分印象が変わります。
ジミヘンのワウは低域に効くように改造されていた!なんて噂も聞きますが、基板をいじらなくてもこの調整だけでできます。
ほんの少し回しただけで可変域の変化が感じられる物だったりしますのでトライ&エラーで好みの位置を探してください。
ポットの周り幅は限界があるので、ギヤとポットの限界のところで固定して無理やり踏み込んだら壊れた!なんてことがないように注意してください。
02. フットスイッチの踏みやすさ
ワウのON/OFFはペダルを手前に踏み込んで行うことは皆さんご存知かと思いますが、このスイッチの感度の具合の好みは人によって割と違います。
同じワウでも人によって「弾いている間に勝手に切り替わってしまう!」という人もいれば、「前に踏み込んでも全然切り変わらない!」という人もいます。そうなると自身で調整できるに越したことはありません。
ゴムとフェルトがクッションになっているので、ゴムを切断したり取っ払ったりフェルトの上にピックを貼って固くすることでON/OFFしやすくなるぜ!なんてことをしてある個体も見たことありましたが、正直どちらもあまりよくないです。
ペダルがスイッチにガシャガシャ当たりすぎるとノイズの原因にもなります。
純正で取り付けられているJimDunlopのスイッチはシャフトが長くできており、固定しているナットの位置を少しずらすことで調整できます。
スイッチ側のナットを外して

内部のナットを少し回して

再度取り付け直すことで高さ調整ができます。ここもほんの少し回すだけでも変わりますのでナット半周ほど回しては組み立てて試して、再度ナットを外して……と、トライ&エラーで調整してください。
なおラジオペンチなどで無理にナットを回すと傷が入るので薄手のスパナなどで行ってください。
このON/OFFの感度調整は座って行っているといざスタジオなどで立って演奏した際に、切り変わりやすすぎる場合がありますので立ったり座ったりしながらちょうど良いON/OFFポイントを探すとよいです。
03. その他メンテ
ワウペダルは置いておくとほこりが入り込んだりしやすいので、定期的にメンテナンスを行った方が長持ちします。
特にギヤの部分はグリスが塗ってあるので埃がつきやすいです。埃はポットのガリの原因にもなりますので、あまりに埃がついている場合は綿棒などでグリスを拭き取ってください。
ただしグリスがないと踏んだ時にギシギシ音を立てるようになってしまうのでその場合は
このようなグリスを塗布してください。車用品などの売り場に売っているシリコングリスなどでもよいです。
塗りすぎは逆に埃がつきやすくなるので少量でよいです。少なすぎてもダメですが……
ペダル裏のゴムが取れて紛失してしまった、過去に切断してしまった、などの場合は交換用のゴムが販売されています。
JIM DUNLOP ( ジムダンロップ ) / ECB124
長く使用しているとフェルトもすり減ってしまいます。ON/OFFしづらいなと思ったら厚手のシールになっているフェルトシートがホームセンターなどで購入できるので切って貼りなおすとよいです。
今回は以上です。
簡単にできる範囲で書きましたが、今回書いたような作業はあくまでも自己責任で行ってください。機械いじりに全く自信がない方はやらない方が賢明なこともあります。
エフェクター改造やシールド自作などもそうですが、できる人は数々失敗しては原因を探ってエフェクターやプラグをダメにして……ということを繰り返して技術や知識を身に着けています。
安く済まそうと思って自作して思ったようにならなかったからこの製品は不良品だ!!と言ってしまう人は向いていないので、止めた方がよいと思う今日この頃です。
ワウペダルのネタは他にもあるのでまた書きたいと思います。










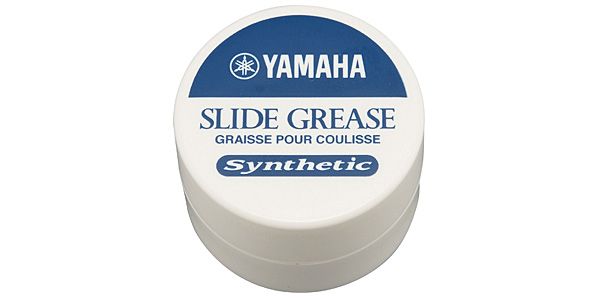








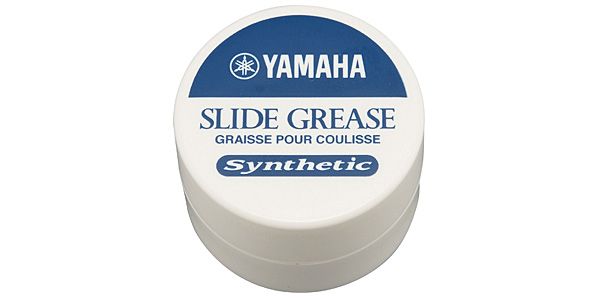











 プレイテックのギターを最強に改造!!
プレイテックのギターを最強に改造!!
 ギター 初心者講座
ギター 初心者講座
 ギターのお手入れ
ギターのお手入れ
 お手入れに必要な道具
お手入れに必要な道具
 エフェクターのつなぎ方
エフェクターのつなぎ方
 エフェクターの種類
エフェクターの種類
















