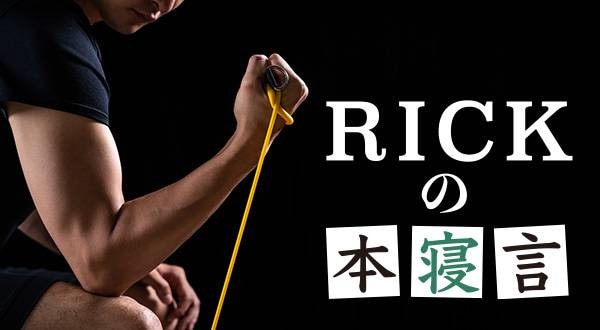時間に追われる日々は、いつまで続くのだろうか!三足も四足も草鞋を履いているため、自分がやるべきタスクは、いつも目の前に積み重なっている。その流れには、とぎれがない。そして責任ある対応を心掛けていると、瞬く間に時間がなくなり、自分のやりたいことがほとんどできずに、毎日が終わってしまう。これも空しいことだ。
自分の時間が無くなる理由はいくつもある。それは決して、自分が社員に仕事を任せてないからではない。むしろ逆で、自分ほど社員に対して仕事を任せきっている経営者は、なかなかいないと自負している。自分が仕事に介入するのは、自分にしかできない仕事がある時、そして社員だけでは上手に取り計らうことができないことから結果を出せず、周りも助けてくれないか、その支援の手が差し伸べられるのが遅すぎる時だ。問題は明らかに後者だ。すなわち、自分が介入しなければならないと思わされてしまうような場面に連日、頻繁に出くわしてしまうのだ。
これを社員教育の問題と言う人もいる。確かにそれも一理ある。しかし根本的な課題は他にもありそうだ。その一因が芋メールとみている。芋とはなにか?カロリーは高く、ボリュームもあり、時には美味しそうに見えることがある。が、決して主食にはなれない、何か中途半端な食べ物ではないか。ワンランク下のことを芋、と言うことがある。俗語辞典によると、1970年代後半の頃から野暮ったいこと、ダサいこと、垢ぬけないことを「イモい」と若者が言うようになったとのこと。だから「イモねーちゃん」なんていう言葉が流行った時代がある。そんな言葉の記憶が脳裏に残っているからだろうか、あまりにも多く読まされる芋メールには、正直、愕然とすることが少なくない。
典型的な芋メールは、まず、意味がわからないという、しょうもないメールだ。何が言いたいんだ!と思うだけで、自分の大切な時間が無駄になる。さらに文法エラーも散見され、読みづらいのも芋メールの特徴だ。昨今、とにかくまともな文章をさっと書ける人が少なくなってきたように思う。その結果、あちらこちらに芋メールが散乱することになる。
だったら、そんなメール読まなきゃいいじゃん!という声が聞こえてくる。確かにそうかもしれない。社員の報告書をいちいち会長の自分が目を通すのは、愚の極めかもしれない。しかし往々にして、その芋メールの中には芋ではなく、会社側としても真摯に受け止めて、対処しなければならないコンテンツが埋もれていることがある。社員の悲鳴などは、その一例だ。誰もその声を聞いてくれない。だから社員は芋が地中に埋もれているように、芋メールを地中で叫ぶ。それをだれも掘り起こさないのがいけないのだ。メールを読む人がいなければ、その社員が書いた大切なメッセージは無視されることになり、会社にとってもロスとなってしまうことを危惧する。だから自分は社員の報告書に目を通すことにしている。他の誰かがしかと対応してくれることがわかるまでは、時間をかけてでも報告書に目を通すことを日課としている。だから、自分の時間が無くなる。
ここまで書くと、愚痴っぽく聞こえてしまうのも仕方がないことだ。しかしながら、この試練はあえて受けて立たなければならないのが自分の宿命であり、所詮、自分の責任と考えている。会社を設立するということは、自分の子供ができるのと一緒だ。一度、生んだからには、親としての責任が生じる。その責任から逃れることはできず、まともな親ならば、子供がひとり立ちするまで教育し、それまでは経済的にも支えていくことになる。よって、会長職としての自分の仕事は、みんながひとり立ちして、会長の介入なく、きちんと仕事をこなし、まともな結果を出してくれるまでは、お付き合いせざるを得ない。その目標が達成できるまでは、とことん、現実の課題、問題に向き合って、逃げることなく日々、対処するのが自分の使命である。それは宿命とも言えるかもしれない。そんな運命的な責任を、いつも感じている。その結果、週7日、連日遅くまで仕事をこなしながら、ふと気が付くと、自分の時間がなくなっているのだ。それが空しくなくて、何と言おうか。
今、自分に必要なのは、9時間というタイムスパンが日々、延ばされることだ。この3年間を振り返ってみても、自分にとっては一目瞭然だ。これまでやりたくても、できなかったことをリストアップしてみた。大事な順番とは言えないが、思いつくままに書く。
- ギターの練習
- ピアノを弾きながらの作曲
- 演奏するための打ち込み
- アイスホッケークラブの練習に夜参加
- 可愛い彼女とデート(可能性なしの夢)
- 歴史関連の読書200冊+
- 1日1原稿の執筆
これらに該当する時間も考えてみた。ギターの練習は、1日1時間はするべきだ。もうかれこれ45年ほど、しなくなった。指先の皮もふにゃふにゃのまま、放置されている。このままでは音楽離れしすぎてしまうと焦るも、時が経つのが早すぎる。2と3は、1日30分でもあると有難い。そもそも作曲活動も1994年、今から30年前に止まってしまった。4のアイスホッケーは週3回、チームの練習があるのだが、全く行けてない。1回行くことに実技が1.5時間と車の行き来などで、4時間以上がぶっとぶ。週3回行くと、およそ14時間、1日あたり2時間近くの時間が費やされる計算になる。5は情けないことに相手がいないので、実現不可だ。そもそもデートには時間とお金がかかる。そんな暇はないというのは単なる言い訳にすぎず、悲しいかな、夢は空しく去っていく。6の読書は1日1時間はこなさなければいけないと思っている。読まなければならない本が、今や自分のデスクの上に山積みされている。そして執筆となると、それなりに時間をかなり食う。1日3時間は費やさなければならない。
するとどうだろう。これらのやりたいことを実現するためには、連日9時間ほどの時間が必要になるのだ。つまり、現状を打破しない限り、1日33時間なければ実現できないことなのだ。しかし現実は厳しい。前述したとおり、会社の仕事に関わり、社員を指導しているうちにもたつき、芋掘りに没頭してしまうことになる。気が付くと芋メール処理も含め、あっと言う間に1日が終わっている。こんな人生の歩み方では、時間が足りなくなることは明白だ。
答えはあるのか?やはり1日の時間を長くするしかない。1日24時間というその時間軸が短すぎるのが問題なのだ。この1日という時間が33時間あれば、自分が本来やるべきこと、やりたいことがきちんとできるようになる。神様はそのような新世代、異次元の時間帯を創ってくださらないだろうか。無理を承知で祈ってみることにする。
そうこうしているうちに、さらに時は過ぎ去っていく。こんなつまらん原稿を書いている暇があれば、それこそギターでも弾いていたほうが自分のためになるかもしれない。しかし、もしかしてこの原稿を読んで心が動かされ、芋メールを放り投げていたことを改心し、優れた内容のメールを書くことを目指して学びたい、と純朴に考えてくれる社員がいるかもしれない、と思えば、一概に無駄とも言えないのだ。一縷の望みはある。その積み重ねがいつしか実を結び、芋メールがなくなり、美味しい実を結ぶブドウのメールに様変わりすることを夢見る。それだけでも1日、数時間は解放される。まだまだ希望は残されている。それに賭けてみたい。