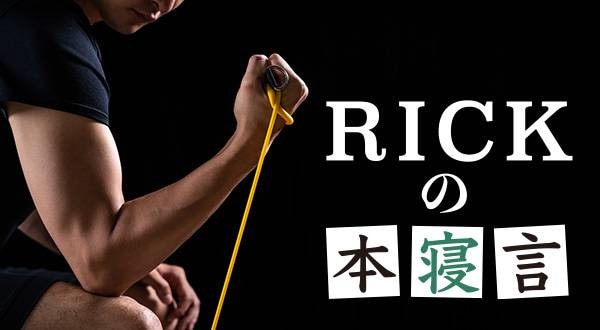2023年の11月からスタートした四国八十八ヶ所の遍路巡り。走り始めてから延べ19日目、GW連休中の5月3日、遂に走行距離が1,000㎞を突破した。想像を絶する苦しい自分との闘いの連続だったが、残り3日で四国一周を完結できると見込んでいる。22日間で1,200㎞を超える遍路みちを完走することが目標だ。当初は30日間を想定していたが、数々の難関を乗り越えてトレーニングを続け、体が順応してくるにつれて、1日あたりの走行距離をどんどんと伸ばしてきた結果、一週間以上前倒しで完走する見込みがついたことに、自分でも驚いている。
遍路にチャレンジする時間は限られている。仕事もしなければならないことから、常にノートパソコンをリュックに入れたまま走っている。その中には水や栄養ドリンク、最低限の着替えなどがあるから、いつもリュックはパンパンだ。それでも走ることに負担がかからないよう、重量は最小限にとどめている。もしかしてノートパソコンを掲げて遍路を22日間で走るのは、自分が史上初めてで、最後かもしれない。そしていつも何故か着ているウェアーは黒。10年ほど前、琉球宮古島で出会った著名なユタ、預言者の方が「空海が山々を黒い服を着て素早く走っているのを見た」という言葉が、ふと蘇る。自分が所有している遍路用のスポーツウェアはすべて黒だった。
そもそも多くの難所、山道が連なる1,200㎞の遍路みちを22日間で完走することなど、まさに自分に重圧を課すことになる無茶なプランだ。無理難題が山積みとなる厳しい条件を知っているある知人は、それを「拷問」と言う。確かにそれが適切な言葉のようにも思える。本当に死ぬ覚悟がなければ、通り抜けられないような難所がいくつもあり、しかも日中に走りきらなければならないという時間制限がある。それでも我慢に我慢を重ね、耐えがたきを耐えつつ、神の哀れみによってかろうじてセーフ、命が保たれているから幸いだ。こうして最後の3日に今、備えていることが奇跡かもしれない。
何としてでも四国の遍路みちをすべて走り抜けたいという強い意志があったからこそ、ここまで走り切ることができたのではないかと思う。その一番の目的は、四国八十八ヶ所の遍路とは、剣山を崇拝するための参道であることを自分の目で確認し、それを世に知らしめることであった。これまで誰も説明することもなく、巷では自分の足で実際に見たこともない多くの人々が、思いのままに遍路についてありきたりのことを執筆している。それは良しとして、肝心の剣山については、四国八十八ヶ所の遍路と紐づけられることがなく、説明がなされていない。少なくとも自分の知る限りでは、一件もない。キリスト教系のライターとして著名な宇野正美氏は、著書の中で剣山は第十番札所切幡寺からしか見れない、と記しているが、それも間違いだ。剣山を崇拝するために、遍路はいたる箇所で迂回している。よって正しい情報を世に知らしめ、歴史の真相に迫る情報を提供するのが自分の役目だ。そのためなら、拷問でも受けて立つ、という覚悟で臨んだ。
遍路みちのチャレンジは、挫折の連続であり、ありえないことが次々と起きた。人生、初体験の遍路みちだけに、当然のことかもしれない。その苦しみを、第一番札所霊山寺からはじまった第1日目の遍路ランから味わうことになった。それは2023年7月23日、真夏の炎天下で起きた。真夏にフルマラソンを走ったこともあることから油断していた。日中、みるみるうちに気温は上昇し、30度を超えてきた。しかも第一番霊山寺から第十番切幡寺までの遍路みちはほぼ、道路が真っ黒のアスファルトだ。よって地面からは太陽の熱で温まった熱気がむらむらとこみ上げ、体感では40度以上の暑さになっていたことに違いはない。リュックには水が2本しか入っていなかったが、途中、自販機でも買えるだろうと安心しきっていたのが大間違い。まずいな、と思って走り続けていた途中、ひとつだけ見つけた自販機を見て安堵するも、すぐに絶望に変わった。何と、小銭を用意してなかったのだ。しかも財布をみると1万円札しかない!直後から脱水症状がはじまり、意識が朦朧としてくる。そして第七番札所だっただろうか、神社には売店があったことから、そこでやっと水を補給するも、その後、2本の水はまたたく間になくなり、何と、再び脱水症状が悪化。第九番札所を過ぎたころには、足が痙攣し始めた。人生初めての体験だ。そしてその日の目的地となる第十番札所切幡寺に着いた時には、両足がつってしまい、まともに歩ける状況ではなくなっていた。しかもそこで目にした最後の遍路とは、切幡寺の333階段だ!痙攣して言うことが効かなくなった足をひきずり、手すりにしがみついて、その階段を手の力で上って行ったことは、今でも鮮明に覚えている。初日から、すごい洗礼であった。
そんなトラウマもあり、心が癒されるには2か月ほどかかった。そして9月23日、満を持して第2日目の遍路みちにチャレンジすることとなる。予定は第十番切幡寺から第十一番藤井寺を経由して最初の難所となる山を登り、第十二番焼山寺に到達すること。そしてお遍路さんがよく泊まられる徳島県神山町の植村旅館に予約もいれた。そこでくつろぐのを楽しみにしていたのだ。ところが、切幡寺から出発した直後、ありえないことに、左足の筋肉に激痛がはしった。何か自分の体の中でおかしなことがおきている。そう思いつつも、藤井寺までの10㎞が痛みのために走り切れず、途中で断念。すぐそばの鴨島駅から汽車に乗って徳島に戻ることにした。屈辱の時であった。正に、自分の体が遍路を走り切れるような状態でなかったことが、やっとわかり始めた。
その悔しい思いはぬぐいきれず、それからというもの、筋トレの量を増し、今一度、体調を整えることに留意した。そして連休にあわせて10月9日、鴨島駅から第十番藤井寺を経由して山を登り、第十一番焼山寺を越えて、そこから山をくだり、第十六番札所の観音寺まで戻ってくるという無茶な計画をたてた。なぜ無茶をするかというと、理由はただ一つ。前回の遅れを少しでも取り戻すために他ならない。それでも走行距離は43㎞。難所である大きな山を登りつつも、距離としてはフルマラソン程度なので、何とか頑張れると思った。結果は、登山の上り道は快適に進み、あっという間に焼山寺まで辿り着いた。が、その後が問題だった。緩やかな下り坂が続く徳島方面へ向けてのアスファルトの固い道が何故か足にダメージを与えていたのだ。そして再び、2日目で味わったような激痛に見舞われることになる。そして幾度となく道の途中で止まり、ストレッチを繰り返し、かろうじて第十六番観音寺まで到達することができた。今後の流れに不安を残した第3日目であった。
それから第4日目は25㎞、第5日は51㎞を無難にこなすも、足の不調が気になって仕方がなかった。不思議なことに、山を上ったり、緩やかな斜面を上がっていく時は全く痛みが生じたことがない。ところがアスファルトの平らな地面をずっと走っていると、左足の大腿筋、特に骨との付け根が痛くなってくるのだ。歳のせいかとも思い、日々、少しずつトレーニングを重ねるのだが、なぜ、平らな地面を走ると痛くなるのか、良くわかっていなかった。そして第6日目、遂に地獄を見ることになる。
忘れもしない11月13日の遍路ラン第6日目。自分にとっては最難関と思われた徳島の美波町にある第二十三番札所の薬王寺から室戸岬、第二十四番札所の最御崎寺までの78㎞だ。遍路みちはほぼすべてアスファルトの道路。高低差もほとんどないフラット。普通の人なら、いちばん走りやすい道のはずだが、自分にとっては一番、不安が残る環境だった。そして案の定、不安は現実となる。40㎞を越えた所くらいから左足がおかしくなり、50㎞を超えると何故か、麻痺したように固まって動かなくなる症状が出始めた。とはいえ、周囲を見渡すと何もない、というのが室戸岬への遍路みちだ。助けを呼ぶわけにもいかず、何とかして自分で室戸岬まで辿り着くしかないのだ。そこで足が固まるたびに止まり、ストレッチ、屈伸運動をした。すると、何とかまた感覚が戻ってきて、走れるようになることがわかった。ところが最初のうちは一度ストレッチすると、数百メートルは持ちこたえたが、段々と繰り返すうちに、100メートルももたなくってくるのだった。結果として何十回、途中で止まっただろうか。止まってはストレッチと屈伸運動を繰り返し、再び出発して足が麻痺して止まるまで走る。この辛さは言葉では言い尽くせない。しかも足が止まる時、激痛が走るのだ。痛みのあまり、足摺岬への道路上にて、大声をあげてうなることもしばしばあったが、それでも走り続けた。いつかゴールが見えてくると信じてやまなかったからだ。そして確かに、自分の力で室戸岬まで到達することができた。
この事件から、自分の足について、その不具合を徹底して研究することにした。正直何が問題なのか、わかっていなかったのだ。ヒントは、平らな道、固い道路を走っていると、左足の大腿筋に激痛がはしりはじめ、放置しておくと足が固まってしまうということだ。調べていくうち、この症状はマラソンランナーに多い、腸脛靭帯炎であることがわかった。平らな道で膝を曲げる角度が浅い状態が続くと、大腿筋の靭帯が膝の骨とこすられる状態が続き、摩擦ストレスがかかって痛みが発生するのだ。
そこでスポーツ医療の専門医師と相談し、PRPと呼ばれる再生医療を受けることを決断。それも、残りの遍路みちを走り抜けるための決断に他ならない。簡単に言うと、自分の幹細胞を培養して、直接関節内に注射をして投与することにより、傷ついた組織や痛みを改善する試みだ。その治療を受けるだけでなく、大腿筋と臀部の筋肉を鍛えるために、そこに集中した筋トレも日々、取り入れることにした。そのうえで、これまでしたことのない大腿筋のストレッチも導入。この対策が功を奏した結果、恐怖に思われていた四万十から足摺岬までの86㎞を見事にクリア!また、レントゲンやCTを撮って、膝の骨には異常がないことを確認し、膝の痛みはおおよそ加齢によるものと断定し、それはロキソニンなどの鎮痛剤を走る際には飲んで、痛みを和らげることにした。つまり、痛みと疲れさえ我慢すれば、ゴールが見えてくると確信するに至ったのだ。
これらの努力の結果、その後、30日間を費やすはずの予定を、一気に22日間に繰り上げるに至った。何故なら、いつの間にか7-80㎞を走る自信がついてきたからだ。それも平らな道だけでなく、結構厳しい山道を含む遍路みちであっても、むしろ50㎞ではものたりないと思えるまでになった。これも努力の結果かもしれない。確かに60㎞を越えてくると、つらくなる。第15日目の伊予大洲から第45番札所の岩屋寺までの71㎞は標高差もあり、自分の限界を感じた。しかしあの厳しい岩屋寺までの道のりを克服できたことこそ、大きな自信となり、その後の展開においても長距離をこなすことができている。
こうして2024年のゴールデンウィーク、新入社員が石鎚山に登頂している間、自分は伊予三芳から第60番札所となる石鉄山(いしづちさん)の横峰寺を経由して、伊予三島までの77㎞を走る抜けることができた。体は無論、ぼろぼろ、がたがた。その日、夜は徳島で社員との祝賀会。かろうじてすまし顔で参加はしたものの、立っているのがやっとではあったが、そこは根性。やればできる、と信じて進んで行くしかないのが自分の人生だ。そして今日、昨日走ったばかりの5月4日、好天気が続いていることから明日、5月5日、20日目の遍路ランに突入することを思いつき、東京に戻るフライトをドタキャンして備えている。果たして明日、どうなるか。しかもGWの帰り、フライトはすべて満席でもうない。着替えもない。それでも進んでいく。必ず道は開かれてくることを信じて。