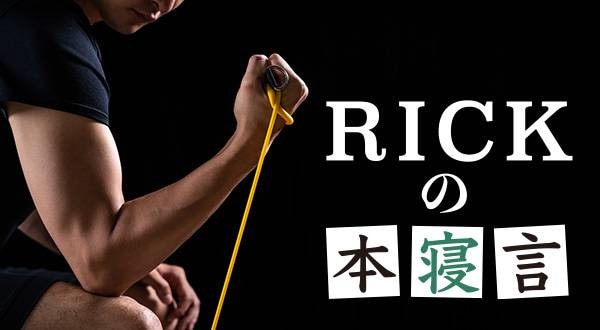2023年からサウンドハウスは、福祉の道にも大きくかじを取りはじめた。一般財団法人サウンドハウスこどものみらい財団を設立し、こどもを支援しているグループに対して、毎月のように会社の利益から寄付することを決めたのだ。その延長線において、財団は単に受領した寄付金を困っている団体をサポートするための支援金として提供するだけでなく、財団が直接関わる事業の手始めとして、特に若年妊婦のために、こどもを生みたくても出産後の養育や周囲との問題で出産をためらう特定妊婦とも言われる女性を支援し、安心してこどもを生むことのできる環境を提供する「みらいはうす熊本」というプロジェクトも始めた。女性が長期間宿泊できる施設の提供をはじめ、そこで働くスタッフすべて、サウンドハウスの財団が面倒をみることになったのだ。また、「さうんどはうしゅ」と命名された純米大吟醸酒の売上を全額、こどもたちのために寄付する、という大胆なプロジェクトも推し進めている。これらをすべて、サウンドハウスから得た利益の一部でまかなっている。
こんなことばかりしていると、周囲の目からすれば、よほどサウンドハウスは儲かっている企業だと思われがちだが、現実は厳しい。音楽業界におけるネット通販での競争は厳しく、特に昨今の三大ECモール同士によるネット上でのポイント合戦の影響を受け、サウンドハウスの業績は、はっきり言って低迷している。会社の利益を図る尺度はさまざまだが、例えば売上に対する経常利益率をみても、どんどんと右肩下がりになっている。つまり、売上が増えてはいても、その金額に対する利益が減り続けているのだ。これは決して良いことではない。そしてここ最近は、赤字すれすれのレベルまで利益が落ち込むことも少なくない。天下のサウンドハウスが何を言っていると言われそうだが、事実だから仕方がない。
ではなぜ、そのような厳しい状況においても寄付を続け、財団を設立してまで毎月支援をしているのだろうか。そんな余裕があれば、社員の給料と賞与をもっと増やせ、というような叫び声が聞こえてきそうだ。サウンドハウスは音楽業界では最も給与ベースを上げてきた会社であると自負しているだけに、何を言われても動じないでいられる。とはいえ、会社の経営者、オーナーとして最低限の弁明なり、説明はしておかなければいけないと考えている。それを理解してもらえるかどうかは、また、次の課題としよう。
必要不可欠なお金の裏表
そもそも、目まぐるしく進化し続ける今日の世の中を生きていくには、お金は大切だ。不可欠と言っても過言ではない。お金がなければ現実的に生活ができないからだ。よって自分も含め、誰もが仕事をして、日々の生活のために稼ぐことは重要だ。それ故、人が生きるということは、仕事をすることと同じなのだ。働かざる者食うべからず!自分の手で得た収入でもって日々の糧を頂くことが、人間に与えられた宿命ともいえる。そしてお金を得ることによって、人々の生活はより豊かになっていく。お金は大事にしなければならない。
でも気を付けなければならないことがある。何故ならお金は神様ではないからだ。しかもあまりにお金のことばかりを考えると、人を狂わせてしまうことになりかねない。実際、世間でおきている痛ましい事件の大半が、金銭がらみのいざこざに原因がある。時にお金は魔物となり、人の命を奪う惨事の引き金になることもあるということを忘れてはいけないのだ。あくまでお金とは、大切な資産として、上手に貯めて使うことにより、本来の価値を見出すことができると心得るべきだ。そこでお金について、じっくりと考えてみたい。
聖書から学ぶお金の真相とは
世界のベストセラーと言われる聖書には、実はお金の話がたくさん書いてある。中でもソロモンの格言集である旧約聖書の箴言は、読むだけでためになる面白い格言の宝庫だ。そこにはお金の話だけでなく、人を狂わす酒、男女関係の落とし穴、権力がらみのトラブルのことなど、さまざまなことが、独特の表現で綴られている。例えば、日本の格言と思われがちな「七転び八起き」という名言は、箴言にそのルーツがあるように思う。「神に従う人は七度倒れても起き上がる」と書かれているからだ。また、女性がいくら美しく着飾っても知性に欠けるならば、「豚が鼻に金の輪を飾っているのと一緒」というような比喩を用いてまで、次から次へと格言が綴られているのが箴言の魅力だ。
その箴言から、お金について5つの大切なポイントが読み取れる。ぜひとも注目してもらいたい。
1.お金持ちは存在し、財産をもつこと自体はOK
世の中にはお金持ちと貧しい人が共存する。これは歴史の常であり、避けられない現実だ。その現状を見据えたうえのことだろう。箴言には
「金持ちと貧乏な人が出会う。主はそのどちらも造られた。」(箴22:2)
と書いてある。金持ちも、貧乏も、どちらも神様がお許しになった現状と考えられる。よって金持ちになること自体、決して悪いことではないことは明白だ。箴言は金持ちの存在を肯定しているからだ。そして箴言の言葉は続く。
「神に従う人の家には多くの蓄えがある(箴15:6)」
「財産は金持ちの砦、自分の彫像のそびえる城壁(箴18:11)」
つまり神を信じる人には貯蓄があり、財産そのものが生活の基盤を支え、生活を豊にすることを是認しているのだ。しかもお金を貯めて財産を増やすことにより、仲間も増えてくることが語られている。
「財産は友の数を増やす(箴19:4)」
それ故、お金を貯えることは悪いことではないことがわかる。むしろ、その財産によってお友達も増え、人生がより豊になると考えられるのだから、なおさらお金は大事だ。よって、一生懸命働き、財産を増やしていくこと自体、良いことのようにも思えてくる。
「勤勉な人はよく計画して利益を得る(箴21:5)」
と書いてあるとおりだ。しっかりと働いて、しっかりと稼ぐ。これが人に与えられた天からの宿命といえる。あたかも頑張って財テクし、しっかりと利益を得ることを推奨しているようにもとれる。
2.財産は消えていくもの
しかしながら、財産は貯めてばかりではいけないようだ。その虜になってもいけない。何故なら箴言は、せっかく貯めた財産であっても、すぐに消え去っていくものであると警鐘を鳴らしている。一生懸命働いて貯蓄し、友だちを一杯作って、いい暮らしをしようといつまでも考えていてはいけない。なぜなら一転して、その財産は消え去ることがあるからだ。聖書は禁じ手のごとく、財産の行方についても忠告している。
「目をそらすや否や、富は消え去る。(箴23:5)」
「財産はとこしえに永らえるものではない(箴27:24)」
つまり、一生懸命に働いて貯めた財産というものは、いつまでも手元に残されるものではなく、いずれ消え去る運命にあるというのだ。しかも、そのスピードが何と、あまりに速い!
「財産は吐く息よりも速く減っていく(箴13:11)」
すると、働いてお金を貯めても意味がないのか、とも思えてしまうが、実はそうではない。その点においてもきちんと箴言は説明をしている
「(財産は)手をもって集めれば増やすことができる(箴13:11)」
つまり、お金とはいずれなくなるものではあるものの、一生懸命自分の手で働いて稼いでいけば、ある程度は増やすことができることから、有効活用できることに違いはないのだ。よって、生活をするために働き、お金を稼いで貯めること自体は、決して悪いことではないと言える。財産を増やせる可能性は残されている。大事なことは、お金の誘惑に溺れないことだ。ふと油断すると消え去っていくのがお金の運命だからだ。たとえ油断しなかったとしても、財産というものはいずれ無くなっていくものと考えた方がよいのだろう。
3.貪欲がいけない
では根本的に何に注意しなければならないのだろうか。働いて得たお金を貯めることは悪いことではなく、むしろそれは勤勉な証ともいえる。よって、しっかりと働いて貯蓄を増やし、生活を安定させることは良いことのようにも思える。その通りなのだろうが、その貯蓄、すなわちそれぞれが蓄積している財産には、とんでもない罠がしかけられているようだ。それが貪欲という、人間をダメにする恐ろしい仕掛けだ。
箴言は明確に注意を促している。これら3つの格言を読めば、富、すなわちお金に対する潜在的な問題が浮かび上がってくる。
「富に依存する者は倒れる。」(箴11:28)
「富を得ようとして労するな、分別をもって、やめておくがよい。」(箴23:4)
「貪欲な者は財産を得ようと焦る。やって来るのが欠乏だとは知らない。」(箴28:22)
箴言が忠告していることは、お金に頼ってはいけないということ。それに執着すると、とんでもないことになりますよ、ということを教えてくれているようだ。お金というものは所詮、無くなるものなので、それを一生懸命貯めようとするのではなく、むしろ働きながら、お金にとらわれることなく、それを自然に蓄積、与えられれば感謝するくらいが望ましいことのように思える。そういう考えに徹すれば、お金に執着しているわけでもないので、たとえお金が消え去ってしまったとしても驚くに値しなくなる。いずれにしてもお金を欲するがあまり貪欲になり、お金のことだけを考えるような生活がいけないのだ。そういう人は金欲しさに焦り、最終的には貧乏になりますよ、と箴言は警告している。この点においては、しっかりと心に受け止めるべきではないだろうか。
4.貧しい人と共に
では、一生懸命働いて貯めたお金はどうするべきなのか。いずれそのお金は無くなってしまうことは格言が教えている。しかも死ぬ時には誰も、その貯蓄したお金を天国に持っていくことができない。ならば自分が生きている間に、お金は有効活用するべきではないのか。そう考えていくと、自ずからお金の使い道が見えてくるのではないだろうか。そこで箴言は、ふたつの格言をもって諭している。
「貧しい人と共に心を低くしている方が、傲慢な者と分捕り物を分け合うよりよい」(箴16:19)
「貧しい人に与える人は欠乏することがない」(箴28:27)
これら2つの格言はとても貴重だ。何故ならお金持ちの貯蓄の話しから、お金がなくなってすっからかんになる危険まで格言を通じて諭された後、その結末として貧しい人達との話に見事に結び付けているからだ。まず基本的な考え方として、お金持ちであるなしに関わらず、不当に得た大金を山分けするような連中と一緒にいるよりは、貧しい人達と共にいることの方がずっとよい、ということをこの格言は教えている。これは自分の心が、何に結びついているか、心の目が何を見ているかという点について指摘している。どういう人達と心が通じ合い、何を求めて生きているのか、ということだ。お金よりも、もっと大切なことがあるということを、格言をとおして教えているのだ。
では何が大事なことなのだろうか。誰に寄り添うべきなのだろうか。そこで貧しい人達、困っている人達に寄り添い、そして必要に応じて自分の持っているものをシェアーする、つまり分け与えることの大切さを格言は告げている。もしお金があれば、そして幸いにも神が財産を持つことを許してくれたのであれば、それをひたすら求めて増やしていくのではなく、貧しい人たちに積極的に与えることが、人としての生きる道であることを示している。しかも困った人達を助けることにより、自分の財産は少なくなるのではなく、むしろ逆に「欠乏することがない」と断言している。
これが神の摂理というものなのだろうか。自分のもっているものを困っている人に与えてしまえば、誰もが自分の財産は少なくなってしまう、ということで悩むはずだ。ところが他人に与えても、財産は少なくなることはなく、むしろ欠乏することがないという確証に満ちた言葉が綴られていることに驚きを隠せない。
これこそ今、サウンドハウスが目指しているところの信念だ。つまり困っているこどもたちを助けるために、与え続ける。そしてひとりでも多くのこどもたちの生活環境が改善されることを心から願う。その働きの結果、サウンドハウスの財産はどんどんと減っていくのではなく、むしろ逆に欠乏することなく、いつまでも栄えているという結果に結び付く。こんな不思議な神の摂理があることを信じてやまない。
最後に人が幸せになる秘訣を3つの格言から学びたい。人間は、いかにして幸せな人生を歩むことができるのか、という究極の課題だ。以下の箴言の言葉に注目してみた。
「財宝を多く持って恐怖のうちにあるよりは、乏しくても主を畏れる方がよい。」(箴15:16)
「貧乏でも、完全な道を歩む人は、二筋の曲がった道を歩む金持ちより幸いだ。」(箴28:6)
「貧しくもせず、金持ちにもせず、わたしのために定められたパンでわたしを養ってください。」(箴30:8)
ここで語られている主とは、ヘブライ語で神を意味する言葉だ。まず、裕福になってもいつも金の事ばかり考えて、夜も心配で寝れないような日々を過ごすくらいなら、お金がなくても、神を信じながら生きて行く方が良い、という教えに注目したい。お金は大事だが、人の心を虜にすることが多く、時には悪の道へと陥れることさえある。よって聖書の言葉は再三ながら、お金に対する警告を発信し続けている。イエスキリストも言われた。「金持ちが天の国に入るのは難しい」と。人は誰も、お金に対して執着せず、心が捕らわれないように気を付ける必要がある。お金には誘惑の力があり、罠になりがちということを覚えておきたい。
実はこれが難しいのだ。誰もが一度お金のありがたさがわかり、それを手にしてしまうと、もっとお金を欲しいと思ってしまう傾向にある。そして気が付かぬ間に、ふと、金儲けのために間違った道に入ってしまうことさえある。よって人道を外れてでも金儲けをして裕福になろうとするような考え方を格言では叱責し、貧しくても人の道として正しいこと、神を信じて互いをいたわる事により、人は幸せになると教えている。
ではどうやって貪欲な思いを断ち切り、お金がある、なしに関わらず、真っすぐな道、正しい道を歩み続けることができるのだろうか。どうしたら、お金に執着せずにいられるのだろうか。今日、ほとんどの日本人は世界的にみてもおよそ豊であり、経済的にも恵まれ、貧しい生活を強いられている人は少なくなった。そのような近代社会において、日本人はお金についてどのように考えるべきなのか、迷ってしまう方もいるはずだ。
その迷いに対する答えが中道の精神と言える。それが3つ目の格言に綴られていた。願わくは、貧しくならないように。なおかつ、金持ちになってお金の虜にもならないようにと。生活をするだけのほどほどのお金があれば、それで十分満足ではないか。そして正しい道を歩ませてください、という祈りの言葉に格言がまとめられている。このような祈りの思いがあればこそ、自らの財産にゆとりがあるならば、それを貧しい人たちのために提供しようという気持ちに自然と導かれるのではないだろうか。
その究極ステージが、マザーテレサが語った「Give until it hurts!」 という言葉に象徴されている。自分の懐が痛むまで、そしてたとえ自分が必要としているものであったとしても、それさえも困っている人、貧しい人のために差し上げることができたら素晴らしいと。有り余るところから寄付をすることは、さほど難しいことではないかもしれない。そして一度寄付を始めると、その行為にも慣れてきて、当たり前のようになってくる。しかし本当の寄付、本当の支援とは、自分が犠牲を払ってでも、他を助けるという思いとそのアクションに尽きることをマザーテレサは世界に発信したのだ。
だからこそ、サウンドハウスは少ししかない利益の中からでも、困っているこどもたちを助けるために慈善のアクションをとる決断をした。創業者として、会社の経営者として、自分が生きている間はサウンドハウスの利益は困っている人たち、こどもたちのために使われることになる。たとえそれで会社が一時的に赤字になったとしても大丈夫なのだ。何故なら、
「貧しい人に与える人は欠乏することがない」
という言葉あるからだ。何もない所から始まったサウンドハウスだからこそ、本当の意味での慈善事業、人助けを目指したい。その道は簡単ではない。こんなことを言っている自分もいつか追い出されるかもしれない。しかし神の言葉は永遠だ。箴言に秘められた素晴らしい格言に聞き入り、心の中に染み付くまで繰り返し学びつつ、実践していくことが大事に思えるこの頃だ。