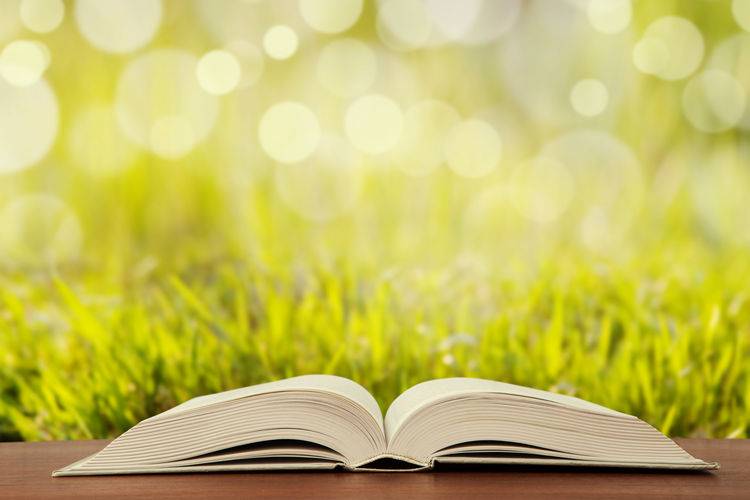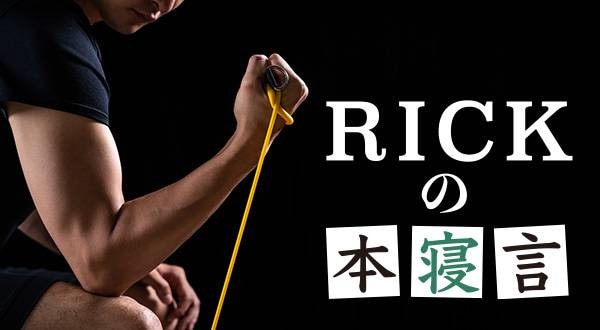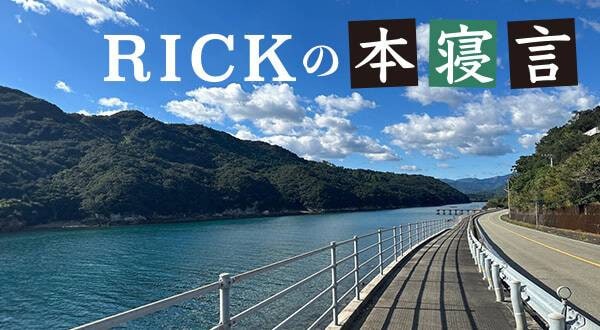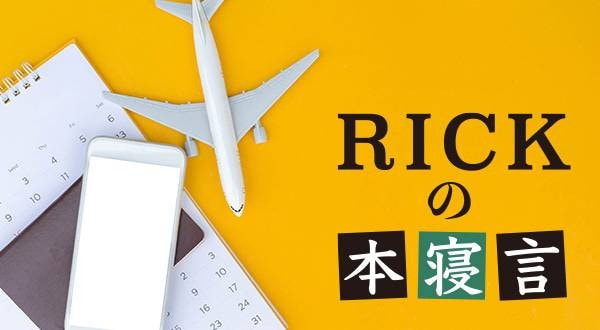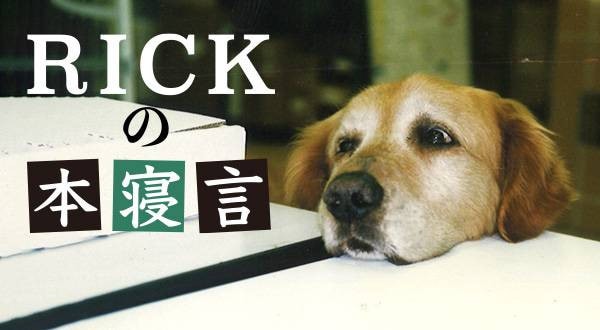社員は正社員だろうがパート社員だろうが、家族のようなものだ。実際、この30年を振り返っても、自分の子どもより社員のフォローを優先したことが幾度となくある。子どもたちと過ごす時間より長い時間をスタッフと一緒に仕事する訳だから、当然のことかもしれない。別段、それを苦にしたことはない。そもそも親があまり構わない方が、子どもたちはたくましく育つと考えている。
理想を語るとするならば、社員は家族同様なのだから、単に会社で時間を一緒に過ごすだけでなく、時には一緒に食事をしたり、旅をしたり、いろいろな経験を共有できてあたり前のはずだ。そして会社のトップにいる経営者としては、自分にしかできないことをしっかりと実行することが望まれる。例えば、仕事に関するさまざまなトピックや世界経済についてまで、長年にわたる経験や学びから教えてあげることができれば嬉しい限りだ。ところが、いくら教えたくても相手が望まないならば、それらはすべて絵に描いた餅のようなものだ。果たして今時の社員は、上司や、会社のトップである自分から学びたいと思うことがあるのか、ふと、気がかりになることがある。
親心は子どもにはなかなか伝わらないと言われるが、教えることだけに限らず、社員との接点を保ち、有意義な時間を過ごす機会がどんどんと減ってきている現実を痛感するこの頃だ。それに輪をかけるように、特に昨今入社してきた社員については、理解に苦しむこと、わからないことが増えてきた。何が問題かと、ふと考えてみた。すると、わからないことが3つ、いや4つあることがわかった。
まずひとつ目のわからないことは、挨拶をしない、できない人が増えてきたことだ。これは一体、どういうことか。社会現象なのだろうか。親の教育の問題か。それとも軽い精神疾患に関わることなのだろうか。ごく普通に朝は、「おはようございます」とみんなが聞こえるように言えばよい。それが言えずにだまっているか、誰にも聞こえないようなボソボソ声でつぶやく。そんなのは挨拶とは言えない。以前ならば、挨拶できない人は早朝から守衛室の前に立たされ、会社に来る人全員に対し、大きな声で「おはようございます」と言うことを、挨拶のトレーニングとしていた。大和の湯の温泉の受付にも入ってもらい、お客様に対して笑顔で「いらっしゃいませ!」と繰り返し挨拶する訓練さえしたものだが。が、今の時代、そのようなトレーニングはパワハラと言われかねない。では、どうやって挨拶することを教育するのかがわからない。
2つ目のわからないこと。それは年商200億円を越える会社のオーナー、会長の立場から社員と話し合いたいことがある時、成長を期待する社員に対して時折こちらから、一緒に食事でもしながら話しましょう、と誘うことがある。少人数の誘いはめったにあることではない。よってわざわざ声をかけていることもあり、喜んで来てくれるかと思うと、最近の社員は7~8割がた断ってくる。理由は用事があるとか、友達と約束しているとか、親の所に行くとか、まあ、これもさまざまだ。しかし今時の常識とは、そんなものなのか。会社の代表者から声をかけられても、行きたくなければスパッとメールで断ってしまう?ソフトバンクの孫社長が20代の社員に声をかけたら、果たして断る人がいるだろうか。千葉銀行の頭取が成田支店のスタッフに、今晩話をしよう、と声をかけたら断る社員がいるだろうか?どうしてもそうは思えない。ということは、この会社だけの問題であり、自分が見下されているのかとも思ってしまうが、もうどうでもいい。この人たちは、天皇陛下から声をかけられても、用事があるので、行きたくないので、すいません、と断るのだろう。それが今風なのかは、わからない。
まだ、わからないことがある。最近の社員は体が弱い。病気がちな人が多い。ちょっとしたことですぐに風邪をひく。コロナに何度もかかる人がいる。精神的にも弱く、夜更かしに慣れていることもあるせいか、軽うつのような人が多く見受けられる。しかるに運動をしないのだ。日々30分の運動をするだけで、体はぐんぐんと健康になる。そして栄養ある食べ物をしっかりといただいていれば、免疫力もつき、ちょっとした病気はみな、防げる。また、運動して、多少日光をあびることにより、うつ病の予防にもなる。そしてご飯がもっと美味しく食べれるだけでなく、夜も寝つきが良くなり、ぐっすりと眠れるようになる。これだけメリットがあるのに、なぜか、運動を嫌がる。早死にしたいのだろうか、車いすの生活でも構わないと思っているのか?それとも単なる無知?家庭教育がいけない?学校教育が悪いのか?それともこれが、今の日本の文化?これもさっぱりわからない。
わからないことが、もうひとつあった。何故か社員には新しいことを吸収して学ぼうという思いがあまり感じられない。世の中、どんどんと変わっている。グローバル化が急速に進み、世界もどんどんと小さく見えてきている。そして今やAIが、そのパワーをお披露目しはじめ、世の中が大きく変わろうとしている。そんな激変する社会にあって、有意義な人生の日々を送り、かつ、しっかりと仕事をこなして、社会にも貢献しようと思うなら、新しい知識、技術をしっかりと吸収していかなければならない。
ところが何故か勉強をしたがらない人が多い。例えば英語の勉強を嫌がる。苦手意識が先行するのか、単なる偏見か、学習障害があるのか、理由はわからない。いずれにしても、これからの社会で活躍し、会社の事業展開において何でもバリバリとこなそうと思うのならば、英語くらいは学んでおかなければ、というのは単なる老婆心か?英語に限らず、昨今の目まぐるしく激変する世情を顧みるならば、社会人として日々、ニュースに耳を傾け、日経デジタル版でも購読して世界経済の状況を把握し、さまざま雑誌、SNS、Webのコンテンツからいろいろな情報を取得しなければ、到底世の中の流れについていけなくなるのは火を見るより明らかだ。しかるに、社員のほとんどはそのシュプレヒコールに耳を傾けてくれない。なぜだろうか。向上心がないのか、今のままで満足しきっているのか、将来のことを危惧しないのか、不思議だ。これもまたわからない。
わからないことばかり、3つ、いや、4つが思い起こされ、書きなぐってみた。が、これもむなしいことだ。なぜなら、いくら書いても現実は変わり様がないからだ。自分の労力が泡と化してしまうのはもったいないことではないか。それでも、せめて記録だけでも残しておこうと筆をとる。自分の言葉には耳を傾けずとも、もしかして神の言葉には、心が留まるかもしれない。果たして自分も含め、蟻や岩狸、いなごや、やもりよりも賢くなれるのだろうか。そう願うばかりだ。
「この地上に小さなものが4つある。それは知恵者中の知恵者だ。
蟻の一族は力はないが、夏の間にパンを備える。
岩狸の一族は強大ではないが、その住みかを岩壁に備えている。
いなごには王はいないが、隊を組んで一斉に出動する。
やもりは手で捕まえられるが、王の宮殿に住んでいる。」(箴言30章)