■これまでのGM音源シリーズ
GM音源01 いにしえのGM音源
GM音源02 ピアノカテゴリー
GM音源03 クロマチック・パーカッション・カテゴリー
GM音源04 オルガン・カテゴリー
GM音源05 ギター・カテゴリー
ベースは、アンサンブルの底辺を支える楽器です。 打ち込みは、生演奏のような細かなニュアンスを出すのが難しいですが、ベースの場合は、そのような要求はあまりなく、一定音量の正確なベタ打ちは逆に求められていることだったりします。 打ち込みに向いている代表的なパートといえるかもしれません。 またベースは基本的に単音で使うため、モノフォニック&ポルタメントONの設定もお勧めです。
033 000 Acoustic Bs. 音域 E1-G3
アコースティックベース。ウッドベース、アップライトベース、コントラバスとも呼ばれています。この音色の奏法は指で弦を弾くピッチカートです。実際の楽器はバイオリンと同じようにフレットがないため、正確な音程を出すのが難しいですが、それゆえに独特な表現が可能となっています。打ち込みでは正確な音程は出せますが、表現力という意味では厳しい面があります。

エレクトリックベース 指弾き
2フィンガーと呼ばれる指弾き奏法の音で、一般的に人差し指と中指を使います。 エレクトリックベースはフェンダー社のジャズベースとプレシジョンベースが二大巨頭として君臨しています。下写真はジャズベースとなります。

034 000 Fingered Bs. 音域 E1-G3
指弾きの標準的な音で、使い勝手のよい音です。
034 001 FingerJ.Bass 音域 E1-G3
上記と同じ指弾きですが、より太い音になってアタックも若干鋭い印象ですが、微妙な差といえます。
035 000 Picked Bass 音域 E1-G3
エレクトリック・ベースをフラットピッキングした音で、アタックが強調されます。フェンダー・プレシジョンベースをピックでゴリゴリ弾くベーシストが多いように思います。プレシジョンベースは世界初のエレクトリック・ベースとなります。1951年に誕生しました。ベースがウッドベースしかなかった時代に、ギターのようにフレットを打ったことで、音程が正確に表現できるようになりました。プレシジョンとは正確という意味ですが、フレットを打ったことを意味しています。1957年以降は、名前はそのままで下写真のようなデザインに変更され、現在に至っています。

036 000 Fretless Bs. 音域 E1-G3
フレットのないエレキベースを指弾きした音です。アタックの立ち上がり遅く、独特な味があります。フレットレスベースを弾くベーシストとしてはジャコ・パストリアスが有名です。下写真は彼のシグネイチャーモデルですが、フレットに見えるラインは指板と違う色の木が埋め込まれているだけで、フレットは打ち込まれていません。

037 000 Slap Bass 1 音域 E1-G3
スラップ奏法は、弦を叩くようにして演奏するスタイルで、よりパーカッシブなアプローチが可能となります。フレットに弦が当たり、アタック音が派手に鳴ることで、本来地味な存在のベースが、目立てる存在になりました。この奏法はジャズ、フュージョン、ファンク等のミュージシャンに好まれています。
038 000 Slap Bass 2 音域 E1-G3
上記と同じスラップ奏法ですが、つぶれたような音が特徴で、この音だけを聴くと使えない印象になりますが、アンサンブルにおいては意外と重宝する音になります。ベースの音はアンサンブルの中で本領を発揮するため、このような逆転現象がよく起こります。
シンセベース1
ここからは、電気的に音を作り出すシンセベースサウンドで、TTS-1のフィルターなどを積極的に使える音色といえます。 またオリジナルモデルが予想できる音色に関しては実機の写真を載せておきます。
039 000 Synth Bass 1 音域 B0-G3
シンセベースの代表は間違いなくミニモーグです。アナログらしい王道モノフォニックベースサウンドは1970年に誕生しましたが、色あせることはなさそうです。TTS-1の音は本物のような図太さはなく、ずいぶんクリアで軽い音になっています。

039 001 SynthBass 101(warm) 音域 B0-G3
1983年に発売されたRoland SH-101の地味だけどしっかりした音のアナログシンセベースの音です。TTS-1シンセベースの中で最も丸い音となります。

Roland SH-101 - Own work, CC-BY-SA 3.0 Unported (Wikipediaより引用)
039 002 Acid Bass(resonance) 音域 B0-G3
これもミニモーグを模したような音で、レゾナンスの効いたシンセベースとなります。ベロシティの値でフィルターの効き具合が変化します。本物のアナログシンセと違い、パラメータがあまりないGM音源の弱点をうまくフォローした音作りといえます。
039 003 Clavi Bass音域 B0-G3
クラビネット系のシンセベースで、明瞭なアタックが特徴です。
039 004 Hammer 音域 B0-G3
エレキベースで、ハマーオンしたときのようなアタックのある音です。もしくはJan Hammerが演奏するミニモーグの音というところでしょうか。音色名の由来が定かではありません。
シンセベース2
全体的に音の輪郭がはっきりしたベースとなっています。
040 000 Synth Bass2 音域 B0-G3
アナログシンセの音と思われますが、039 000とは違った方向になっています。
040 001 Beef FM Bs(attack) 音域 B0-G3
1983年に発売されたデジタルシンセ YAMAHA DX7の音です。 FM音源の重低音ベースサウンドです。プリセットと同じような音がします。サイン波をFM変調したサウンドはアナログシンセでは得られない独特の音を持っています。

040 002 Rubber Bass 音域 B0-G3
ゴムまりのようなシンセベースで魅力があります。
040 003 Attack Pulse 音域 B0-G3
矩形波によるアタックがはっきりしたベースですが、サスティーンは地味なベースらしい音が鳴ります。
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら

















 定番DAWソフトウェア CUBASE
定番DAWソフトウェア CUBASE
 iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”
iZotopeが手がけるオールインワンDAW “Spire”
 DTMに必要な機材
DTMに必要な機材
 UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ
UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ
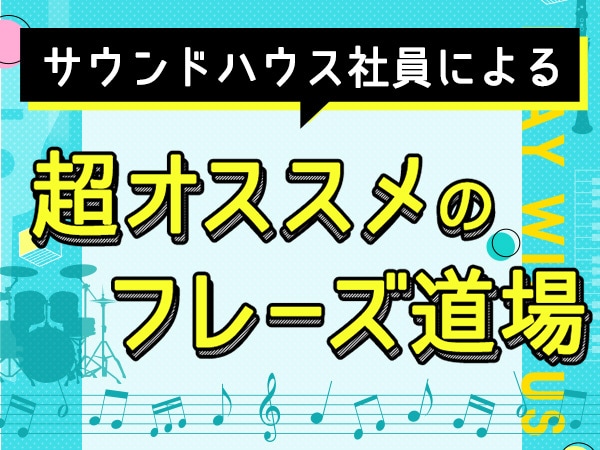 超オススメのフレーズ道場 ベース
超オススメのフレーズ道場 ベース
 DTM・DAW購入ガイド
DTM・DAW購入ガイド















