
「ライブハウス」という日本独特な文化。
そこで日夜奮闘するバンド、ミュージシャン達。
巻き起こる様々な出来事は、簡単にシロクロ付けられないことばかり。
好き。嫌い。楽しい。つまらない。
よう分からんけど、なんか気になる。
実はそもそもあんまし興味ない。
そういった沢山の感覚で溢れ返る大海原。
ライブハウスは港かもしれません。
音楽は素晴らしいものなので続けて欲しい。
バンド活動において「楽しくなくなる」ことを回避するために、ライブハウスで十年以上働きバンド活動も続けている私に(マコトニキョウシュクですが)少しだけアドバイスをさせて下さいね、というのが今回のテーマです。
偏った部分もあるとは思います。その時「わたしはそうは思わない」という感覚だけは大事にしてください。
自分の感覚を大事にするということがこの世界では最も大切です。これは言い切っちゃいましょう。
今日は「ライブ当日の過ごし方」について。
朝起きてどうたらってことじゃなく、もっと実のある話にしようと思います。具体的に。
「リハーサルを意味あるものにして欲しい」
これです。
まずライブ当日までの練習や制作活動にバンドメンバー以外の他者が介入することは少ないと思います。
ただライブ当日になるとお客さんはもちろん、共演者、ハコ(ライブハウスを私たちはこう呼びます)のスタッフなど様々な「他者」が現れます。
その混ざり合いがサイコーな一日を作ることもあれば、思い出したくもない悲惨な夜となることもありますね。
悲惨な夜が続けば誰だって音楽を好きじゃなくなります。
それを回避するために一番手っ取り早いのはたぶん「良いライブをする」ことです。
誤解されないよう言い換えると「自分が納得いくライブをする」ことです。
ライブ当日のリハーサルを意味あるものにして欲しい
自分の納得いくライブのためには納得のいく音が必要です。
言うのが遅くなりましたが、私の仕事は音響です。ハコのPAってやつです。
自分達の音楽に介入してくる「他者」の代表でしょう。
この観点を軸に話を進めます。
サウンドチェック時、多くのPAはこう言いませんか?
「全体でワンコーラスやってみて下さい。」
これは無視していいです。
ワンコーラスだけの演奏で本当にモニタリング(音の分析)が出来ますか?
曲の前半を少し演奏しただけですぐモニター注文せずに、もっと長く演奏した方がいいです。
そのハコの音の出方を感じて下さい。耳を慣れさせてください。
すると本当にモニターしたい音が分かってくる。すると中音の作り方もイメージが湧きやすい。
演奏を止めるな、とでも言いましょうか。
これは実はPA側としても有り難いのです。その演者の音楽に集中する時間が増えるからです。
PAは良い音を作る仕事と思われていますが、「目の前の音楽を理解し解像できる」ことが前提です。
それが結果として「良い音」になるのです。ではPAに自分の音楽を理解させ解像させるためには?
そうです。演奏を止めてはならないのです。
時間が許すなら、気持ち良くなってダラダラと演奏し続けてもいいです。
そうなった場合リハーサルはその気持ち良さの確認だと思ってください。
本番はそこにお客さんもいるのです。
もっと気持ちよくなって、きっと「良いライブ」ができると思います。
細かいことを気にしないのなら、リハーサルはそんなもので良いのです。
もう少し真面目に耳を使いたい人。
上述したように、まずはその場の出音を味わい、耳を慣れさせることが重要です。
今日の自分の音はどんな調子だろうか。
その空間にどんな風に響いているか。
冷たい感じ、暖かい感じ、とかでも素敵だと思います。
とにかくその日の出音の感想を言語化できるようになりましょう。
音は空気がないと成り立ちません。
「音を聴く」とは、「空間を感じる」に同義です。
温泉に浸かって思わず溜息が漏れる感じと似ています。
浸かった次の瞬間すぐに湯から上がる人はいないと思います。
緊張のほぐれを意識し、心身のリラックスを味わい
壁の絵や、露天ならその庭模様に目をやるでしょう。
これから自分はこうすればもっと気持ち良くなれるとイメージが湧いてきませんか。きませんね。
話を戻します。
バンドの場合、自分の音よりメンバーが出す音を聴くようにしましょう。
自分の音ばかり気になって不安になる気持ちはよく分かりますが
じつは仲間の音にこそ不安を消し去るヒントがあります。
ドラマーが煮えたぎるやる気や極度の緊張でいつもより力任せにバシャバシャと叩いてしまってないか。
そもそもこのハコのドラムセットはいつも練習するスタジオのものと比べてどうだろう。
いや待てよ、もしかしてステージの床や客席に反響してこんな聴こえ方がしてるのかな。
いやいや、あいつはやっぱりいつも通り最高なドラムを叩いてくれてるな。じゃあこの余計な低音感は俺のベースのせいかも....
お?ベースが落ち着いてくれたから俺のギターが聴こえてきたぜ。ボリューム上げようと思ってたけど、一旦このままやるか~。
わーい。歌いやすいからもっともっと上手に歌える気がする~。
うんうん、やっぱり良い歌歌うな~うちのボーカルは。よし、楽しくなってきた。
ドラムはキット丸ごと持ち込まない限り大幅な調整が効かない楽器なので、そのハコでの音作りの指針に成りやすいと言われます。
ドラムだけでも注意して聴くと、そこから方程式のように楽器の音量バランスが整ってきたりします。
最初のワンコーラスで何かの音が小さくて聴こえなくても、曲が進むにつれ静かなセクションではその小さかった音も案外に聴こえて演奏に支障は無いと思えることも多いです。
モニターに余計な注文をしなくて済みます。
余計な注文でパツパツになったモニターはアンサンブルやダイナミクスの邪魔をしてくることもあります。
客席にいるお客さんにも「返し過ぎ」のモニターは意外と聴こえていて違和感のある外音になってしまったり......
ハウリングに関してもそうです。
ハウリングが起こったからといってバンドは演奏を止めてはいけません。
PAはハウリングを決して聴き逃しません。
どのマイクがどう干渉してハウリングを起こしたのか、あなた達の演奏の中に答えを探します。
PAを助けてあげるくらいの心持ちで、ハウリングを恐れないでください。
意味のあるリハーサルになったとして、ギタリストやベーシストはアンプやエフェクターのツマミを決して写真に撮らないで下さい。
確かに良い音、良いバランス、バンドの音は整いました。でもそれはリハーサルでのこと。
音は一分一秒変わり続ける生き物です。飼いならせないものとして認識しましょう。
なにより写真に撮ったアンプのツマミはあなたの「音を考える力」を失わせます。
魚を与えてもらうか、釣り方を教えてもらうか、です。
その時の良い音はその時だけのもので、本番はあらゆる状況起因により写真通りのツマミが正しいとは限らないのです。
前回のスタジオで作ったツマミの写真をそのままやってみる、なんてもっての他です。
厄介なことに同じアンプでも個体差は相当なものなのです。でもその厄介さが可愛いのです。
なによりドラムやボーカル、肉体で音を出していく彼らがリハーサルや練習と全く同じテンションで演奏する訳がありません。
その流動性をバンドで楽しみましょう。生き物である音楽、バンドには、決められたことなんて何一つないのです。
大切なことなのでもう一度言います。
写真より自分の耳を信じてください。耳で覚えてください。
普段の練習から音作りに意識を持つようにすると耳は必ず育ちます。
耳が良くなると冗談ではなく音楽の楽しさが何倍にもなります。
なによりこんな説教じみたアドバイスを読まずに済みます。
色々と好き勝手書きましたが、素晴らしい演奏を目指すには演奏を続けなければならないという単純明快な構造だと私は考えます。
音楽は言葉で説明しても届くところに届きません。
演奏を続ける。
すなわち音楽を好きでい続ける。楽器を練習し続ける。考え続ける。
それらが意味のある時間である限り、それは少しの苦痛と大いなる喜びに満ち溢れ音楽人生を歩む私たちを魅了し続けてくれるでしょう。
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら
















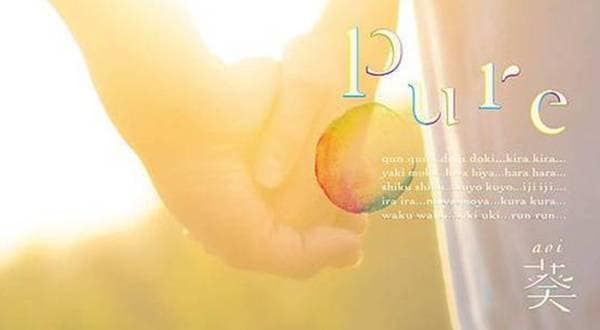
 ベーススタートガイド
ベーススタートガイド
 キーボードスタートガイド
キーボードスタートガイド
 ギタースタートガイド
ギタースタートガイド
 簡易PAセットとは
簡易PAセットとは
 ライブをしよう!
ライブをしよう!
 PAシステム講座
PAシステム講座


















