前回の鍵盤狂漂流記はサウンドハウスさんより購入したコルグのKingKORG NEOのボコーダー部分のリポートとボコーダー周辺情報、ボコーダーを使ったアルバムなどをリポートしました。
今回はコルグが過去にリリースし、私が所有していたウェーブステーションとそれらのレガシーを生かした新製品への展開などを含め、KingKORG NEOのシンセサイザー情報を書いていきたいと思います。

KingKORG NEO(写真上部)下はヤマハYC61、両方とも私物
KORG ( コルグ ) / King KORG NEO バーチャルアナログシンセ
■ KingKORG NEOとは
KingKORG NEOはコルグから発売されたバーチャル・アナログシンセサイザーであり、2013年にコルグからリリースされた「KingKORG」のリニューアル版です。リニューアル版とはいえ以前よりも鍵盤数は減り、金額も下がりました。躯体はプラスチック部分が増え、3.1kgと軽くなりました。
コルグはwavestate mkⅡやmodwave mkⅡ、op six mkⅡといったフラッグシップ機とは別に比較的廉価版であるデジタル3機種を発売しています。
KORG ( コルグ ) / wavestate mk II シンセサイザー
KORG ( コルグ ) / modwave mk II ウエーブテーブル・シンセサイザー
KORG ( コルグ ) / opsix mk II オルタードFMシンセサイザー
これらのシンセサイザーは過去にコルグが発売したシンセサイザーの名機と言われる遺産を踏襲し、さらにそれをバージョンアップした形の機材です。
KingKORG NEOもその例外ではありません。デジタル3機種と同じ仲間と言っても差し障りないはずです。
これらの機種はミニ鍵盤ではない37鍵盤で4機種共、同じ躯体を使っています。写真からも分かる通り、正方形に近い形状です。鍵盤左側にピッチベンドとモジュレーションホイールがなく、パネル左下にホイールや同等の操作ができるジョイスティックが付いているためです。
コストダウンを図るため、電源部分は本体内には入れず、ACアダプターによる電源供給です。本体が軽いのはこんなところにも要因があります。
■ コルグの戦略の元となったシンセサイザー
過去にコルグの名機であったウェーブステーションはwavestate mkⅡとなって現在に蘇りました。modwave mkⅡもDW-6000、8000という過去に隆盛を極めたシンセサイザーをバージョンアップしたものです。op six mkⅡはY社が1980年代に世界中で大ブレイクさせたDX7、FM音源シンセサイザーのノウハウをベースに作られています。
コルグはそういった名機のノウハウをベースにバージョンアップさせたシンセサイザーを廉価で発売しています。
そういう意味では新たにシンセサイザーと対峙をするユーザーにとってはかなりお得な機材でもあり、シンサイザーの名機にプラスアルファされた楽器が安価で手に入るのはとても幸せなことだと思います。
コルグのレガシーシンセ、ウェーブステーション
私は以前、wavestate mkⅡの元となったコルグのウェーブステーションというシンセサイザーを所有していました。

コルグ ウェーブステーション(Wikipediaより引用)
ウェーブステーションはサンプリングされたPCM波形を連結し、波形を生成するという新しい発想のシンセサイザーでした。
シーケンシャルがリリースした名機、プロフィットVSというシンセサイザーを開発したスタッフが関わり、ベクトル・シンセシスというシステムを作り上げしました。
現在もプロフィットVSの音源をコンパクトにまとめた「PRO VS MINI」という機材がB社から発売されていますね。私も欲しいなと思っています。
ウェーブステーションはその斬新さからユーザーの支持を受け、世界中に広がりました。音作りは少し面倒という側面がありましたが、今までにはない音を作ることができました。また、SE的な音も素晴らしかったことからTV番組の音楽制作にも使用しました。
そんなシンセサイザーを更に進化させたwavestate mkⅡが発売され、私は購入しました。
ウェーブステーションは良い楽器というイメージがあったからです。
しかし、wavestate mkⅡはアナログ人間の私にとって複雑すぎました。これを使いこなせる方なら当時のウェーブステーションは20万円を超えていたので、さらにバージョンアップされた楽器が7万円程で購入できるのは夢のようなお話です。
wavestate mkⅡの階層は深く、複雑なのでそれに対するスキルのある方は是非、挑戦することをおすすめします。
次はいよいよKingKORG NEOの体感リポートです
■ KingKORG NEOは先進的バーチャル・アナログシンセだった!
最初に楽器を持ち上げた感覚は「軽い」。この一言でした。電源はACアダプターから供給されるタイプ。廉価版のシンセサイザーであり、コストダウンのためには仕方ないですね。しかし、この軽さは驚異的で練習でスタジオに持っていくにはとても便利です。鍵盤は37鍵盤。私はもう少し高価な鍵盤が付いていればいいと思います。元々コルグは国内製の鍵盤をプロローグなど、フラッグシップシンセサイザーに使っています。この鍵盤はとても素晴らしいのでぜひ、この鍵盤バージョンも出してほしいと思います。
それではプリセットの音を出してみます。

KingKORG NEOのパネル部分(私物)
プリセットはいかにもバーチャル・アナログシンセサイザーといった音が意識的に並んでいる印象を受けます。
写真からも分かるようにKingKORG NEOのプリセットはシンセ、リード、ベースなどのカテゴリー別に分かれており、カテゴリーを選択して液晶画面の右側にあるダイヤルを回し、音色を選択します。音の太さを売りにしているこのシンセサイザーですから、液晶パネルに記されたミニモーグのリード音をシミュレートしたと思われるMini Leadを選択してみます。
出音はまさにミニモーグを意識した音でした。以前、ヤマハのYC61を私がリポートした際、グレッグ・マティソンのミニモーグのリード音をシミュレートした音がありました。まさにそんな音がプリセットされていました。KingKORG NEOの音はオシレーターから作られた音、YC61はFM音源シンセから作った音なのでどちらがいいとは言えません。もちろん、出音の違いはあります。グレッグ・マティソンのミニモーグのリードはシーケンシャルのTAKE5でもトライしてみました。一番近かったのはTAKE5でした。アナログシンセサイザーですから当然と言えば当然です。アナログ独特の暖かさとふくよかさがあります。FM音源でもここまで近くなるのかという程、近い音でした。
KingKORG NEOも近い音なのですが、どこか音が鋭い感じがします。VCFでカット・オフをコントロールするものの鋭い感じは消えません。最終的には元々のオシレーターの質やDAコンバーターの質にも関わるものかとも思います。もう少しこの辺りのコントロールには私自身の勉強や習熟が必要なのだと思います。
バーチャル・アナログシンセサイザーKingKORG NEOはアナログライクな音が得意分野であると感じるプリセットの内容でした。
しかし、バーチャル・アナログとはいってもそれだけではなく、アナログでは出すことのできないベル系の音もかなり充実していました。おまけにボコーダーも付いています。この価格でこれだけの音がでるのなら十分に使えるシンセサイザーだと思います。
次回は実際にKingKORG NEOの詳しい細部までの機能とそれにまつわる音作りをリポートしていきたいと考えております。乞うご期待。
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら
















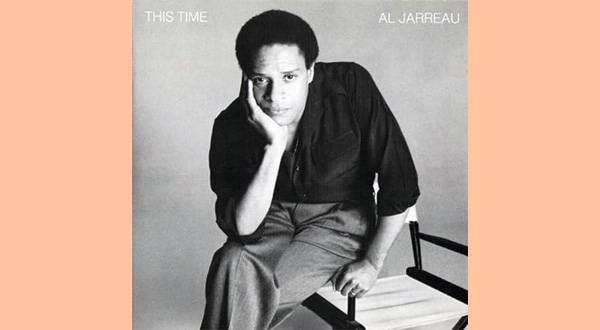

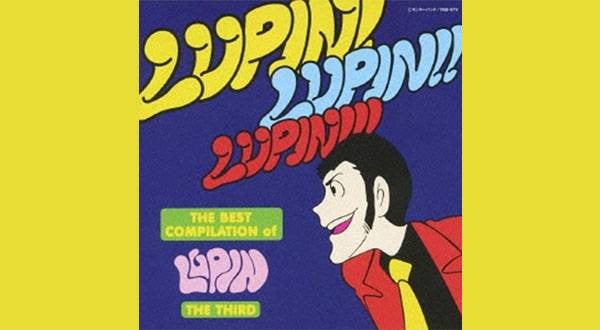


 Sennheiser ボーカルに最適なマイクの選び方
Sennheiser ボーカルに最適なマイクの選び方
 スピーカーの定番 Classic Proのおすすめモデル
スピーカーの定番 Classic Proのおすすめモデル
 初心者向けUSBマイクの選び方
初心者向けUSBマイクの選び方
 BOSS ボーカル・エフェクターのススメ
BOSS ボーカル・エフェクターのススメ
 ワンランク上のボーカルマイク選び
ワンランク上のボーカルマイク選び















