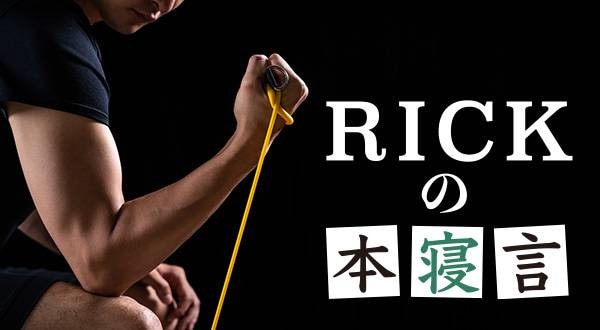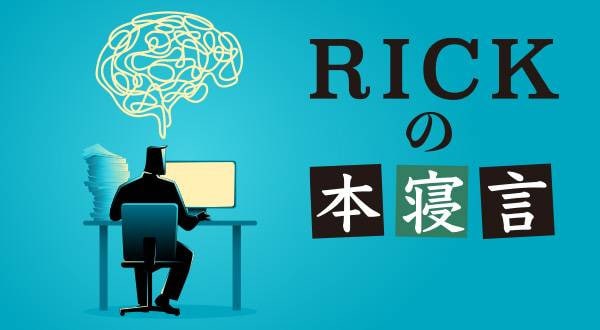世界中を旅して思うこと、それは日本の食生活が、紛れもなく世界一であるということだ。その素晴らしさを知らない日本人が多いようであり、何でも当たり前のことと思っているようだが、もしそうだとしたら残念だ。何故なら、日本の食文化に感謝する機会を失うことになりかねないからだ。たしかに井の中の蛙のように世界の大海を知ることなく、日本だけの生活環境しか知らなければ、それが当たり前と思っても仕方ないのはわかる。それでも知ってほしい。日本の食生活は、世界で一番恵まれているのだと。
日本人が優れた食文化を日常、当たり前のように満喫できる理由は簡単だ。それは日本の地理と自然の環境に起因する。食文化の発展に一番大事な要素は、種類が豊富であることと、食材としての鮮度が高いことだ。具体的には、海の幸、山の幸、野の幸、川の幸を指し、そのいずれにも食材の種類が豊富にあり、しかも新鮮で美味しいことが要となる。日本の土壌は、それら食の幸を現実のものとし、世界でも類を見ない優れた自然環境を誇る。よって、そこから採れる食材の恵は、桁外れに素晴らしい。
特筆すべきは何と言っても海の幸であろう。日本は三千以上の島々から成る島国であり、すべて海に囲まれている。これほどまで海岸線に恵まれている国は、世界でも珍しい。フィリピンやインドネシアなど、東南アジアの国々の中にも、日本と同じような島国が存在する。しかしながら際立って違う点が2つある。まず、海温の差だ。赤道に近い東南アジアの国々周辺の海は、海温が高く、食するにふさわしい大きい魚がなかなか育たない。よって島々の周辺は、熱帯魚のような小さい魚が多く、よほど沖合に出ない限り、なかなか美味しい魚に出会えない。それに比べ、日本列島は北緯20度から45度まで南北広範囲に位置し、暖かい琉球諸島から涼しい北方領土の方まで、島々が広がっている。よって、さまざまな魚が随所で生育するのに最適な自然環境を提供している。
その適度な海温に加え、日本列島の臨海には日本海流とも呼ばれる黒潮が流れている。遠い南方から日本に向かって北方に流れてくる潮流は、多くの魚類を私たちの元へと運んでくることになる。こうして一年中、途切れなく流れている潮流が存在するが故に、多くの魚が自然に運ばれてくるという海の幸にあずかれる国は、世界でも類がない。しかも、この潮流は四国からは二手に分かれ、太平洋側から紀伊水道、淡路島方面へ流れるだけでなく、九州と四国の間から瀬戸内海へと流れる海流も淡路島の方まで流れつき、そこで元の海流とぶつかり渦潮の現象となることで有名だ。双方の海流が注ぎ込まれる終点であり、それが瀬戸内海で渦となることから、必然的にそこに多くの魚が集まることになる。また、日本海流は九州の西側から日本海にも注がれ、対馬海流となって、日本海側にも多くの海の幸をもたらす原動力となっている。嬉しい限りだ。
これまで自分が食した日本の海の幸で際立った事例を思い起こしてみた。筆頭に上がるのが、日本海側の京都府、宮津湾で採れたばかりのとり貝だ。俗に言う「生とり貝」のことだ。宿のマスターによると、天然のとり貝はほとんど採れなくなってきていることから、禁漁の期間が長く決められ、毎年、とり貝の漁ができる期間は6月の数週間しかないとのことだ。そしてたまたま、自分が宿泊するその当日、最高のとり貝が手に入ったとのこと。もちろん値段はとても高いけど、「誰もが食べたいと言ってうちの旅館に泊まりにきますけど、めったに手に入れることができないことから、みなさん食べられないんですよ。お客様は食べられたらラッキーですよ!」、と言う。騙されたと思って、お願いすることにした。
すると料理長でもある店主が、部屋に小さい炭火のコンロと持ってきて、自分の目の前で見たこともない大きなとり貝を手にとってみせてくれた。「これ、生きているんですよ」、と言って貝を軽くたたくと、10㎝くらいは出てきただろうか。大きな舌のような形をしたとり貝が、にょきっと貝の間からはみ出してきた。これまで自分の知っているとり貝というものは、すし屋でいただく、どちらかというと、うすっぺらい貝だ。色は白をベースに茶色、黒色がまみれており、ちょっとした歯ごたえはあるものの、イカのように少しねちっこいところがある。このような、すし屋で食べる生とり貝が、自分の知識と経験の限界だった。その常識を覆す事態が、目の前でおきることになる。
何しろとり貝がでかい。そして分厚いのだ。ぱっと見、3㎝くらいの厚さはあっただろうか。それを料理長が貝殻から鋭い手さばきで切り出して、バタフライ、すなわち包丁を真ん中にさっと入れて、貝を開いたのだ。何と大きいとり貝に見えたこと!色は全体が白かった。それも想定外。そしてすぐに料理長は、そのとり貝を、炭火焼きのグリルの上に置いた。そして両面をあぶった時間はおよそ1分程度だっただろうか。
すると驚いたことに、自分の目の前でとり貝がみるみる小さくなって、しぼんでいくのだった。おそらく火にあぶられて、熱かったのだろう。痛かったかな、ごめんなさい。そしてもう一つ、驚いたことは、グリルにのせられた瞬間、色が変わり、黒とグレーが入り混じった、すし屋のとり貝で見るような色になったのだ。料理長曰く、とり貝は火が入ると、すぐに変色するとのこと。そしてグリルから箸で取りあげたとり貝を口に入れることができるほどの大きさに切り、皿の上にのせて出してくれた。
料理長は、「今が美味しい時なので、すぐに食べください!」と言われた。その言葉を信じて、軽くあぶられたばかりのとり貝を箸でとり、口に入れてみた。まず、その分厚さに驚いた。あぶられたことにより収縮はしているのだが、それでも厚さは2㎝ほどはあったと思う。柔らかいステーキを噛むような感じで、ほおばることができた。次の驚きは、その歯ごたえだ。イカのようにねちっこく嚙まなければならないかと思いきや、全く違った。どちらかというとホタテと、みる貝の中間のような柔らかさで、心地よく歯ごたえが伝わってくるのだ。これには感動した。無論、その味はというと、貝でありながら、何と甘く感じたことか。これがほんまもんの生のとり貝か!と感動を抑えきれず、「美味しい!」と絶句していた自分がそこにいた。
なんか、とり貝のことを思い返して書いていると、それだけでこの原稿が終わりそうなくらい、思い入れがあったことが、今もって身に染みてわかる。たった一つの食材の話だが、世界中で食べられる所は日本しかないし、その奇跡の一食に出会えただけでも、感動の極みと言うしかない。
その他、海の幸の極めとしては、北海道の離島である礼文島でとれた雲丹も素晴らしく美味しかった。また、四国愛媛県の最西端、佐田岬の漁港近くでいただいた、一本釣りで捕れたばかりの鯖を、生で美味しく食べられたことも嬉しい体験だった。こうして考えると、人生の道のりの中で味わってきた海の幸の体験談は、枚挙に暇がない。あまりに多くの恵を味わうことができた人生の旅路であっただけに、感謝がつきない。海の幸だけをとってみても、日本は世界一、素晴らしい国だ。そして今日は、宮城県の女川にいる。きっと今晩も、美味しい魚を食べることができるのかと思うと、仕事にも熱が入る。