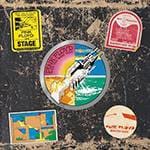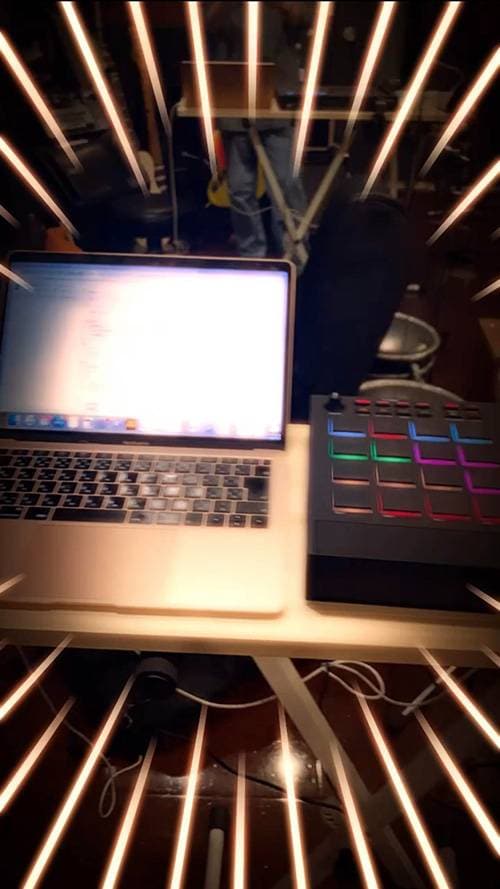
こんにちは!
ライブハウス京都GROWLY制作のイトウです!
日々、京都をはじめ関西拠点のミュージシャンの音楽ライフをサポートするお仕事をしています。
京都GROWLYは4月で12周年!
二条駅から徒歩3分という好立地に、ライブハウスと音楽スタジオ、ギャラリーを併設した音楽ビルを運営しています。
特に3Fのギャラリーは不定期開催ですが基本入場無料ですので、お近くの方も観光でお越しの方も、ぜひ一度ご来店ください!
さて、今回はミュージシャンへ向けたライブでのノウハウの記事をポストしてみようと思います。バンド、ソロ、ユニット、どのような形態でも活かせる情報になっていると思います。
テーマは【同期音源】
メンバーが演奏するだけでなく、あらかじめDTMで作成した音源や別途レコーディングした音源と生演奏をシンクロさせることで、表現の幅がより豊かになります。
DTMやデジタルツールの普及とともに、かなりの数のミュージシャンが同期音源を導入しており、フェスやアリーナクラスのミュージシャンも多く使用しています。
メンバーが4人だけなのにストリングスが鳴っていたり、多重コーラスが鳴っていたり、というのは同期音源を使用しているライブになります。
今回は同期音源の中でも、「複数の別個の音源を」「別個でコントロールして出力したい」という、なんとも贅沢なシチュエーションにお答えする記事を書いてみようと思います。
同期音源の出力システムについては、大まかに2通りに分かれます。
- ① モノラルあるいはステレオ(2mix)に全ての音源をまとめてPAへ出力する
- ② 2種類以上の音源をモノラルあるいはステレオとしてPAに別個に出力し、別個にコントロールしてもらう
①の場合は、かなり簡易的な機材のみで完結できます。
よくあるのは「MTRを使用する」「PC接続で2out機能搭載のオーディオインターフェースを使用する」かと思います。
<MTRの商品例>
ZOOM ( ズーム ) / R12 MultiTrak マルチトラックレコーダー
<オーディオインターフェースの商品例>
TASCAM ( タスカム ) / US-2x2HR オーディオインターフェイス
メリットとしては
- 操作的にも簡単に導入できる。
- 必要な機材も安価なものが多い。
- PA側の受け取る回線も少ないのでセッティングがスムーズ。
デメリットとしては
- 1回線ないし2回線に使いたい全ての音源をまとめる必要があるので、自分でmix処理しておく必要がある。
- (コーラスだけ、シンセリードだけ、といったように使う音源数自体が少ない場合は問題なし)
- 特に「リズム」「リード」「コーラス」のように異なる種類の楽器が含まれる場合、会場によって”オイシイ処理”が違うため、1回線ないし2回線に同梱されることでオイシイ部分を妥協せざるを得ない。
これらのデメリットを解消するためには、
「複数回線(3回線以上)をそれぞれ別個で出力できる機能に対応したMTR/インターフェースを使用する」ことで解決します。
<マルチトラック対応のインターフェースの商品例>
私も実際にこの「BEHRINGER / UMC1820」をライブで使用しています。
機能説明欄にもある「8in/8out」という部分が”マルチトラック”という機能にあたります。
ライブでは「8out」の部分が重宝します。
すなわち、8種類の別個の音源をそれぞれ8本の回線を使ってPAに出力できるのです。
例えば
①②:レイヤー系シンセ(stereo)
③④:ハイハットやリズム系シンセ(stereo)
⑤:エレドラのキックだけ
⑥:リード
⑦:コーラス
⑧:シンセベース(ベースアンプへリアンプ&DIへ送り)
といったような送り方でオケをPAへ送ります。
特に私が重宝を感じるのは「キック」「ベース」を単体で送れること。
低音楽器は会場によってオイシイ音色がかなり異なるため、ミュージシャン側でバランスや音色を決めすぎずになるべくナチュラルな音色でPAへ送り、あとはお任せしてしまう!
その方が良い結果を得られることが多いと感じています。
あとは、入念なリハーサルを行っていただくこと。
PAに委ねる音が増える分、PAスタッフとよくコミュニケーションをとり、なんどもテストし、ご自身が作った素晴らしい音楽がイメージ通りに鳴っているかを確認していただくことが重要だと思います。
ライブのリハーサルについては、弊社内田が先日投稿した記事も是非併せてご一読くださいませ。
おわりに
このようなデジタルツールの発展と普及により、少人数や一人で表現できる音楽が無限に広がっています。宅録で音源を制作するだけでなく、ぜひともライブで披露することに挑戦してみていただけたら嬉しいなと思います!
関西のミュージシャンの皆さま、GROWLYでお待ちしております!
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら















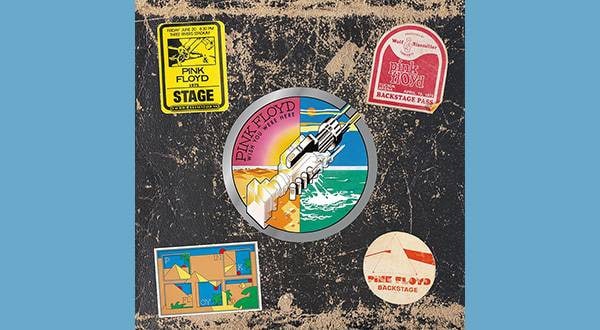







 厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集
厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集
 ドラム音源に最適なMIDIパッド・コントローラー
ドラム音源に最適なMIDIパッド・コントローラー
 機能で選ぶ オーディオインターフェイス
機能で選ぶ オーディオインターフェイス
 UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ
UR-RT4 ソフト音源やループ素材をリアンプ
 TASCAMオーディオインターフェイス USシリーズ比較表
TASCAMオーディオインターフェイス USシリーズ比較表
 TASCAMマルチトラックレコーダー 比較表
TASCAMマルチトラックレコーダー 比較表