■ オーバーハイムという伝説ブランド
鍵盤狂漂流記の中でその名は何度か出ているシンセサイザーブランド、オーバーハイム。今回は私が購入したオーバーハイムの新製品TEO-5のリポートです。
私はシンセサイザーフリークなので多くのシンセサイザーをこれまでに購入してきましたが、最終的に行きつくところはアナログ・シンセサイザーです。音を作る面白さがパネルから直接伝わってきます。これはアナログ・シンセサイザーの醍醐味です。
アナログ・シンセサイザーといえばモノフォニック・シンセサイザーではミニモーグ、ポリフォニック・シンセサイザーではシーケンシャルのプロフィット5かオーバーハイムのOB-X8(現段階では)かモーグのミューズ辺りです。
最終的にアナログ・シンセサイザーの良し悪しはオシレーター(発振器)とフィルターでほぼ決まります。そういう意味でこの3つのブランドは鉄板であると私は考えています。
先日、渋谷の楽器店で6月初頭にリリースされるモーグのメッセンジャーという新製品を弾いてみましたが、その音の太さに驚きました。モノフォニックなのですが、メッセンジャーの出音には言葉を失う程の説得力がありました。私はミニモーグを所有したことが無いので多くはコメントできませんが、ミニモーグのベース音などは今も多くのミュージシャンから圧倒的支持を受けています。メッセンジャーはそのミニモーグの遺伝子を受け継いだのか出音の太さは圧倒的でした。モーグの底力を垣間見る思いがしました。
さて、オーバーハイムの話です。ウェザー・リポートの名曲「バードランド」のイントロで聴けるあのぶっとい音はオーバーハイムの専売特許です。ヴァン・ヘイレンの名曲「ジャンプ」冒頭のあのシンセサイザーもオーバーハイム。あんなに太くてコシがあって、粘り付くような中低音域の凄まじさはオーバーハイムでなければ出すことはできません。
勿論、プロフィット5の音も凄いのですが「野太さ」からいえば、オーバーハイムに軍配が上がります。
私にとって音の太さはポリフォニック・シンセサイザーの基準において重要な要素です。過去にオーバーハイムのエクスパンダーを所有していたことから「ポリシンセの理想的な音はオーバーハイムだ!」という概念ができあがっていました。
そこに現れたのがTEO-5でした。

Oberheim Xpander analog synthesizer, CC BY-SA 3.0 (Wikipediaより引用)
■ TAKE-5との最大の操作感の違いは?
SEQUENTIAL(Dave Smith Instruments) ( シーケンシャル ) / Take 5
このオーバーハイムTEO-5はシーケンシャルとのコラボレーションによって製作されています。
TEO-5のサイズはシーケンシャルTAKE-5と全く同じサイズ。37Keyでピッチベンド・ホリール、モジュレーション・ホイールも鍵盤横にはないため、とってもコンパクトです。
重量はTAKE-5が7,7キロに対し、TEO-5は100グラム重い7,8キロです。実際、持った印象はそれ以上の重さを感じます。
つまみ、ノブは少し違っています。TAKE-5のノブはノブ自体にゴム状の加工が施されていてノブを指でつまんで回転させる際には滑ることがなく使いやすいです。
オーバーハイムTEO-5は黒いプラスチック製のノブです。この仕様は以前にリリースされた OB-6 と同様のノブが使われています。
TEO-5、TAKE-5共、多彩なモジュレーション機能があるため、アマウントなどの数値を0から100以上までノブを回して入力する場合があります。ノブをかなり回転させる必要があるのです。そうなると右手で鍵盤の音を確認しながら左指だけで(その逆もあります)ノブを回転させるには中指1本でノブの側面を指で滑らせ回転させる必要がでてきます。その時にゴム状の加工がノブに施されたTAKE-5は、指1本でも指が滑らずに回転させることができるので操作が容易です。
一方、TEO-5はプラスチック製ノブでそれほど沢山のくぼみがないため、どうしても指1本だと滑りやすく、回転させにくいのです。この様なノブでの入力シーンは沢山あるので操作感としてはTAKE-5に軍配が上がります。

TEO-5のプラスチック・ノブ

ゴム状の加工がされたTAKE-5のノブ
■ 小さくてもヤッパリ…オーバーハイム!!
肝心の音は流石のオーバーハイム!そう、あの音が出ます。過去に所有したエクスパンダーの音とは比較しようがありませんが(既に売却)、記憶をたどるとエクスパンダーはもっとモコっとしていて角がなく、音に付帯している空気の量が多い気がします。
一方、TEO-5はエクスパンダーの音をより現代的にしたシャープな感じを受けます。
音自体がエクスパンダーよりもソリッド(高密度)になっているというイメージです。音はまさしくオーバーハイムです。あの音です。
■ グレッグ・マティソン・プロジェクトのミニモーグもシミュレート!
私は所属するバンドで「グレッグ・マティソン・プロジェクト」の曲を演奏しています。このアルバムは80年代のライブの名盤といわれ、ロサンゼルスのライブハウス「ベイクドポテト」でのセッションが記録されています。メンバーはキーボードがグレッグ・マティソン、ギターがスティーブ・ルカサー、ドラムがジェフ・ポーカロ、ベースがロバート・ポップス・ポップウェルという強力な面子です。
グレッグ・マティソンはハモンドB-3オルガンとミニモーグのみで演奏しています。これまではTAKE-5でミニモーグの音を作って演奏していましたが、TAKE-5だとミニモーグほど音が太くないため、どうしても中低域のボリューム感が不足してしまいました。これはオシレーター等の特性だと考えられます。
TAKE-5もそれなりにコシのある素晴らしい音はするのですが、ミニモーグのシミュレートはあまり得意ではない気がします。
しかしTEO-5はミニモーグの音により近付けることができました。2つあるオシレーターは両方ともノコギリ波を使い、サブ・オシレーターでオクターブ下の音も混ぜました。カットオフとレゾナンス、EGを少しいじってホーン系のテイストを出し、この音に少しポルタメントをかければベイクドポテトで出しているグレッグ・マティソンのミニモーグの音に近付けることができます。
オーバーハイムTEO-5はTAKE-5に比べると中低音が豊かで音が太いのでミニモーグの音はさほど苦労もなくプログラムすることができました。
スタジオでも使ってみましたが音の抜けは全く問題なく、爆音ギターの音にも十分対抗できました。マスターボリュームは3か4程度でした。
次回はTEO-5とTAKE-5の音作りの違いなどをリポートしたいと考えています。
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら





















 シンセサイザー 入門ガイド
シンセサイザー 入門ガイド
 PLAYTECH 鍵盤特集
PLAYTECH 鍵盤特集
 キーボードスタンドの選び方
キーボードスタンドの選び方
 おすすめの電子ピアノ
おすすめの電子ピアノ
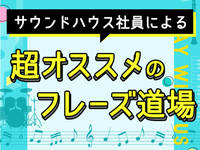 超オススメのフレーズ道場 キーボード
超オススメのフレーズ道場 キーボード
 キーボードスタートガイド
キーボードスタートガイド


















