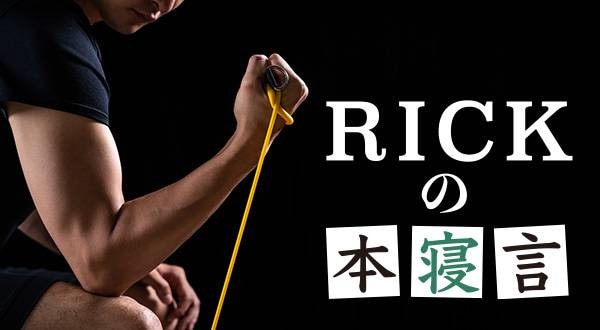愛って、何だろう?世の中、愛が冷え切っているせいか、そもそも愛とは何なのか、わからなくなってきたようにも思う。世界を見渡せば、各地で戦争が勃発し、連日、大勢の人が犠牲になっている。多くの子どもを含む民間人が命を失っていることも、憂慮しがたい現実である。この世は、いつの間にか「愛」とは真逆の泥沼の深みにはまってしまったのだろうか。普段は平和である日本においても、毎日のように殺人事件が報道されている。何の理由もなく第三者に襲われ、尊い命を奪われてしまうという悲惨な事件が後を絶たない。そして子どもたちまでが、実親から殺害されるという虐待事例も頻繁に起き続けている。まさにこの世は、末法の時代の様相を呈していると言わざるをえない。
そんな冷え切った現代の日本社会だから、愛を語ることなど、あまり身に覚えがない、という人がほとんどではないだろうか。自分もそのうちのひとりであることに違いはない。「いや、そんなことはないですよ!」とたとえ、若者が豪語したとしても、おそらく男女関係における「惚れた腫れたは当座の内」程度の話であり、恋愛感情が先走っている結果に過ぎないのではと想像する。人は、時には異性を好きになり、とことん惚れこんでしまうと、「愛している!」と思い込んでしまうのもわからない訳ではない。確かにそれも愛の一種なのだろうが、では何故、そんな情熱的な愛が、すぐに物別れに終わってしまうことが多いのだろうか。愛とは、冷めやすいものなのか。
本当の愛とは、いったい何なのだろうか。ある哲学者が言った。「愛とは距離を縮めたいと思う心」だと。何となく、的を得ているように思う。確かに好きな人、愛する人のそばにはいたいと思うし、逆に、嫌いな人の顔は見たくもないし、そばにいるのも嫌だ、と思うのが普通の人間感情ではないだろうか。でも、それだけでは愛の説明にならないのは明白だ。何故なら、ストーカーでさえ、距離を縮めたい、相手のそばにいつもいたいと思うからである。相手の気持ちを無視した一方的な行為や思い込みは、決して愛とは言えず、それは単なる危険な妄想、自己中心的な思い込みによる挙動にすぎない。では、本当の愛とはいかなるものか。
つい先週、YouTubeの動画がふと目についた。バンビのような鹿の子どもが浅瀬の川を泳いでいる動画だ。突然、岸の向こう側から大きなワニが波をたてて泳ぎながら、その小鹿に迫ってくるのだ。絶体絶命のピンチ。小鹿のスピードは遅く、このままでは間違いなく食われてしまうに違いないと思ったその時、遠く右側の方から母親の鹿が飛び跳ねるように泳いでくるのが見えた。まさに全速力で飛ぶように、水の上を走るかのごとく、ワニと小鹿の間を目指して突進してくるのである。小鹿がワニに追われて万事休すということを察知した瞬間から、母鹿はワニの行く手を阻むべく、その間に割って入ったのだ。そしてワニと小鹿の中間にまで辿り着くと、そこで仁王立ちし、ぴたりと足を止めたのだった。その数秒後、巨大なワニは一気に母鹿をむさぼり食いちぎった。母鹿は自分の子を助けるために、有無を問わず、自らの命を捧げるという場面をカメラが捉えていた。それは単に動物の本性、と言えるようなものでもないように思う。理屈抜きにして、相手の命を救うために自らを捧げる行為そのものが、愛の結晶のように思えてくるのだ。
聖書にも書いてある。「人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない」(ヨハネ15:13)。そのお手本を、母鹿が示してくれたように思う。相手のために自らが犠牲を払うこと、そして相手を自分よりも優先し、忍耐と寛容にあふれた思いに満ちて、率先して相手に尽くすことこそ、愛の原点ではないだろうか。それは、そんじょそこらの「惚れた腫れた」の男女付き合いの話とは異なる。人と人、魂との触れ合いの結末であり、相手のため、相手が利することを願いつつ、自分が労し、時には命まで惜しまず投げ出すこと、それが究極の愛なのだろう。その愛を実践したイエス・キリストも人類を救うため、自らの命を捨てて、十字架を背負われた。人間の歴史の中でもすごいことが、過去、おきていたのだ。今の冷めきった日本社会の坩堝にいる自分にとって、果たしてそのような愛を見出すことができるのか、疑問である。愛の話が自分自身、到底及ぶことができない理想郷に纏わる話にさえ思えてしまうのは、自分の心も冷え切ってしまった証拠なのだろうか。
最後にひとつの動画の話をして、締めくくりたい。サウンドハウスこどものみらい財団を通じて一緒に労する仲間の一人である、愛のメッセンジャー、板倉未來さんからの紹介で、このYouTubeを昨日、見ることになった。英語のショート動画だが、ああ、みんなが英語を理解できたら、なんと素晴らしいだろうと思う。いつか日本語でも見られるようになってもらいたい。言葉がわからなくても、見るだけで感動するかもしれない内容だ。
話はイラク戦争に遡る。町が空襲にあい、幼い兄弟2人が爆風の影響を受け、弟は両手を、兄は片手を失い、致命傷をおってしまった。そして助ける人もなく、靴箱の中に入れられて、道路際に2人は置かれていたのだ。その光景を思い浮かべるだけでも涙が出てくる。兄弟はそのまま拾われ、孤児院に収容されて手当を受けた。生命は危機的な状況にあったが、オーストラリア人がふたりを養子として受け入れ、母国にて治療に専念し、2人とも一命をとりとめることができた。
母親代わりとなったオーストラリア人の女性は、ふたりの子を自分の子どもと同様に育て、思う存分に愛を注いだ。そして母の愛に育まれたふたりは、重度の障害をもっているにも関わらず、笑顔の絶えない家庭での生活に、徐々に心が癒されていくのだった。そして17歳になった兄は、得意な歌を披露するためXファクターという最もハードルの高いテレビのオーディションにチャレンジし、厳しい審査に見事合格し、テレビに出演することになる。当時、Emmanuelと呼ばれた兄の歳は17歳前後と思われていたが、実際のところ、生まれた年や正確な年齢は知る由もない。
そしてステージの上に立ったEmmanuelは、自らの幼少時代の苦難を証し、そのバックには母親の愛情に包まれたふたりの子どもの笑顔が映しだされたのだった。そして彼は、ビートルズ、ジョン・レノンが作詞作曲したImagineを見事にステージで歌った。その姿と彼の素晴らしい歌声に、審査員全員が、大勢の観客と共に涙した。重度の障害を持ちながらも、彼がステージに笑顔で立ち上がった背景には、長い年月をかけて、ふたりの子を我が子のように愛を注いで育て続けた母親の姿があった。尊い母の愛により、死に直面していたこどもたちが立派に育てられ、戦果の悲劇に打ち勝つことができたことの証を目の当たりにし、感銘を受けたのは、自分だけではないだろう。
いかなる逆境においても、愛の力は計り知れず、人々の心、人生そのものを劇的に変えていくことができる。そんな本物の愛が、もっとあふれる日本の社会を目指すことを夢見て、何もできない自分ではあるが、できること、最初の一歩から、サウンドハウスこどものみらい財団を通じて、こどもたちに手を差し伸べていきたい。いや、それだけでなく、今、できること、できそうなことは何でも、すぐに実践することが大事なのだ。自分が死に直面した時に、やっておけば良かった、と後悔することがないように、大切なことを今、やっていきたい。愛はアクション、実践、その思いを胸に歩み続けたい。そんな夢を描くこの頃である。