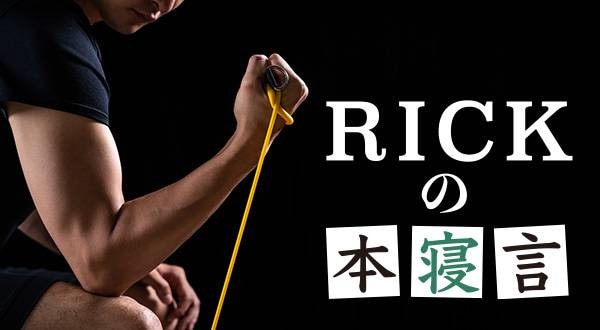2月6日、世界的な指揮者として活躍されてきた小澤征爾氏が88歳で死去した。残念でならない。あのパワフル、かつ情熱溢れる全身を使ったダイナミックな指揮がもう見られなくなるかと思うと、虚しさを感じる。小澤さんは旧満州で生まれている。小さい頃から音楽に没頭し、戦争のさ中、10代から楽団の指揮を学んだ。そして戦後間もない1959年、20代にして音楽を勉強するために貨物船に乗り込んでフランスに行き、そこで開催されたブザンソン国際指揮者コンクールで優勝しているのだ。その後の活躍も超人の域に達しており、ニューヨーク・フィルの副指揮者、サンフランシスコ交響楽団の音楽監督などを歴任した後、1973年からは30年近くもボストン交響楽団の音楽監督に就任している。すごいとしか言いようがない。
小澤氏は教育者、リーダーとしてもその才能を、生涯をとおしていかんなく発揮してきた。そして常に音楽と向き合い、西洋の音楽をとことん理解するまで果敢に挑戦しながらも、若手を育てることをいつも心がけていた。「でも僕だけでは歴史の点にしかならないから、若い世代を育てなくてはいけない。それぞれの個の能力が世界のスタンダードに達すれば、あらゆる芸術と仕事に国境はない。」このように小澤氏は自らの信念を語った。2000年には長野県にて小澤征爾音楽塾を開校し、弦楽器奏者に室内楽を指導しただけでなく、松本市では音楽祭も創り上げている。そして晩年まで世界各地から集まってきた若手の教育に時間をさき、音楽を愛する若者たちに、互いの音を徹底して聴き合うことの大切さを教えていたという。
その根底には、「音楽が、共通語として世界をつなぐ」という確信があり、常に世界と向き合う姿勢が貫かれていたからに他ならない。小澤氏はクラシック音楽という西洋から発祥した文化が世界共通の言語として、人々を繋いでいくことを目の当たりにしてきた。その貴重な体験があったが故に、誰もが国籍を当たり前のように問い、私たちは日本人だと考えている時代のさ中、誰もが「世界人でなければならないのだよ」と、小澤氏はテレビのインタビューで答えた。そして「日本は何が素晴らしいかと言うと、人間。もっと世界とあちこち混ざらないと。絶対狭くなっちゃだめ」と熱く語り続けたのだ。国や文化を超える世界共通語としての音楽の大切さを知りつくしていた小澤氏ならではの言葉だ。
音楽の世界に限らず、今や1990年代から始まったインターネット時代のおかげで、世界中がデジタルの世界においてリンクされるようになった。今日では、ありとあらゆる世界の情報をだれもが共有できるようになり、世界中に情報が溢れている。昨今ではAI化が一気に加速し、人間の頭脳を超えるまでになってきている。そこには想像を絶する膨大なデータ量を処理する架空の知恵袋が存在し、そのAIが発信するデータに多くの人が深い関心を持つようになってきた。このようなAIの活用を大前提としたネット社会においては、もはや国境も人種も何もない。世界はひとつなのだ。よって、インターネット社会となった今、私たち日本人も島国根性から脱皮して、国際人、世界人にならなければならない時がきた。
小澤氏ほどではないが、自分も1973年に日本を飛び出し、それから20年近くアメリカで10代から30代前半までの時を過ごした。そしていつしか自分には、半分が日本人、半分がアメリカ人、というハイブリッドな側面があることに気が付くようになる。その現実は、言葉を発する時に感じることが多くなった。つまり日本語を話している時は、和風の雰囲気を醸しだす日本人となるのだが、いったん、英語を話し始めると性格までが変わったようにアメリカ人になりきってしまう自分がいた。そうこうしているうちに世界を旅するようになり、段々と世界が小さく見えてくるにつれて、自らがインターナショナル化していくことに気が付くことになる。いつのまにか、世界人になっていたのだ。それが功を奏してか、サウンドハウスの起業にも大きく役立つことになる。
仕事の話に戻ろう。サウンドハウスの創業は、アメリカからの輸入事業から始まった。そして短期間で急成長した背景には、海外とのコネクション、特に米国メーカーとのタイアップを急速に進めたことがある。サウンドハウスの強みとは、自分の英語力とアメリカ人らしくビジネスができることにかかっていたと言っても過言ではない。そして瞬く間に多くの海外メーカーとの信頼関係を構築しながら代理店契約を結ぶこととなる。創業してから3年後には中国にまで足を延ばして多くの工場と提携し、サウンドハウスの自社ブランドも開発するまでになった。こうして長年にわたり海外の旅を百回以上繰り返しているうちに、もはや自分の頭の中には国境というものが段々と無くなっていくことを感じることとなる。今では日本からアメリカに行くというような出張は、自分にとっては息抜きの散歩のような感覚で捉えている。
自分の例は極端なのは百も承知だ。しかしながらAI化が進む社会の中でサウンドハウスが生き抜いていくためには、国境を越えた音楽の力を通じて、音楽家が国際人になるように、僕らも皆、国際人、世界人にならなければならない。それが時代の流れであり、それができないと、いつかは取り残されてしまうことになる。しかしながら、小澤氏とは違い、自分はそこまで若手の教育に取り組むことができていない。小澤氏との違いは明白だ。自分とはレベルが違う。小澤氏の元には、小沢氏から直々に学びたいという若者が世界中から訪れてきた。やる気に溢れた若者、ビジョンと目的をもった若手が集結することにより、教える方もやりがいを十分に感じたのではないだろうか。ところが自分のところには、サウンドハウスの創業者から学びたい、などという思いで入社するような若手など、皆無だ。むしろ最近は、自分のやりたいことを、自分風に、オリジナルでやりたい、という考えを持つ若者が多く、大切なことを教えたくても、なかなか教えるムードにならない。むしろ少しでも厳しいことをいうと、めげてしまう若者が目に付く。これはいったいどうしたことか。自分の人間性が足りないことが原因なのだろうか。
そうこうしているうちに、自分も歳をとってきた。そんな現実を尻目に、今が人生のターニング・ポイント、などと自らに言いかけてはいるものの、体の不具合はあちこちに生じてきていることを否めない。自動車レースで言うならば、一周回るごとにピットインに入るような状況である。それでもいったんピットインを出れば、全速力で突っ走ることができる。これが自分流であり、ゴールまで貫く決意である。よって、まだまだ余力はある。だから80㎞の遍路でさえも、一人でとことん、ゴールするまで突っ走ることができる。
つまるところ、若手を教育しなければ、サウンドハウスの未来はない。そのためには自分の言うことに耳を傾けてくれる若手がいなければならない。耳を傾けないならば、傾くまで待たなければならない。「鳴くまで待とう、ホトトギス」、とは良く言ったものだ。果たして自分にそこまでの忍耐があるか、今はわからない。それでも選択肢がなくなって来ている今、もはや残された道は限られている。つまるところ、旧約聖書に残されている知恵の言葉が、救いの道となる指針をほのめかしている。
天の下の出来事にはすべて定められた時がある。
生まれる時、死ぬ時
求める時、失う時
保つ時、放つ時
黙する時、語る時