■ ハモンドオルガンはオルガンの代名詞
今回の鍵盤狂漂流記もオルガンがテーマです。ヤマハのYC61という楽器を購入したことに端を発しますが、この楽器の良さを語るにはこれまでに国内外でリリースされた様々なコンボオルガンの機種や機能などを踏まえたほうが、より本機の魅力が伝わると考えます。
オルガンの代名詞ともいわれる普遍性の高いハモンドオルガンのコピーからスタートするコンボオルガンの歴史を理解し、オルガンという楽器の奥深さを垣間見ていただければ幸いです。
YAMAHA ( ヤマハ ) / YC61 ステージキーボード
■ ハモンドのコピーの紆余曲折
ハモンドオルガンという大きく重く、複雑な仕組みを持ったオルガンを再現するには非常に困難な課題が待ち受けていました。
ハモンドオルガンは内部でトーンホイールという円盤状の板を回転させ、分厚く重厚な音を作り出しますが、当然、本体の重量も重くなります。また、トーンホイール自体の再現も難しく、オルガンの個体差で音が異なるという宿命も持ち合わせていました。
しかもハモンドの音を出すにはレスリーというスピーカーも必要です。しかしレスリースピーカーも重くならざるを得ない構造でした。
重いハモンドとレスリースピーカーを軽くするという、無理難題を可能にしたのがサンプリングという先端技術です。サンプリングは簡単に言えば音を録音して再生するというデジタル技術をベースとしていました。
■ 世界を席巻したあの音…
1983年、イエスというプログレッシブ・ロックバンドがあり得ない音をイントロに使います。それが「オケヒット」。オーケストラが一斉にジャ~ンという音を発します。その音がサンプリングされ、楽曲「ロンリー・ハート」に使われました。たった5人のバンドが何十人というオーケストラの発する音を使うというセンセーショナルさもあり「ロンリー・ハート」は全米1位を獲得。これに寄与したのがサンプリング技術。オーケストラが一斉に発する「ジャン」という音をサンプリングし、その音をイントロ等に使ったのがイエスでした。
イエスが使用した機材はフェアライトCMI。
当時のサンプリングマシンの音は8ビット仕様でそれ程密度の高い音ではなく、実際のオケヒット音は押しつぶしたようなキメの粗い音で実際のオーケストラの音とは異なるものでした。しかしそれが異様に新鮮でカッコよかったのを記憶しています。
その後、このフェアライトCMIは大ブレイク。スティービー・ワンダー、ケイト・ブッシュ、ピーター・ガブリエル、トレバー・ホーン、国内では坂本龍一氏、久石譲氏など、世界中のミュージシャンが使用しました。

フェアライトCMI, public domain (Wikipediaより引用)
■ サンプリングそしてコンボオルガンへ
ハモンドオルガンシミュレートに一役買ったサンプリング技術。ハモンドオルガンが発するトーンホイール一つ一つをサンプリングし、コンボオルガンに登用。
しかし当時のサンプリング技術は発展途中で、当時の技術ではオルガンの音を全てサンプリングすることができず、数音を1つのサンプリング音で賄うなどの作業がされていました。サンプリングするためのメモリー容量が潤沢でなかったことが挙げられます。
しかし、技術の発達と共にメモリー容量は増え、本物のハモンドオルガンと聞き比べても一聴しただけではどちらがシミュレートしたオルガンか分からない程のクオリティになっていきました。それはレスリースピーカーのシミュレーターも同様でした。現在もその音質には磨きがかけられています。
■ 国内でコンボオルガンリリースラッシュ
国内では鈴木楽器やローランドからハモンドオルガンをシミュレートしたコンボオルガンがリリースされます。鈴木楽器はXKシリーズ、ローランドはVKシリーズなどです。両社共、ハモンドオルガンを模した9本のドローバーやレスリーシミュレーターが装備されていました。
私も鈴木楽器からリリースされたXK-1を使用していました。音はハモンドオルガンにかなり近づき、重さは12~3キロと70年代と比べれば信じられない程の軽量化がされて、使い勝手も良かったと記憶しています。
ローランドのVKシリーズも貸しスタジオで使いましたが音質は上々でした。ローランドのレスリーシミュレーターにはパネル上の光っている部分を手や顔で遮ることで音にトレモロが掛かる優れものでとても重宝しました。重さは鈴木楽器のものと同等くらい。
しかし腰の悪い私には12‐3キロでもいささか重く、軽量なキャリーを使いスタジオに運んでいました。キャリーに縛ったオルガンが移動中に傾くなど、運搬は困難を極めました。

ハモンドXK-1, (出典:鈴木楽器HP)

ローランドVK-8, (出典:ローランドHP)
■ ノードという素晴らしい選択
オルガンの重さに閉口した私は次なる選択をします。軽いコンボオルガンを探した結果、ノードエレクトロ4Dを購入しました(写真はNord Electro6D 外観は殆ど変わりません)。
このスウェーデン産のコンボオルガンは素晴らしいの一言でした。オルガンの音もいい。コンボオルガンといっても生ピアノの音もいい、オーバーハイム的なシンセサイザーの音もいい。鍵盤のスプリット機能も付いています。重さは8キロ以下。何よりバンドで演奏の際にはギターの爆音にも対抗できる音抜けの良さは秀逸でした。
4Dはある種、理想的な鍵盤でしたがスプリット機能はオルガンのみでシンセサイザーやエレピなどとのスプリットはできませんでした。それが可能になるのはeNord Electro 5D以降の機材です。
NORD ( ノード ) / NORD ELECTRO 6D 61 コンボキーボード
■ 沈黙を続けたヤマハ
各社からハモンドオルガンのシミュレート機材がリリースされる中、ヤマハは何故か沈黙を続けます。
2015年、ヤマハはrefaceシリーズの一環でオルガンサウンドに特化したミニ鍵盤のreface YCをリリースします。オルガンフルート音源を搭載。
サンプリングを用いた音源ではありませんでした。ハモンド系、ファルフィッサ系、エーストーン系、ヤマハYC系などの音が出るオルガン鍵盤の登場です。しかし、このオルガンは通常鍵盤ではなく、ミニ鍵盤。
ヤマハがオルガンサウンドを中心とした通常鍵盤のモデルをリリースするには、もう少し時間を必要としました。
このreface YCもいい音がしました。プロが使用するほどの音質で機材としての質感も高いうえに鍵盤も非常に弾きやすく、今も私の手元に置いている機材です。
次はいよいよ真打登場。YC61の世界が展開されます。
YAMAHA ( ヤマハ ) / reface YC オルガンモデリングシンセ
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら





















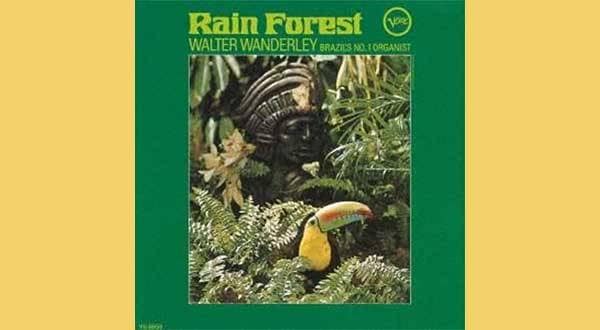
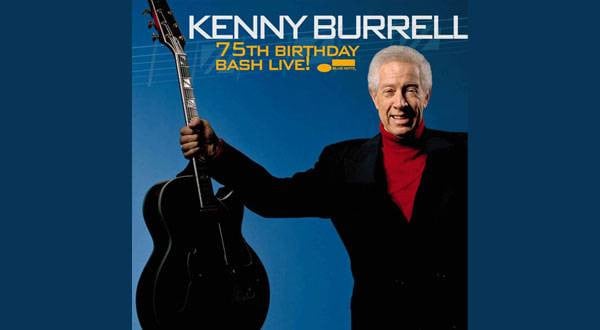
 自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集
自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集
 各メーカーの鍵盤比較
各メーカーの鍵盤比較
 まずは弾いてみよう!楽譜の読み方
まずは弾いてみよう!楽譜の読み方
 用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類
用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類
 キーボードスタートガイド
キーボードスタートガイド
 キーボード・ピアノ講座
キーボード・ピアノ講座















