今回はハモンドオルガンがテーマです。そのきっかけは私がサウンドハウスでヤマハのコンボオルガンをメインにしたキーボード「YC61」を購入したことに端を発します。このYC61という楽器がとても素晴らしく、18歳で触ったヤマハのオルガンとは隔世の感がありました。そこでオルガンの年代記、クロニクルから現在のオルガンの新機軸であるYC61を考えてみよう思います。
このYC61の音に私は驚きました。本当にハモンドオルガンそっくりな音がするのです。サンプリング技術を駆使した他社のオルガンはハモンドをサンプリングしているのでそっくりに決まっていますが、このYC61は新たな音源でその音を再現しているのがエポックです。しかしこのYC61にはサンプリングとは違った独特な味わいが加味されています。
さて、パート1はハモンドオルガンのシミュレートから始まったコンボオルガンのクロニクル(年代記)から展開をします。真打YC61はパートⅡから登場します。
YAMAHA ( ヤマハ ) / YC61 ステージキーボード
■ オルガンといえばハモンドオルガン
音楽の世界ではオルガンといえばハモンドオルガンといわれる程、ハモンドはオルガンの代名詞になっています。
ハモンドオルガンを使うミュージシャンは枚挙に暇がありません。ロックの分野ならディープ・パープルのジョン・ロード、EL&Pのキース・エマーソン、イエスのリック・ウェイクマン、トニー・ケイ、ピンク・フロイドのリック・ライト、TOTOのスティーブ・ポーカロ、デヴィッド・ペイチなど。ジャズの分野ではジミー・スミス、ジョーイ・デ・フランチェスコ、ジョン・メデスキー、ロニー・フォスター、ラリー・ヤング、ラリー・ゴールディングスなど、数多のミュージシャンがハモンドオルガンを使っています。
プレイヤーの数からもハモンドオルガンの音がどれだけ普遍性があるのかが分かります。
■ コンボオルガンの果てしなき変遷
私が大学で鍵盤楽器を始めたのは今から数十年前の1977年。
軽音楽部に所属し、最初に触った鍵盤楽器がヤマハのYC10というコンボオルガンでした。鍵盤は1段で本体上部がケースを兼ねた蓋になっていて、蓋を外すと鍵盤が出てきました。歴代のキーボード担当が使用していたため、ボロボロのオルガンでした。ハモンドオルガンとは全く違う60年代のグループサウンズの香り漂う音でした。
蓋の裏にはオルガンに直付けされる頑固なL型のスタンドが格納され、それを本体にネジで固定する仕組み。重量もかなりのものでした。
1977年当時のヤマハのオルガンの最高機種はYC45Dという2段鍵盤で、マイルス・デイヴィスや著名なキーボーディストが使用していました。その音はハモンドオルガンとは異なり、もう少しプラスチックな音だったと記憶しています。当時の価格は60万円程で重さは60キロ。ヤマハのフラッグシップ機で憧れの楽器でした。
ヤマハはこのYC45Dリリース以来、コンボオルガンのリリースはありません。ヤマハは長い間オルガン専用機はリリースしませんでした。口火を切る2015年のリフェイスYCまで待つことになり、およそ40年もの時間を必要としました。

ヤマハTC45D, (出典:ヤマハHP)
■ コンボオルガン開発の長い道のり
国内におけるコンボオルガンの変遷は技術の発展とシンクロしています。これはシンセサイザーも同様です。電気楽器、電子楽器はメモリーチップやLSI、半導体といった現代の最先端技術に依存しているからです。
コンボオルガンを製作するにあたり一番普遍的な楽器はハモンドオルガンです。1970年代からハモンドオルガンをシミュレートしたコンボオルガンが国内各社で製作されました。そしてその製作過程には様々な壁が立ちはだかっていました。
■ 開発は重さとの戦い。もちろんその音も…
元々、電気のポータブルオルガンはパイプオルガンに起源があると言われています。パイプオルガンは教会に設置されているので外に持ち出すことはできません。
ハモンドオルガンはパイプオルガンのない教会でも導入できる簡易的な小型オルガンとして製作されました。
ハモンドオルガンはトーンホイールという小型の円盤を回転させて音を出します。ハモンドオルガンの多くは2段鍵盤で鍵盤の数と同じトーンホイールを回すだけでも膨大な重量になります。ハモンドオルガンはポータブルとはいえ、ゆうに100kgを超える重さでした。それに加えハモンドオルガンの音を出すにはレスリースピーカーという特殊なスピーカーが必要でした。

ハモンドオルガンB- 3とレスリースピーカー, CC BY-SA 3.0 DEED (Wikipediaより引用)
■ レスリースピーカーとは
レスリースピーカーは木製のタンスの様な形をしています。中を見ると上部には対になったホーン状のスピーカーがあり、その下にモーターが付いて回転する仕組み。さらに上部だけではなく下部にもウーハースピーカーから出た音を回転するホーン状の金属によってトレモロを作り出す仕組みがあります(下図参照)。
ハモンドオルガンを演奏する際、プレイヤーはレスリースピーカーの回転を速くしたり、遅くしたりすることで出力されるトロモロ音をコントロールします。トレモロのオンオフもプレイヤーのセンスが問われる重要な要素になります。
このレスリースピーカーから発せられるハモンドオルガンの音はなんとも言い表しがたい温かみがあり、多くのプレイヤーたちから好まれていました。
とはいえレスリーには大きな問題がありました。それはハモンドオルガンと同様、レスリースピーカーの重さです。
私が運んだ楽器で一番重かったのが、フェンダーローズ・エレクトリックピアノでその次がレスリースピーカーでした。フェンダーローズは楽器の両側に取手が付いているので2人で持つ分には何とかなりましたが、レスリースピーカーはただの木の箱で取手などはなく、重さは50キロ以上!持ちにくいこと甚だしい代物でした。レスリーを運ぶコツはスピーカーの短い面を斜めにして2人で持ち上げて運ぶ方法がありましたが、いずれにしろ扱いにくさは天下一品。1人のオルガンプレイヤーが安易に持ち運べるものではありません。ハモンドオルガンの良さを出すにはレスリースピーカーが必要です。しかしハモンドとレスリーを1人で運び、演奏会場に行くことは到底不可能です。そんな演奏家泣かせの楽器。それがハモンドオルガンでした。
そんな演奏家泣かせの楽器に時代が味方をします。それがサンプリング技術です。このサンプリング技術がコンボオルガンの開発に拍車をかけます。
サンプリングのお話は次回のパートⅡで……乞うご期待!
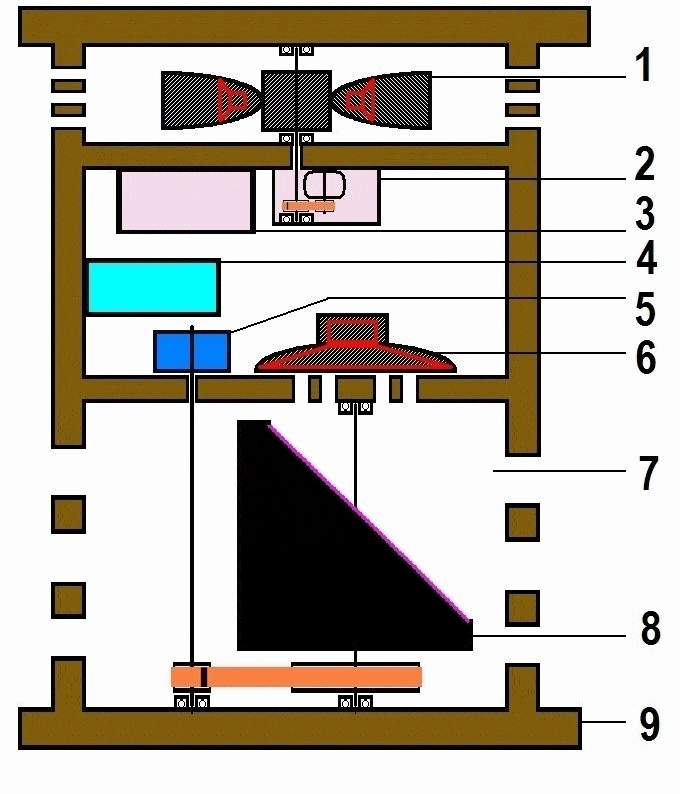
レスリースピーカーの断面図(イメージ), CC BY-SA 3.0 DEED (Wikipediaより引用)
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら
















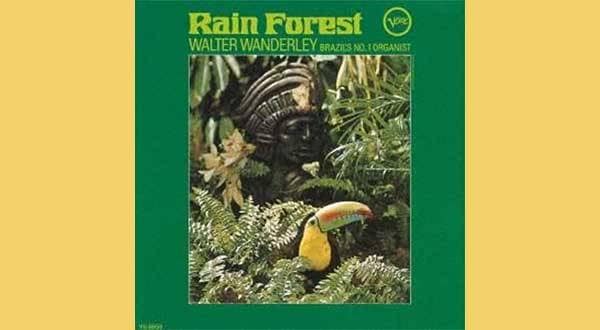


 自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集
自分にあったピアノを選ぼう!役立つピアノ用語集
 各メーカーの鍵盤比較
各メーカーの鍵盤比較
 まずは弾いてみよう!楽譜の読み方
まずは弾いてみよう!楽譜の読み方
 用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類
用途で選ぶ!鍵盤楽器の種類
 キーボードスタートガイド
キーボードスタートガイド
 キーボード・ピアノ講座
キーボード・ピアノ講座















