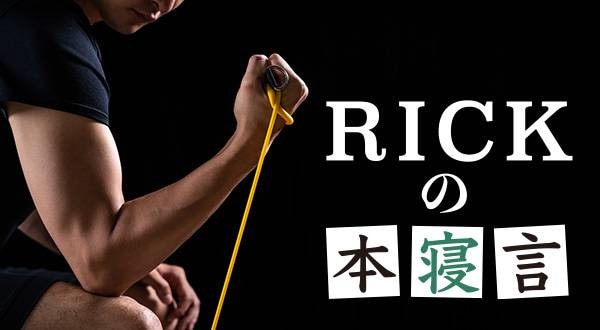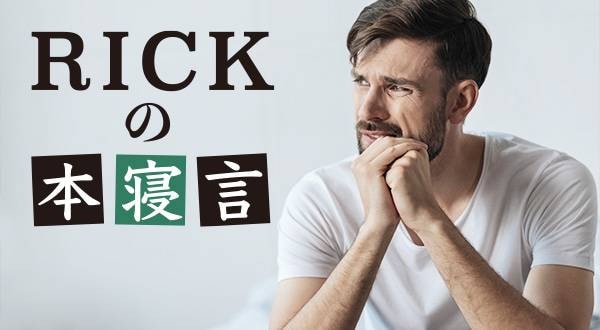ここ最近の若い社員は車社会に慣れすぎたせいか、自分の足で走ることを嫌う連中が多くなった。山登りも嫌、ハーフマラソンも嫌、と言い、全く運動をしない人が目につくことを危惧する。このままでは健康年齢を伸ばすことができず、歳をとると杖をつき、車椅子に乗らざるをえないスタッフが何人も出るように思えてならない。自分の体の管理こそ、一番大事にしなければならないはずなのに、なぜ、わからないのだろうか。
足腰を鍛えることは大事だ。だから自分は毎日走る。よって、ここ最近は登山やトレイルラン、山にこもって木を伐る「きこりっく」などという、山関連の話題ばかりをSNSを通じて発信してきた。しかしながら、よくよく考えてみると、自分の人生に大きな影響を与えてきたのは山ではなく、意外にも海であったことを改めて実感するこの頃である。幼い頃から海を眺めながら、自分自身が育まれてきた背景を振り返ってみた。
自分は東京渋谷生まれの都会っ子ではあったが、いかんせん昭和の時代であり、まだ渋谷の公園通りでさえも空き地が多く、野原になっていたことを覚えている。戦後の復興が目覚ましい東京ではあったが、両親は貧しく、別々に仕事をしていたため、いつも家には不在だった。そもそも自分は次男ということであまり構ってもらえず、きかん坊になっていたのだろうか。小学校4年になると、家を追い出されて(?)鎌倉の材木座海岸そばにある千代田区立の鎌倉臨海学園の宿舎に入れられることになった。親から見れば、自分のような煩しい子を育てるのは面倒だっただろう。また、自分という子どもの目からみても、つまらない無人の家にいるよりは、お友達で賑わう共同生活の方が楽しいと思えたのか、喜んで出家(?)したのだった。
鎌倉臨海学園は、どうも家庭環境を苦にする児童が集まる学校だったらしい。この1年半の経験が今となっては貴重に思える。臨海学園と言われるだけあって、気管支喘息や病弱など、健康上の問題を抱えている子どもたちが多く集まっていた。今でも連日のように夜通し咳き込んで、「苦しいですよ」と泣きながら嘆いていたH君の声が忘れられない。ある朝、真横で寝ていた小学5年生の彼の頭の髪の毛が全部、なくなっていた。彼の布団の上には髪の毛が散乱していたことを忘れることができない。小学生だというのに、栄養失調の影響だろうか。数年後、彼は命をおとしてしまった。昨今の医療を駆使するならば、H君は今でも生きていただろうと思うと、泣けてくる。悔しい。重症の喘息患者で、栄養失調にまでなっていたH君が、なぜ、臨海学園にいたのかと思うと悔まれる。そんな彼とも、小学校の時代に集団生活を一緒に過ごせたことは、自分の宝だ。
臨海学校では毎朝、起きると全員で裸になって乾布摩擦をした。それが当たり前のことであり、真冬の寒い中でも、服を脱いで、みんなで一緒に乾布摩擦をした。今でこそパワハラか!と言われるかもしれないが、みんなで裸になって、タオルを使って体をこすることで、だれもが健康になると思っていた時代もあったのだ。その後は、日課として海辺までみんなで散歩に行き、海を眺める生活が1年半も続いた。週末は、クラスメートと鎌倉の海岸を探索しに行き、洞窟を見つけては、「蛇がいた!」とクラス全体で騒いでいた日が懐かしい。毎日、海を眺めながら始まった日々、この鎌倉での毎日が、心のどこかで海とのつながりを深めることになったように思う。
 中学時代になると、勉強よりもテニスに夢中になり、中2の夏休みで初めて1か月間、アメリカのロスアンジェルスに短期語学留学をした。サンタモニカという海のそばにあるUCLA という大学のキャンパスに滞在したことから、週末の休み時は、海を眺めにしょっちゅうサンタモニカに出向いていた。そして日本に帰国し、中学校を卒業すると、すぐにアメリカに旅立つこととなった。行先は再びロスアンジェルス。その郊外にあるパロスパルデスという太平洋を一望できる街で3年間の高校生活を送った。自分の部屋からは海が見えた。そしてテニスの練習が終わると、週末はクラスメートと一緒に、近くのレドンド・ビーチまで車で遊びにいったものだ。そうそう、カリフォルニアでは15歳半から車の運転ができるので、高校へは車で通っていた。だから、いつでもビーチまで、気軽に遊びに行くことができたのだ。
中学時代になると、勉強よりもテニスに夢中になり、中2の夏休みで初めて1か月間、アメリカのロスアンジェルスに短期語学留学をした。サンタモニカという海のそばにあるUCLA という大学のキャンパスに滞在したことから、週末の休み時は、海を眺めにしょっちゅうサンタモニカに出向いていた。そして日本に帰国し、中学校を卒業すると、すぐにアメリカに旅立つこととなった。行先は再びロスアンジェルス。その郊外にあるパロスパルデスという太平洋を一望できる街で3年間の高校生活を送った。自分の部屋からは海が見えた。そしてテニスの練習が終わると、週末はクラスメートと一緒に、近くのレドンド・ビーチまで車で遊びにいったものだ。そうそう、カリフォルニアでは15歳半から車の運転ができるので、高校へは車で通っていた。だから、いつでもビーチまで、気軽に遊びに行くことができたのだ。
夏になるとテニスの合宿が、海沿いのマリブにあるペパーダイン大学のキャンパスで行われ、そこで2か月間を過ごした。日々、太平洋を眺めながらテニスの練習をこなすことが当たり前の日課となっていた。そして時間を見つけては、マリブビーチまで遊びに行っていた。そんな海と仲良しの生活は、やはり夢だったのか。高校3年生の時にとんでもない苦痛を味わうことになる。
高校の社会科の先生は、忘れもしないブランドン先生。レドンド・ビーチにヨットを保有していて、生徒何人かに声をかけて、ロスアンジェルス沖にあるカタリナ島まで遊びに行こう、と提案してくれた。これはまたとないチャンスということで、参加を決意。一緒に行く仲間のなかには、当時スウェーデンから留学していたオーサというとても可愛い女子もいた。クラスメート4人が集まっただろうか。
そして出発の当日、港に行くと、なんと船は小さなヨットだった。それまでヨットには乗ったこともなく、ワクワクするほど楽しく感じられたのだが、それもほんのつかぬま。出発して1時間ほどすると、ひどい腹痛に襲われ、下痢をしたか、と思い込んでいた。。。すると一気に吐き気に襲われ、船の上から海に向かってゲホゲホと吐くことになる。しかも島に着くまでまだ2時間ほどはあっただろうか。苦しくてつらくて、どうしようもなく、また、ヨットだから寝ることもできず、ずーっとロープにしがみついて苦しみ喘ぎ立っていた。
オーサの前でこんなみっともなく吐くなんて、と情けなく思い、悲壮感のあまり、自分を見失いかけていた。体力も消耗し、ほとんど立っていることもできなくなっていた。まさに地獄のヨットスクールのようだった。振り返るに、慣れないヨットに乗ったことで、ひどい船酔いをしてしまったらしい。その日から今に至るまで、ヨットに乗ったことは一度もない。正にトラウマになってしまったのだ。唯一のよりどころは、なんとオーサも苦しんでいたのか?トイレに我慢できなくなり、ヨットの真ん中で。。。
大学もロスアンジェルスに行くことになり、サンタモニカの海は、いつもそばにあった。また、クラスメートの中にはハワイから来ている学生も多かったことから、夏休みになると一緒にハワイに行き、ホノルルのビーチをたむろすることもあった。そしてハワイでスキューバー・ダイビングのレッスンを受けて、オープンダイバーの資格もゲット。海の底まで潜る楽しみも体験することができた。これほどまでに海とお友達になったつもりだったのだが、なぜかサーフィンだけは手を出さなかった。海の上をパドリングのように手で水をかきながら前に進む動作がどうしても気に入らず、首をずっと上げていることにより、首と肩が凝ってしまうと思うと、引いてしまうのだった。
そんな若き日の海の思い出から半世紀近くたった昨今、再び海と接することが多くなった。そのきっかけとなったのが、徳島への旅だ。まず。徳島の阿南市沖にある伊島に通いはじめ、そこに小さな家まで購入するほど、島には思い入れがあった。伊島には阿南の港から三島と呼ばれる定期船に乗って行き来することとなる。その後、徳島の小松島に会社が設立され、海の真横に倉庫が立ち上がった。その場所は遠い昔は海に囲まれた島であり、和田島とも呼ばれている。また、淡路島には海を見渡すことができる淡路記念館を立ちあげた。近くの東浦の港では船も購入し、その船に乗って小松島の会社まで行ったこともある。船は中古のボロ船を購入したことが仇となり、故障が続いた結果、和田島で沈没してしまった。
その後、いろいろな縁に恵まれ、徳島県でも最大級の島、竹ヶ島を購入することとなる。そして10年の年月をかけて、毎週末のように島に行き、波の音を聞きながら島をきれいに整備し続けてきた。竹ヶ島には船から海に飛び込んで、太平洋岸からよじ登ったこともある。まさにマイアイランド、と言わんばかり、海に囲まれた島を知り尽くすため、ありとあらゆる努力をこなしながら、月日が過ぎていった。
そして2021年、会社は女川に進出することを決めた。震災で大きな被害を受けた女川に残された旧女川中学校を廃校利用して物流倉庫を立ち上げ、女川の住民と共に海を眺めながら日々、仕事ができる環境が構築できたことは、嬉しい限りだ。これからも女川の発展に貢献したいと思う。と同時に、西日本では和田島の発展にも尽力したい。そして引き続き、竹ヶ島の整備に尽力し、誰がいつ来ても美しいと思える島にしていきたい。そんなことを考えていると、やはり、自分はいつも海と共に生きているんだ、と再認識する今日この頃である。