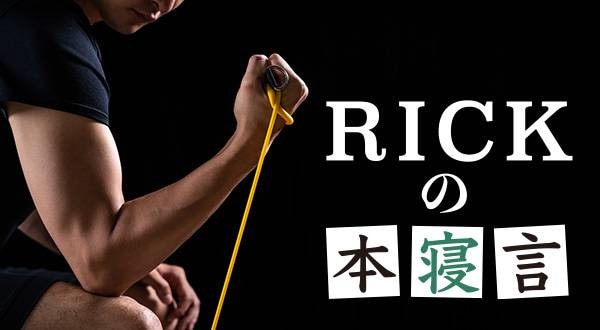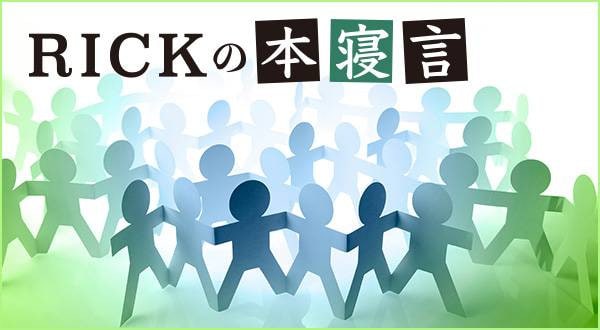梅雨の季節はじめじめしていて、憂鬱な気分になる。既に沖縄では梅雨明け宣言が出されているが、関東や東北はいつになるのだろうか。とは言え、最近の梅雨は、しとしとぴっちゃん、とも一概に言えず、線状降水帯の発達による集中豪雨かと思いきや、突如、真夏日の猛暑に激変する、というような異常気象の繰り返しが多いように思う。極寒よりも極暑のほうが好きではあるが、それにしても災害による被害があまりに多く、被災地における住民の無事を祈るばかりである。
梅雨と言えば、雨漏りが気になる。そしてなぜか、自分が創業したサウンドハウスでは、当初からオーナーである自分が自ら雨漏り対策を仕切ることとなっている。なんでだろう?しかもそのちょっぴりつらいお仕事は、ほとんどがひとりで行うという、孤独な作業の繰り返しだ。社員はそんな苦労を知る由もないが、そろそろ誰かに手伝ってもらいたいものだ。というのは、雨漏り対策には重労働がつきものだからかだ。
そもそもなぜ、サウンドハウスは雨漏りが多いか?答えは簡単だ。基本は中古の物件、すなわち、ボロボロの倉庫や建物を安く買っていることが、根本的な原因である。建物も古くなれば雨漏りもしやすくなるのは、周知の事実。また、施工技術がひどく、手抜き工事、もしくは業者の腕が悪く、まともに防水対策をしてないことも、雨漏りの原因となる。これまで幾度となく、手抜き工事の有様を目にしてきた。
しかしながら、なぜかしら身の回りの建物は、ごく一般的な中古物件よりも、雨漏りの度合がひどいように思う。しかも、新築の倉庫でさえも、雨漏りの害に見舞われてしまうのだ。2年前に竣工した徳島の倉庫増築がその一例だ。新しく倉庫を真横に増設したにも関わらず、その接続部分、エクスパンションとも言うが、その部分で防水加工がうまく施工されておらず、幾度となく雨漏りが生じることが確認された。新築でもやられてしまう!これはまさに、何等かの雨漏りの霊に祟られているとしか思えないほど、毎年、雨漏りの問題がのしかかってくる。
最近では1年半前に購入した旧女川中学校の水害がひどかった。そもそも12年前の震災が直撃した町の丘に佇む校舎であり、よくぞ無事に残ってくれたと思うほど、その容姿は昔のままに残されている。震災の被害を受けなかったのは高台に建造された旧女川中学校と旧女川小学校のみであり、メモリアルの建物として今後も大切に保全していきたいと考えている。
ところがどっこい、震災の傷跡が建物の随所、見えない所に刻まれていたのだ。その結果、雨が降るたびに旧校舎内は廊下や部屋が水浸しになる個所が多く、湿気がひどいことから壁面のあちこちにカビが生えてきてしまう。その対策として雨漏り対策の鉄人が登場することとなる。
すぐに雨漏りのひどい平屋部分の屋上に上ると、そこはプールのような池になっていた。しかしながら、以前、防水対策をした形跡があり、屋上は全体が分厚い樹脂製の防水シートでカバーされていることから、水が漏れないはずだ。ところが問題点をすぐに発見した。まず、水が溜まりすぎて防水シート端の立ち上がり部分を超えてしまうことから、その接続部分のシーリング処理が切れている個所から水が入ってしまうことを確認した。しかし、それだけでは雨漏りは生じない。必ず、その下にある元の屋上部分のどこかに穴や亀裂があるに違いないことから、思い切って防水シートを全部、ひとりで剥がすことになった。
これが大変な作業。なぜなら、まず、この分厚いシートは重たい。10mx20m位はあるだろうか。その重量級のシートが、水が漏れないようにぴちっと接合されているので、1m幅くらいにカッターナイフでカットしていく。そして5m位ずつに切り分け、ぐるぐると巻いてロール状にし、気合をいれて「えい!」と持ち上げて運ぶのだが、これがやけに重たく、とんだ重労働だ。さらに問題は、とにかく汚い。なぜかというと、水が端から滴ってしみこみ、結局は屋上全体の防水シートの下に水がたまっていたので、そこに虫がいっぱい生息していたのだ。説明のしようがないほど気持ちが悪い光景を目の当たりにする!それを我慢して、防水シートをはいで丸めていくのだから、これは我慢比べの何物でもない。
そうして全部はがして屋上を検証してみると、一発で漏水の原因がわかった。まず、建物の壁面と屋根があたる場所の接合部分にあるシーリング、つまり隙間を埋める材料があちこちで切れており、その小さい隙間から水が滴ってしまうということだ。しかもまったくシーリングされてない箇所がなんと多いこと。手抜き工事の発覚だ。本来は防水シートを張る前に、すでに隙間がある個所をシーリングして塞ぐのだが、シートを張るからということで手をいれなかったのだ。だから雨水がしみこみ、雨漏りが起きてしまう。
もう一つの問題は、ドレーンといって排水溝の入り口にある鉄製の金具だ。これらが錆びているだけでなく、その排水溝の金具と躯体の間に隙間ができてしまい、池状に水が溜まりはじめると、そこから壁に沿って水がしたって漏れていくことがわかった。よって、自分の仕事は隙間にシーリング材を埋め込み、水が漏れないようにするだけでなく、排水溝の周りもしっかりと隙間をふさぎ、水が建物の中に入らないようにすることだ。こうすることにより、雨漏りの98%は防ぐことができたが、体力を消耗することとなる。
もう一つの事例を挙げよう。西に向かい、徳島の大型倉庫での漏水対策だ。あれは漏水というより、滝のような洪水対策ともいえる。以前から雨が降るたびに、長さ150mもある大型倉庫の中心線の部分のおよそ20m位のスパンで、天井から落ちてくる大量の水により、床がびしゃびしゃになることがわかっていた。それがだんだんと悪化し、ある大雨の日、屋内だというのに、滝のような幅10mほどの水の壁が倉庫内にできていたのだ。実に驚いた、というより、成す術がなかった。
この雨漏りの原因はすぐに見当がついた。切妻型屋根の屋上には、その尖った中心線の部分に雨水用のドレーンがついているのだが、その溝が明らかに流れなくなっており、そのドレーンから溢れた水が左右にはみ出し、それが滝のように12m下のフロアーまで落ちていくのだった。対策はただひとつ。屋上に上り、100mほどの長さにもなる超ロングな雨水用のドレーンをクリーニングすることだ。
早速、屋上に上り、ドレーンをチェックしてみると、案の定そこには、ヘドロのように積もった泥がどっと詰まっていた。ここからが大変な作業だ。というのも、そのドレーンにはステンレスのカバーが屋根のようにかぶさっており、げんこつがひとつ入る程度の狭い隙間しかない。そこで面倒なことだが、小さいスコップを使って少しずつ泥をバケツに入れることにした。この作業が何時間も続く。果てしなき戦いの始まりであり、正直、うんざりする。あまりのロングランに、途中で救援スタッフもひとり合流したが、いかんせん高さ12mもある屋上斜面での作業であり、正直、高所恐怖症の人にはできない仕事である。しかも内容がヘドロのくみ出し。それをバケツに入れて、満杯になると、屋根の端まで歩いていき、屋上から下に棄てるという作業。実はこの部分は最も怖い作業なのだ。なにせ命綱なしに屋根の端までいき、高さが10m近くある個所からバケツを振って泥を棄てるのだからたまらない。さすがに自分も幾度となく、怖いと思った。よってこの仕事は自分しかすることはなく、決して他のスタッフにやらせることはなかった。
ところがスコップでのクリーニングには限界があり、ある程度までしか綺麗にはできない。所々、手の届かない箇所が見つかり、結局はそこに水が溜まってしまうことがわかった。そこで高圧洗浄機が登場する。この屋上ドレーン清掃のために、業務用のパワフルな高圧洗浄機を用意していた。ところが電圧と水圧に関わる問題が2点生じた。まず、高さ12m、長さ150mもある大型倉庫であり、電源コードで電気を引っ張ってくるにしても、リール型の延長コード30mを5台ほど連結しなければならない。すると当然ながら電圧降下という現象が起きてしまい、高圧洗浄機が動かなくなってしまう。よって最短距離を考えたあげく、近くの社宅コンセントから横切るように延長コードを引っ張り、3台の連結でなんとか高圧洗浄機が動くようにした。
もう一つの問題は水圧だ。水道の蛇口からホースをつなぎ、水を引っ張るのだが、通常は30mほどの距離までしか推奨されない。それをむりやり100mほど引っ張ってくるのだから、これまた水圧の減少となり、高圧洗浄機の水が出にくくなってしまう。ここでも苦肉の策として、最短距離となるルートを自ら見出し、30mのホースを3台連結して、かろうじて水が出るようにした。ここまでが大変だった。その後は、高圧洗浄機を使ってどんどんと強烈なシャワー水をドレーンに吹き付けながら、綺麗にしていくだけだ。そして時間をかけがならやっていくと、遂にドレーンがピカピカになった。これで水が流れるようになり、ドレーンの端から溢れることはなくなる。つまり、雨漏りが止まることを確信した。
とにかく、雨漏りの災難はとめどなく押し寄せてくる。前述した女川の旧女川中学校では大地震の結果、屋上だけでなく、壁面の躯体にも随所にひびが入っており、雨が降ると、そのクラックから水が建物の中に染み込んでくることが発覚した。まさに震災の傷跡に、当初は気付かなったのだ。それを修繕するためには、屋外からクラックの個所を特定し、シーリングするだけでなく、壁面全体を防水塗装するため業者を呼ぶしかなかった。また、成田の本社、あの豪華で最強と思われる建物でも、ここ最近、原因を特定できない雨漏りが連続しておきている。困ったものだ。成田の新館と呼ばれる20年以上も前に購入した建物は、屋上からの雨漏りを放置していたあまり、天井がカビだらけになり、大変な事態となってしまった。このような雨漏りとの戦いは、枚挙にいとまがない。
雨漏り対策が自分の仕事かと思うと、時折ふと、「俺は何をやってんだ!」と思うこともある。しかしながら、それも創業者としての責任。自らを「雨漏り対策の鉄人」と称して、奮い立たせることにしている。