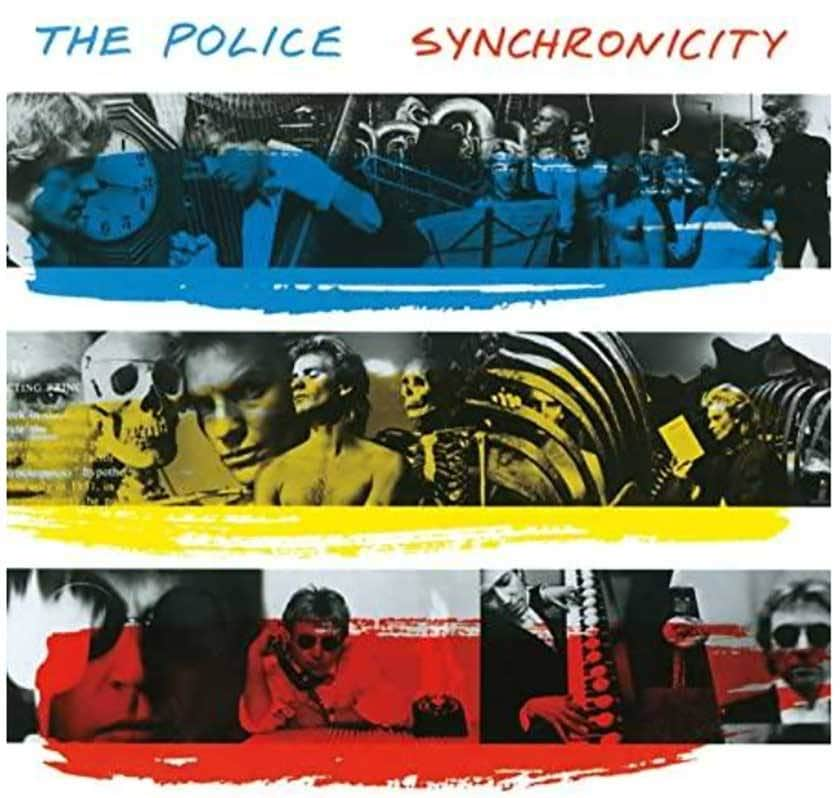
こんにちは。洋楽を語りたがるジョシュアです。 第21回目は、ザ・ポリスThe Policeについて語ります。彼らのことを一行で表すと「空間を生かした前代未聞のアンサンブル、セクシーな歌声、コーラスはイオー、イオー」です。その活動期間は短く、1978年から1983年の間に発表したオリジナル・アルバムは、わずか5枚でした。しかし、その作品群はいまだに多大な影響を与え続けています。ラスト・アルバム『Synchronicity』(1983年)の大ヒット・シングル"Every Breath You Take"(邦題:見つめていたい)は絶対どこかで聞いたことがあるはずです。アメリカでは、ラジオ史上もっとも演奏された曲として認定されている程ですから。
■ The Police “Every Breath You Take"
ザ・ポリスはイギリスで結成されました。1977年にスティング(vo, b)、アンディ・サマーズ(g, vo)、スチュワート・コープランド(dr, vo)の3人組ラインナップとなり、1978年に『Outlandos d’Amour』でデビューしました。スティングはジャズ、スチュワートはプログレッシヴ・ロック、アンディはブルース・ロック出身でした。しかし、当時のイギリスではパンク・ロック創生期で、パンク以外はロックと認めない風潮がありました。そのため、彼らは自分たちの本性を表さずに、あえてパンク・バンドのふりをしていました。実際、アンディは後のインタビューで自分たちのことを「フェイク・パンクだった」と語っていました。しかし、その才能は隠しきれませんでした。彼らの音楽性はパンクとしてはあまりにも異質なものだったからです。
● 歌がうますぎる
スティングのハイトーン・ヴォーカル、シャウトしてもつぶやいても歌い込んでも良し、という万能性は、怒鳴るだけのパンク・バンドとは一線を画していました。それを俳優並みのルックスで歌われるものですから、当時のロック女子は心を完全につかまれたのでした。 そしてコーラスでは、「イオー、イオー」という独特のフレーズを多用しました。これは、一度聞いたら頭から離れない中毒性があります。
● 音が独特すぎる
ザ・ポリスのサウンドはとても独特で、ザ・ポリスの前に似たようなバンドはいませんでした。しかし、彼らの登場後は「ザ・ポリスに影響を受けた」というバンドばかりです。簡潔に表現するとしたら「ロックとパンクとレゲエとスカをごった煮にして宇宙に持っていった」ようなサウンドです。デビュー・アルバムは「フェイク・パンク」らしく、パンク的な攻撃性や瞬発力を持っていました。しかし、それはあくまでも見せかけの姿でした。シングル曲"Roxanne"と"Can’t Stand Losing You"は、ともにレゲエ的なリズムが展開され、クリーン・トーンのギター・カッティング、1拍目の頭でリズム・セクションが鳴らない「頭抜き」のリズムは、それまで全く聞いたことのないサウンドとなっていました。
■ The Police “Roxanne"
● スチュワートのドラムが凄すぎる
ザ・ポリスの独特さを作り出しているのはスチュワートの独特なドラムが影響しています。スチュワートは、拍子の頭で必ずしもバス・ドラムやクラッシュを叩きませんし、2拍4拍でスネアを叩くとも限りません。代わりにハイハットやリム・ショットを乱れ打ちして、独特な世界観を作ります。シングル・ストロークで超高速オカズを加えるかと思うと、サビ前の4拍目にスネアのフラム打ちを一発加えるだけの超シンプルなオカズで、曲の展開をガラッと変えるのです。機材的にも音色的にも、スチュワートの功績は多大です。今や誰もが使うスプラッシュ・シンバルですが、1920~30年代のビッグバンドジャズで使われてからは、しばらく忘れられた存在でした。これをロック・シーンに復活させたのはスチュワートです。胴長のタム、オクトバン(別名キャノンタム)を広めたのも、これまた彼です。そして、甲高いスネアにタムのピッチ!次の動画は、そんなスチュワートらしさに満ち溢れています。
■ The Police “Driven To Tears"
● アンディのギターが凄すぎる
アンディのザ・ポリス時代におけるメイン・ギターは、フロントにギブソンのハムバッカーを搭載したフェンダー・テレキャスターでした。これにコンプレッサー、モジュレーション(初期はフェイザーやフランジャー、後期はコーラス)、テープエコーをかけたマーシャルのクリーン~クランチ・トーンは、ハードロックやメタルの重いサウンドとは一線を画するものでした。また、アンディは「間(ま)」を有効活用して、「引き算の美学」で空間的なギターを奏でました。ザ・ポリス以前にこのようなギタリストはあまりいませんでしたが、ザ・ポリス以降はこれが標準となり、猫も杓子もアンディ風のギターを弾くようになりました。そして、ギター用マルチ・エフェクターが出ると、必ずアンディ風のサウンドがプリセットとして用意されるようになりました。
● スティングのベースが凄すぎる
スティングはもともとジャズ出身だけあり、初期はフレットレス・ベースをピック弾きしていました。よく聴くと音程がズレていますが、結構細かいことは気にしないところが生々しいニュアンスを与えています。一方、後期ではシンプルなビートを繰り返すミニマル的アプローチが目立ち、ライヴではフレット付きベースを弾くようになりました。それを歌いながら演るのは本当に難しい(というか、常人には無理)です。
● 歌詞がうますぎる
ザ・ポリスの歌詞はひねりが効いていて、当時のパンクのように怒りと不満をただぶちまけるのとは違いました。デビューシングルの“Roxanne"は売春婦に恋をする男性、2枚目の“Can’t Stand Losing You"は女性にフラれて自殺する男性で、見事にBBC(イギリスの国営放送)から放送禁止となりました。しかし、それを逆手にアメリカに飛びプロモーションを行った、というしたたかなエピソードがあります。さらに、等身大の大人のおもちゃに恋する男性をテーマにした“Be My Girl"というヘンな曲もあります。
一方、絶妙すぎる歌詞は、2作目『Regatta de Blance』のオープニング曲“Message in a Bottle"(邦題:孤独のメッセージ)で、こんな物語です。「離れ島にいる男性」→「瓶のなかにSOSとメッセージを書いて海に流し、助けを待った」→「1年経っても助けは来ない」→「朝起きて浜辺に行ったらビックリ、同じような瓶が千億個もあった(今ここ)」。
■ The Police “Message in a Bottle"
名曲“Every Breath You Take"も強烈な歌詞です。フラれた女性を「いつまでも君のことを見てるよ」というストーカー気質の男性の歌です。歌詞を深く考えずに「この曲を結婚式のテーマソングにしました!」とスティングに話しかけるファンがたくさんいるらしいですが、スティングは「なんて不健全な関係なんだ」とインタビューで茶化していました。
● バンドとして凄すぎる
こんな個性的な凄腕3人が集まって、良い曲があり、ルックスが良くて、パンクを演じるまでの余裕を持ち合わせています。その結果は、次の動画のようなカオスとなります。これは1980年、京都大学西部講堂での来日公演をとらえたドキュメンタリー風ビデオです。バンドのオーラも観客の熱狂ぶりも尋常ではありません。
■ The Police “Walking on the Moon"
ザ・ポリスの音は、アルバムを重ねるごとにどんどん進化していきました。特に、スティングの作曲能力が開花し、4作目『Ghost In The Machine』と『Synchronicity』では、アンディとスチュワートがスティングのバック・ミュージシャン(しかも、最高級の!)に聞こえてしまうときすらありました。『Synchronicity』での成功は過去の作品以上となり、その後のツアーも大盛況で、スタジアム・ショウも瞬時に完売しました。また、このツアーの様子は、ライブビデオ『Synchronicity Concert』として発売されました。そのおかげで、当時の興奮を今でも擬似体験できるのがありがたいところです。次の動画は、そのオープニング曲、"Synchronicity I"。こんなパワフルな曲が1曲目だから、困ったものです。しかも、6/4拍子ですし。
■ The Police “Synchronicity I"
不幸なことに、バンドの成功と並行してメンバー間の衝突も頂点に達し、ツアー終了後、ザ・ポリスとしての活動は休止状態となりました。スティングはバンド再開への退路を断つかのようにベースを置き、ギターを手に取ってソロ活動を開始しました(ソロ2作目からはベースを持ち直しましたが)。3人がその人間関係に真摯に向き合い2007~2008年の再結成・世界ツアーを行うまでには、20年以上の年月が必要でした。
個人的な思い出話ですが、『Synchronicity』が出たとき、私はアメリカの中学校に通っていました。"Every Breath You Take"はMTVとラジオを占拠し、ビルボード誌チャートで8週連続1位を記録していました。(ちなみに、同じ年にはマイケル・ジャクソンの"Billie Jean"と"Beat It"が同時にチャートインしていて、良い時代でした。)そんな彼らがツアーで街に来たら、もうサーカス状態で、翌日以降は大変!みんな競ってバンドのツアーTシャツを来て、コンサートの思い出を誇らしげに語るのでした。「イオー、イオー」を中学生のうちに生体験できたなんて、なんて恵まれた中学生なのでしょう!
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら











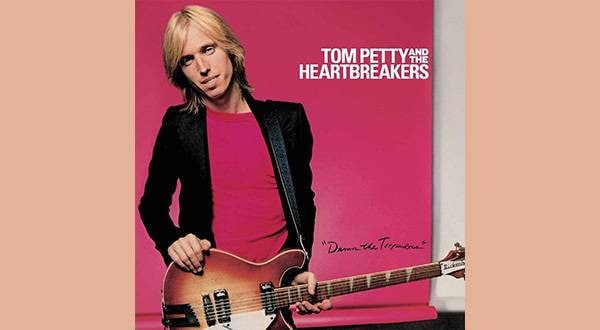
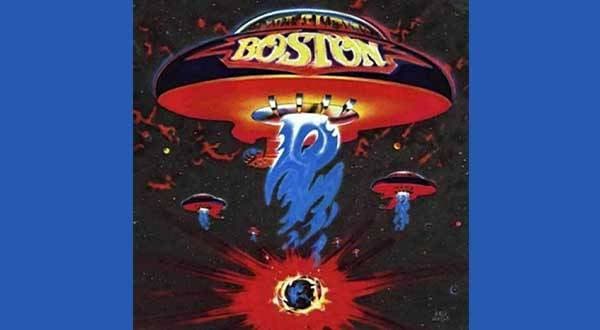
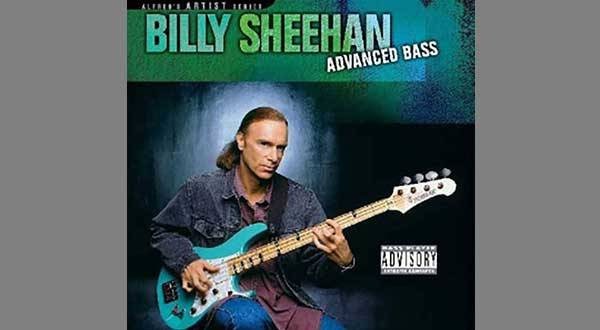
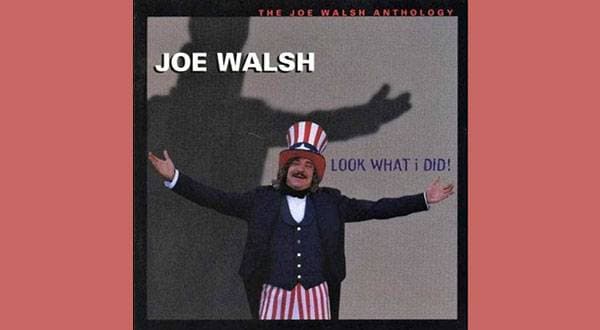
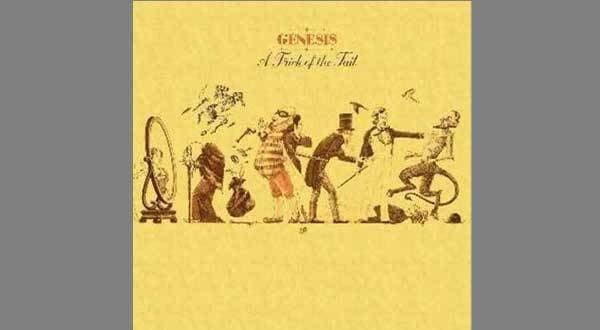
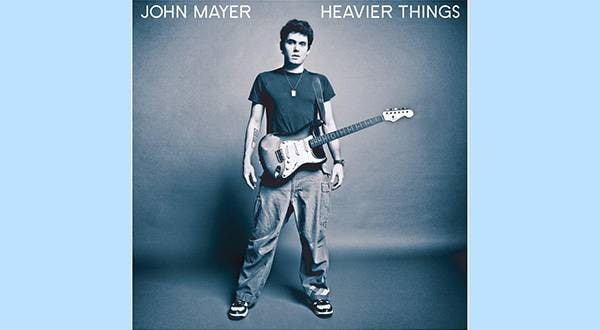
 バンドあるある相談
バンドあるある相談
 基礎から学ぶベースレッスン
基礎から学ぶベースレッスン
 SONEX 吸音材特集
SONEX 吸音材特集
 サウンドハウス社員が選ぶ 『おもしろ商品』はコレだ!
サウンドハウス社員が選ぶ 『おもしろ商品』はコレだ!
 DTMセール情報まとめ
DTMセール情報まとめ
 人気スタジオモニター徹底比較
人気スタジオモニター徹底比較















