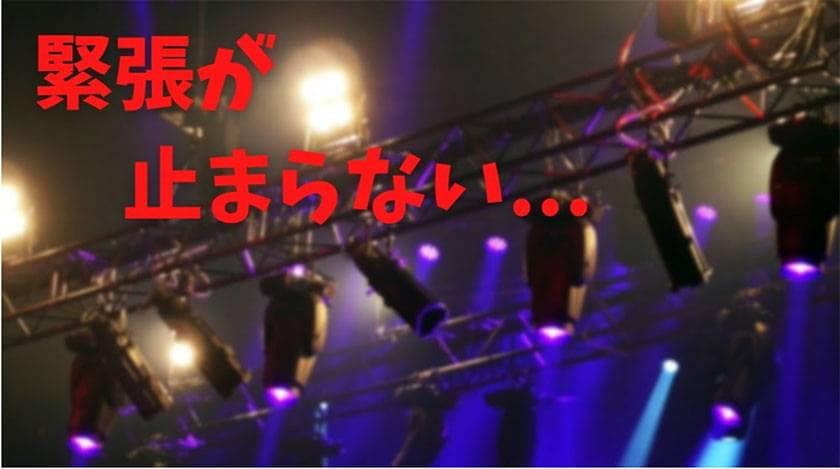
どこで読んだかは覚えていませんが、日本を代表するギタリストであるCharさんのインタビュー記事でこんな発言をされていたのをずっと覚えています。
緊張するのは不安要素があるからだ
つまりステージに上がる前から緊張するかどうかは決まっていることで、緊張しないためには事前に不安要素を取り除かなければならないということです。
確かにCharさんはいつでも不安なんていうものとは無縁に見えます。
自信に満ち溢れ堂々としたプレイスタイルですが、きっと誰よりもギターが好きで努力を怠らなかった結果身に付いたものなのでしょう。
程よい緊張感は気を引き締めてくれるので必ずしも悪いものではありません。
しかし、頭が真っ白になってしまったり冷や汗をかいたりするほどの緊張は演奏するうえでマイナスになってしまいますよね。
それではCharさんの名言をもう少し掘り下げて、ステージ上で過剰な緊張をしないためには具体的にどうしたらいいか考えてみましょう。
■ 練習が足りていない
アマチュアミュージシャンが抱える不安要素の多くは演奏能力が足りていないことではないでしょうか?
普段のスタジオ練習で弾けていないことがライブで弾けるわけがありません。
そりゃ不安になって当たり前というものです。
これに対する解決方法はふたつあります。
まずひとつめは、ひたすら練習を繰り返すことですね。
根性論みたいになってしまいましたがやはりこれに尽きます。
10回弾いて8回ミスがないくらいまでの完成度までもっていけばかなりの不安は解消されるでしょう。
仮に本番でミスってしまったとしても大きなミスには繋がらないはずです。
ふたつめの解決方法は簡単なアレンジに変えてしまうことです。
もし本番までの時間が足りないならひたすら練習という根性論は通用しません。
曲全体に差し支えのない程度で簡単な演奏に変えてしまいましょう。
弾ける可能性が低いのに本番に挑むよりはよほどマシです。
ただし、いつもこの方法に逃げていては成長もしません。
可能な限りは練習で弾けないものは弾けるようにし、どうしても本番に間に合わない時の 対応策と考えておきましょう。
■ MCの練習をしていない
MC担当限定ですが、喋るのが苦手な人は演奏が終わった瞬間に怒涛の緊張の波が押し寄せてきます。
何を話したらいいのかわからなくなり『えっと、なに話しましょうか?』と観客にふって寒い思いを経験したボーカリストも少なくないでしょう。
これを回避するためにはスタジオで通し練習をする時にMCも含めた練習をすることです。
一字一句同じ内容を話す必要はありません。
大まかにMCのガイドラインなど話の落としどころさえ決めておき、念のためその内容を書いた紙をカンペとして足元にでも貼っておけば完璧です。
ついでにその紙はスマホで撮影しておき、ちょっとした空き時間などで日々MCの練習をしておきましょう。
それで急に余裕が出たからといって、MC練習をしていないメンバーに突然話をふるのはやめてくださいね。
■ 機材チェック
バッチリ練習もしてMCも繰り返し通し練習して何も怖いものはナシ!
と、思っても何かトラブルが起きてしまうのがライブです。
それまで順調に進んでいても思いがけないトラブルに対応できず、それがきっかけでボロボロになってしまうというのもよくあることです。
これには最終的に経験値が大きく関わってきます。
機材が突然故障、ハコ側が原因で音が出ない、などプロの現場でも起きてしまうことなので100%回避することはできません。
こういったトラブル時にはどれだけ観客に気付かれないよう対応できるかが重要ですが、トラブルの経験を積んでいないと焦ってしまうのは仕方がないところもあります。
起きてしまった時は『いい経験を積んだ』とも考えられますが、事前に入念なチェックと対策法を準備することでトラブル時に焦ってしまう可能性を最大限に少なくしておくことはできます。
例えばマイクスタンド、ドラムの各スタンドは緩んでいないか確認が必要です。
弦やピックなど消耗品は劣化具合を確認し、予備のものは必ずすぐに用意できる状態に。
特にギター弦は切れやすいので、可能であればサブのギターを準備しておくと安心感が全然違います。
■ 性格的な問題も
ここまでで不安要素を持たずにステージに上がる3つの方法を紹介しましたが、あまり緊張しない人はこの3つを全てクリアしているというわけでもありません。
楽天家の人、観客が身内ばかり、そもそも自分自身に何も期待していないなど様々な理由から不安要素が不安に繋がらない場合もあるのです。
こういった理由から緊張しない人たちを羨ましく思うこともあるかもしれませんが、その必要はありません。
なぜなら不安を抱えたままステージに上がることをヨシとした人は成長が見込めないからです。
もちろん音楽の楽しみ方は人それぞれなので成長=正義ではありません。
自分たちさえ楽しければいいというのも他人に迷惑をかけない範囲であればそれも楽しみ方のひとつでしょう。
しかし、成長しないといつも同じようなことを繰り返すことになりいつか飽きてしまいます。
音楽を楽しみとするならいつまでも楽しめるように成長し続けることが大切だと思います。
緊張感に悩まされている人はもちろんのこと、あまり緊張しないという人もここで紹介した3つの方法は見直してみてはいかがでしょうか?
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら
















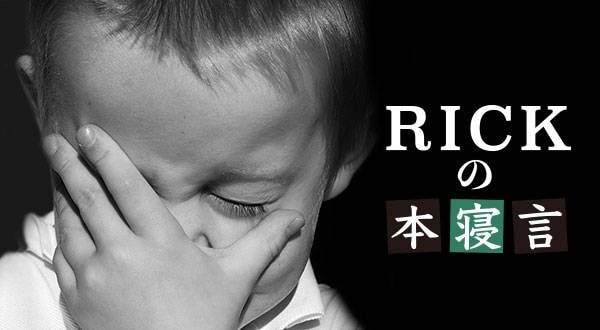
 高性能ミニチュアマイク AUDIX MICROシリーズ
高性能ミニチュアマイク AUDIX MICROシリーズ
 K&M マイクスタンド比較表
K&M マイクスタンド比較表
 ○○やってみた!
○○やってみた!
 ワンランク上のボーカルマイク選び
ワンランク上のボーカルマイク選び
 最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信
最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信
 サウンドハウス虎の巻 !
サウンドハウス虎の巻 !















