皆さんこんにちは。年も明け、2022年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲も発表されましたね。ということは、吹奏楽部の皆さんはそろそろ夏のコンクールの自由曲を決め始めるころではないでしょうか。しかし、人数の関係で大編成A部門に出場できないという部活も多く見かけます。そうなると小編成として出場することとなるのですが、曲を探す際に、「小編成は大編成に比べて曲のレパートリーが少ない…。」や「やりたい曲があるけど楽譜が大編成しかない…。」となってしまい、なかなか曲決めが進まないものです。そこで今日は、小編成で演奏することができ、一際人気のある3作品をご紹介させていただきたいと思います。ぜひ夏コンの曲案に入れてみてください。 それでは見ていきましょう!
吹奏楽の小編成について
まず本題に入る前に、小編成の定義をしておきたいと思います。 一般的に、小編成といえば奏者が30人以下で構成されていることと定義されます。 (ちなみに、吹奏楽コンクールに出場する際、小編成は一般的にB部門とされていますが、この定義はそれぞれの支部、都道府県吹奏楽連盟によって定義が異なるようです。詳しくは、自分の出場する吹連のホームページや要綱をチェックしてみてください。)
言わずと知れた定番曲 歌劇「トゥーランドット」
最初は、コンクールでも定番となっているプッチーニが作曲した最後のオペラ歌劇「トゥーランドット」です。フィギュアスケートなどで第3幕の「誰も寝てはならぬ」が用いられたこともあり、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
【ちょこっとあらすじ】
舞台は北京。美しい姫であるトゥーランドットに恋した王子カラフが、結婚するために三つの謎を解く。そして、最初はカラフに対して冷淡だったトゥーランドットの心が揺れ始め…。
( 「トゥーランドット」あらすじと解説 )←もっと知りたい人用
全国大会でも幾度となく演奏され、多くの名演を生み出してきました。その中でも一際有名であり、過去に全国大会で福岡工業大学附属城東高校が演奏していたのも、この編曲です。
(歌劇「トゥーランドット」よりarr.後藤洋 演奏 陸上自衛隊中央音楽隊)めっきり大編成のイメージしかない歌劇ですが、実は最小8人から演奏することができる小編成編曲版も存在しています。しかもその編曲を担当しているのは、サックスアンサンブル「アミューズメント・パーク組曲」や金管アンサンブル「文明開化の鐘」で有名な高橋宏樹さんです。原曲の壮大さ・美しさはそのままに、少人数での演奏が可能となっています。
(「トゥーランドット」セレクションarr.高橋宏樹 演奏 尚美ウインドフィル)ミュージカルの代名詞 「レ・ミゼラブル」
続いては、皆が一度はやってみたいと憧れるであるミュージカル「レ・ミゼラブル」です。 原作はヴィクトル・ユーゴーの小説であり、楽曲はミュージカルとして公演される際に、シェーンベルクによって作曲されたものです。
【ちょこっとあらすじ】
舞台はフランス革命後のパリ。パンを盗んだ罪で19年投獄ののち、仮釈放されたジャン・バルジャンは、コゼットを養子として引き取る。その後、革命の雰囲気が漂う中、コゼットは学生革命家のマリウスと恋に落ち…。
( 「「レ・ミゼラブル」あらすじと曲、作品解説) ←もっと知りたい人用
こちらもよく自由曲として演奏されていますが、それは森田一浩さんが編曲されたものです。名演といわれる、埼玉県立伊奈学園総合高校が演奏したのもこの編曲です。冒頭のリコーダーの印象が、強く残っている人も多いでしょう。
(ミュージカル「レ・ミゼラブル」よりarr.森田一浩 演奏 陸上自衛隊中央音楽隊)ほかにも大編成版では、「ラッキードラゴン~第五福竜丸の記憶~」などで知られる福島弘和さんが編曲された版もあります。
そしてこちらの曲は、いくつか中・小編成版が存在しています。探してみるといろんな版がありますが、今回はその中でもやりがいがあるのではないかと感じた2作品を挙げておきます。
(Les Miserables 「レ・ミゼラブル」より arr. Marcel Peeters )こちらはかなり原曲に近い編曲ですが、演奏人数の目安が35人となっており、小編成というよりは中編成という立ち位置になります。しかし、大編成と同じような迫力、緊迫感のある編曲となっています。
(Les Miserables selection from the motion picture arr. Hal Leonard)こちらはフレキシブルの楽譜となっており、最小パート5人+打楽器1人での演奏が可能です。パートを重ねることで、それ以上でもできるようになっています From the motion picture ということで映画版をもとにした編曲となっており、映画版だけの「Suddenly」を含めた5曲でメドレーとなっています。吹奏楽としてだけでなく、アンサンブルとしても取り組めますね。
素晴らしいハーモニーが人々を魅了 歌劇「ローエングリン」より「エルザの大聖堂への入場」
最後は前の2曲とはガラッと変わって、素晴らしいハーモニーを持つワーグナーの歌劇「ローエングリン」の第2幕より「エルザの大聖堂への入場」です。あまりコンクールで演奏される機会はありませんが、吹奏楽の中では定番曲とされています。原曲では合唱も入っており美しい和音、ハーモニーが進んでいきますが、そのため演奏する難易度はかなり高いと言われます。 レミゼなどほど有名ではないかもしれませんし、技術的にも音楽的にも派手なものではありませんが、取り組む価値が大いにある楽曲だと思います。
(「エルザの大聖堂への入場」指揮 佐渡裕 演奏 シエナ・ウインド・オーケストラ)大編成版ではカイリエの編曲のほか、鈴木英治さんや保科洋さんなど様々な方が編曲されていますが、そんなエルザにも小編成版が存在します。こちらも「トゥーランドット」と同じく高橋宏樹さんが編曲を担当されています。
(「エルザの大聖堂への入場」arr.高橋宏樹 演奏 尚美ウインドフィル)技術と、それ以上に響きと表現力が必要となるこの曲をぜひチャレンジしてみませんか?
というわけで今回は、「トゥーランドット」「レ・ミゼラブル」「エルザの大聖堂への入場」の3曲が、小編成でも取り組めるということをお話してきました。このように見てみると、世の中にはたくさんの小編成楽曲があるのだなと改めて感じました。次の機会に、他の小編成編曲や、邦人作品についてもご紹介したいなと思っています。 これからさらに需要が高まるとされる小編成作品。今後の進化に目が離せません。
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら












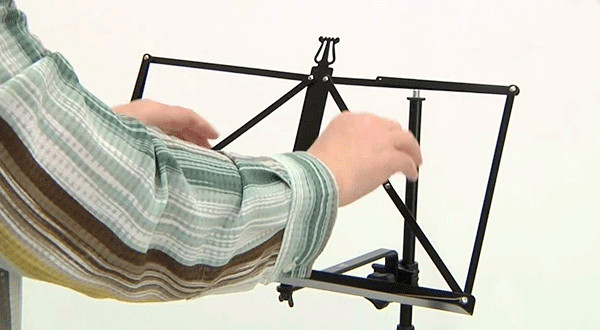
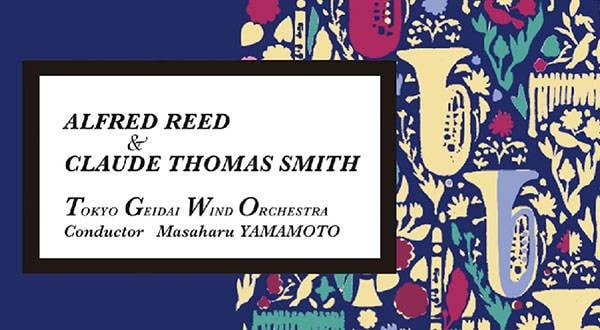
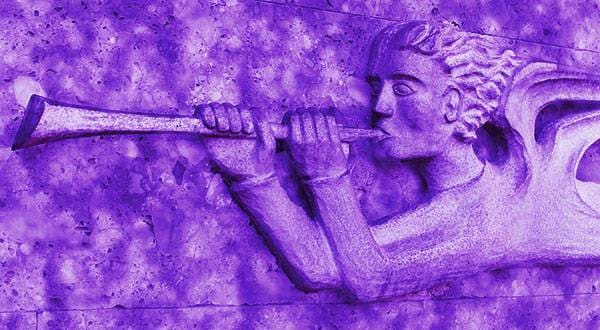


 プラスチック管楽器特集
プラスチック管楽器特集
 デジタル管楽器とは
デジタル管楽器とは
 PLAYTECH 管楽器特集
PLAYTECH 管楽器特集
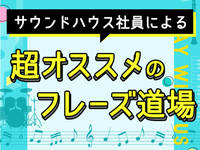 超オススメのフレーズ道場 クラリネット
超オススメのフレーズ道場 クラリネット
 弦楽器 初心者講座
弦楽器 初心者講座
 サウンドハウス虎の巻 管楽器入門ガイド
サウンドハウス虎の巻 管楽器入門ガイド


















