ジャズバンドのディレクターには、ミュージシャンをリードし、インスピレーションを与えて、最高のパフォーマンスを実現することが求められます。また、オーディオ技術の進歩に伴い、サウンドエンジニアとしての役割も求められるでしょう。これらには、リハーサル、スタジオレコーディング、コンサートのライブストリーミングなどの音作りも含まれます。
基本的な技術的ノウハウとオーディオ機器があれば、これらの課題を解決することができます。以下の "音作りのヒント"では、ジャズバンド・アンサンブルで最高のサウンドを得るために、各楽器に適切なマイク設定とイコライジングの方法について、いくつかの簡単なテクニックを説明しています。
ギターアンプのマイキング
他の楽器の音量に合わせてギターの音量をコントロールできるようにするためには、ギターアンプの音をマイクで拾うのがベストです。アンプから出る音自体がギタリストのモニターにもなり、ステージ全体の音量を管理しやすくします。

ヒントとテクニック
位相キャンセルの問題を避けるために、単一指向性のダイナミックマイクを1つのスピーカーに向けて設置してください。マイクは、スピーカーのグリルの布にほぼ触れる位置で垂直に設置します。マイクのヘッドをスピーカーの中心と端の約半分となる位置に置くと、音を最大限に捉えられます。オーバーロードを避けるため、ダイナミックレンジの広いマイクを選びます。また、指向性の高いマイク(スーパーカーディオイド)を使用すると、意図しないステージ上の音を拾わなくなる効果があります。
ギターのイコライジング
- - 80Hz以下
- ギターの中で最も低い弦の周波数は80Hz、それ以下の周波数をカットすることでうなりを抑えます。
- - 80Hz~320Hz
- この音域は、楽器の「中核」ともいえる基本的な音域です。必要に合わせてブーストやカットを行います。
- - 2kHz~3kHz
- この帯域をブーストすると、音色をコントロールでき、ピックのアタックが強調されたりしますが、逆に耳障りになることもあります。
- - 5kHz~10kHz
- オーバードライブやディストーションを掛けているとこの領域が強調される傾向があり、ブーストしすぎると、非常に耳障りな音になってしまいます。
- - 10kHz以上
- 10kHz以上では、必要な音ほとんどないので、適宜カットします。
ベースのマイキング
キャビネットへのマイキングは、エレクトリック・ベースもギターもほぼ同じですが、ベースの場合、キャビネットへのマイキングそのものが必要ないかもしれません。最近のベースアンプの多くは、ダイレクトライン出力を備えており、その信号をミキサーに送ることができます。ライン出力がない場合は、ダイレクトボックスで代用します。

ダブルベース(アップライトベース)マイキングのヒントとテクニック。
ダブルベースの場合、単一指向性のダイナミックマイクをブリッジ自体に向けることで、より多彩な音色を得ることができます。マイクは弦から数十センチ離れたところに置き、ブリッジとその先にある楽器の表板に向けます。このとき、演奏者の邪魔にならないように配置してください。
ベースのイコライジング
- - 40-200Hz
- この周波数帯は、各弦の基本的な音を含んでいます。
- - 200~800Hz
- 倍音が顕著に現れる場所です。必要に応じてブーストまたはカットします。
- - 300~500Hz
- この範囲を強調することで、独特のウッディな音色が得られます。
- - 800Hz~16kHz
- グロール(唸り)、アタック、プラック(pluck)のトーンなどがこの帯域にあります。ブーストするとアグレッシブな音になります。
グランドピアノのマイキング
適切なマイキングを行わないと、ピアニストは常に最大限の強さで演奏しなければなりません。指向性の高いコンデンサーマイクをペアで使用すれば、ピアノのステレオイメージを維持しつつ、演奏者の表現力を余すところなく伝え、ハウリングも最小限に抑えることができます。

ヒントとテクニック
スムーズで均一なレスポンスを得るために、スモールダイアフラムで設計された2本のペンシル型コンデンサーマイクを使用します。まず、2本のマイクを弦のダンパーの後ろ20~25cmのところに置き、ピックアップの先端が正面を向くようにします。マイクヘッドは弦から約20cmの高さになるようにします。ハンマーストライクと弦の音色のバランスが最も良くなるように、マイクを弦に対して45~85°の角度で設置してください。マイク自体は60cm~90cm離れた場所に設置し、ピックアップエリアが重なっていても構いません。
グランドピアノのイコライジング
- - 200Hz以下
- この周波数領域を下げることで、キックドラムやベースとのミックスに余裕を持たせることができます。
- - 200Hz~1kHz
- 即興的な伴奏(バンピング)の基本となる音域です。ブーストしすぎると音が濁ってしまいます。
- - 1kHz~6kHz
- ここでブーストをかけると存在感が増しますが、ギターの音域と重複する可能性があります。
- - 6kHz~8kHz
- ソロでは、ここにブーストをかけることで、各音をはっきりさせ、ミックスからピアノのサウンドを少し引き立てさせます。
- - 8kHz以上
- この領域をブーストすると、かなり派手にピアノの音が装飾され、耳障りな音になることもあります。
ドラムのマイキング
バンドが安心して演奏できるように、ドラムの音がはっきりと聞こえなければなりません。ドラムセットへのマイキングでは、何台のマイクを設置するか、マイクをどう取り付けるか、過大な入力に耐えられるかなどが課題となります。さらに、ドラム、シンバル、キックドラムにはそれぞれ専用のマイクが必要です。ドラム用のマイクは、便利なキットとして販売されています。

ヒントとテクニック
マイクは2本(キック+スネア)が最低条件です。バスドラムには、大口径のダイナミックマイクが最適で、ドラムヘッドの真正面に設置します。多くの場合、ヘッドには穴が開けられていますので、そこに設置します。スネアドラムやタムには、単一指向性のダイナミック・マイクを打面のすぐ近くに設置します。リムクランプは、ドラマーの演奏を妨げないように、マイクをヘッドのエッジに対してほぼ垂直に(わずかに角度をつけて)固定します。タムを追加した場合、同じタイプの指向性ダイナミックマイクを追加します。ハイハット・シンバルには単一指向性コンデンサー・マイクを使用します。クラッシュシンバルやライドシンバルを収音する最も簡単な方法は、2本の単一指向性コンデンサーマイクをピックアップエリアを狭めるように角度をつけて設置します。
ドラムセットのイコライジング
- - キックドラム
- 基本音は60~80Hz、アタック音は4kHz付近です。
- - スネアドラム
- 240Hzを中心とした音色で、スネアやスティックのアタック音は5kHz付近です。
- - タム
- タムの音色は、サイズとチューニングにより、120~250Hz、打音は5kHz付近。
- - シンバル
/ ハイハット - シンバルのキラキラ感やシズル感は、6kHzから10kHzあたりが基本です。 打音や金属音は200Hzくらいに現れます。
管楽器のマイキング
初期のステージバンドでは、各列に数本のマイクを配置してアンサンブルの音を捉えつつ、個人がそのマイクに近づいてソロを取ることができるようにしていました。この手法は今でもよく使われています。そのコツは、演奏者が「マイクに合わせて演奏する」ことで、最高の音色を得ることができます。マイクは楽器のベルに向かうように設置します。演奏者は楽器のベルをマイクから15~25センチ程度離して演奏します。楽器の軸を少しずらすと、ウインドノイズやバルブノイズの少ない滑らかな音色になりますが、マイクから離れすぎると音量が下がることがあります。

ヒントとテクニック
金管楽器や木管楽器のソリストに機動性と表現力を与え、ステージ上の煩わしい配線を排除するためには、ベルにクリップ式のコンパクトなワイヤレスマイクを装着するのが良いでしょう。管楽器用のワイヤレスシステムは、クリップオン・ラベリア式を改良したものです。
管楽器のイコライジング
バリトンサックス、テナーサックス、アルトサックス、ソプラノサックスは、音域は異なるものの、似たような倍音成分を持っています。同様に、トランペットとトロンボーンにも、周波数は異なりますが、同様の成分があります。
- - サックスの基本
- サックスの「ホンク」と呼ばれる音色は、300~500Hzの範囲にあります。
- - サックスの倍音
- キーイング、風圧、アンブシュアなどによって生じる倍音「スクォーク」は、1000~2500Hz付近に集中しています。これをカットすると温かみのある音になり、ブーストすると透明感や存在感が増します。
- - 金管楽器の暖かさ
- 金管楽器の暖かさは、200~450Hz付近の周波数にあります。ここをブーストし過ぎると、音が濁ってしまいます。
- - 金管楽器のボディ
- 1~5kHzの帯域により、音色を明るくしたり、ボディ感を出したりします。
- - 金管楽器のラスプ
- 金管楽器の音色の特徴であるエッジ感(ラスプ)は、5~8kHzの範囲に現れます。





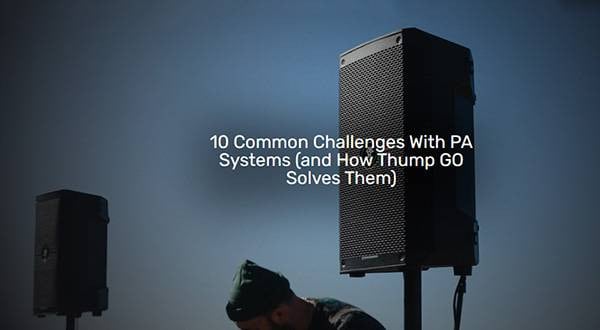




 SAMSON特集
SAMSON特集
 SAMSON PAスピーカー特集
SAMSON PAスピーカー特集
 SAMSON 簡易PA比較表
SAMSON 簡易PA比較表
















