今回は前回のブログ予告通りだと真空管の番外編になる予定だったが、緊急なネタ(新鮮かつ美味)が上がってきたので取り急ぎブログにしてしまった。
普段お目にかかる事のない内容なので、長年の疑問や疑いが晴れると思うぞ。
では、行ってみよう。
ギターアンプやベースアンプ、果てはPAシステムから家庭用ステレオまで、どんなに時代が変わっても決して動作方式が変わらない物にスピーカーユニットがある。
世がデジタル製品でごった返してもこれだけはアナログ(こうしないといけない理由がある)のままだ。
アンプや、ステレオ、PAのトラブルでよく聞く言葉の中に「スピーカーが飛ぶ」というのがある。
どういう事だろう、、、、。
これはスピーカーユニットに過大入力や直流電流が入ったために、コイルが焼けてスピーカーが壊れたことを指す。
これがその状態のコイル画像だ。

コイルが真っ黒に焦げているのが分かるだろう。
更に、コイルは本来上から下まで均一にキッチリ巻いているはずなのだが、なぜかこの画像を見る限り巻いてあるハズの部分に巻いていない隙間がある。
問題の部分を拡大してみよう。

これが飛んだスピーカーの壊れた部分だ。
真ん中へんは真っ黒に焦げ、指で触るとパキパキに折れて崩れてしまう。
この部分はボイスコイルと言って、普段マグネットの隙間にこの部分が入り宙吊り状態になっている。
コイルに電気信号(交流信号)が流れると、フレミングの法則に乗っとり電気信号に応じた磁力が発生しコーン紙を振動させるという原理だ。
そのコイルに瞬間的な大電流や、高圧電圧を流すとこのような無残な最期になってしまう。
筆者の経験上、過大入力ではコイル切れやコイル焼けがおきやすく、直流電圧が流れた場合はボイスコイルの変形によるコーン紙の固着がおきやすいような気がする。
こうなってしまっては最早治しようがない。
スピーカーユニットごと交換するのが一番手っ取り早いが、物凄く高価なスピーカーだったり貴重品だったりした場合、コーン紙交換(リコーン)も考える。
しかし、これがまた超大変な作業なので普通は諦めるだろう。
今回の一番大事な部分。
実は、音じゃない場合も飛ぶ事がよくある。
それば電源スイッチを入れた際のポップノイズや、スピーカーの出力周波数の範囲を超えた周波数を入れた場合など。
劣化したスイッチを使用した大出力パワーアンプのポップノイズはかなりの広範囲の周波数を一気に出力するため、スピーカーのコーン紙が大きく前後に動く。
これでよくウーファーが飛ぶ。
出力周波数を超えた周波数で飛ぶという現象は、本来そのスピーカーの再生音域に合っていない音を入れ、コイルが動けと命令してもコーン紙が動かない、もしくは大きく動き過ぎてしまう為に起こる。
入力した信号量に応じた動きをしてくれない場合、そのエネルギーはどこかしらでべつの物に変換されてしまう(エネルギー保存の法則)。
これが熱になると最初に害を被るのは画像にあったボイスコイルになるのだ。
、、、段々めんどくさい内容になってきたのでここで一旦終了する。
ギターアンプ、ベースアンプ、オーディオ用など、安い物ではないだけに余計なノイズやうっかり大音量などには気を付けて頂きたい。
ではまた。

















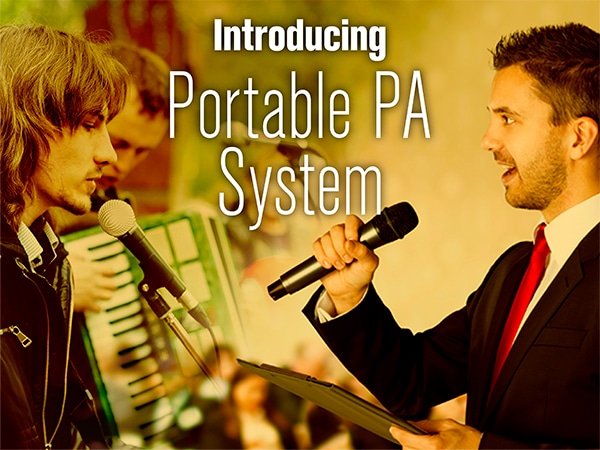 ポータブルPAシステム特集
ポータブルPAシステム特集
 CLASSIC PRO 簡易PAシステム特集
CLASSIC PRO 簡易PAシステム特集
 SAMSON PAスピーカー特集
SAMSON PAスピーカー特集
 簡易PAシステム タイプ別おすすめランキング
簡易PAシステム タイプ別おすすめランキング
 簡易PAセットとは
簡易PAセットとは
 PAシステム講座
PAシステム講座















