こんにちは!
BABY BABYというアコースティックユニットのギタリスト兼、作業療法士のフジオカタクトと申します。
いつも目を通してくださりありがとうございます!
突然ですが、あなたは「第六感」を信じますか?
いえ、決して怪しい話ではありません。(笑)
前回の記事で、
「思い通りに身体を動かすにはボディマッピングの他に、筋肉や感覚といった要素も影響してきます。」
といったことを文末で書いていました。
人間には五感(視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚)があることはご存知かと思います。
今日話していく「第六感」とは、五感を超えた不思議な感覚や直感のことではなく、体性感覚、その中でも「固有感覚」という正真正銘、人間のメカニズムのことです。
これがどういうもので、ギターを弾くことにどんな影響があるのか語っていきたいと思います!
最初に教科書的なことを書いておきますので、さらーっと読み流してください。(笑)
結構難しい内容なのできちんとした事が知りたい人はググってください。すみません。
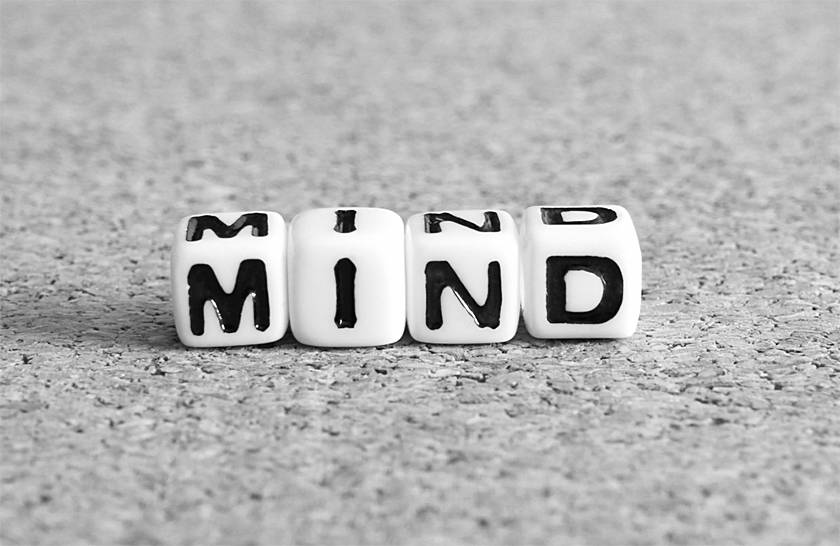
体性感覚とは、表面感覚(皮膚の感覚のこと)と固有感覚(深部感覚ともいう)に分けられます。
表面感覚には触覚(触れた感じ)、圧覚(押さえられた感じ)、温覚(暖かさ)、冷覚(冷たさ)、痛覚(痛さ)があります。
固有感覚には位置覚(手足の相対的な位置)や運動覚(運動の方向)、他にも振動覚、深部痛覚というのもありますが今回の話題に関係がないので省略します。
今回知って欲しいのは位置覚と運動覚のことなので、細かいことは置いといてここではこの2つを合わせて固有感覚と言わせてください。(ちなみに筋肉についての感覚なので筋感覚と呼ばれることもあるそうです。)
ザックリいきましょう!
固有感覚を感じる部分は関節や筋肉、腱にあって、体の位置や動き、関節の曲がり具合、筋肉への力の入れ具合といったことをセンサーみたいに感知することでその情報を脳へ伝えているのです。
簡単にいうと目で見たりしなくても身体の位置や動き、力加減がわかる、この働きが固有感覚です。
例えばですが、目を閉じたまま手を挙げたり指を動かしてみてください。わりと正確に手がどの辺にあってどんな動きをしているかわかるはずです。
他にも、コップの水を飲むとき、特に何も考えなくても、きちんと目視しなくても手にとって口元まで運べると思います。
無意識のうちに使っているこの固有感覚、意識を向けることもできますし、向けなくても人間は動くことができます。
そのために視覚や触覚といった他の感覚に注意を向けていると固有感覚にまで意識が向きにくいことがあります。

その昔テレビゲームに熱中していてお母さんの「ご飯できたよー!!」という呼びかけに気付かなかった、なんて経験ありませんか?
人間はひとつのことに集中していると他の感覚に意識を向けにくくなってしまうのです。
これをギターに置き換えると、例えば左手のフィンガリングや右手のストロークにばかり集中して注意が向いていると、首や肩に力が入っていたり、無理な姿勢や必要以上に力が入ってしまうなんてことが起こってきます。
実際僕もこういう考えに至る前は上に書いたようなことでとっても悩んでいました。
僕にはどうやら右肩が上がる癖があったみたいで、うまく弾けないフレーズがあると手元ばかりに意識がいってしまい、右肩が上がっていることに気付けなかったのです。
右肩が上がることで腕の位置も変わってしまうため、ピッキングの位置が安定せず、また肩が上がって動きが固定されることで他の肘や手首が代わりにサポートしようとして余計な力が入る、、、といった感じで負のループに陥ってしまっていました。
こういう無意識のうちに起こっているカラダの反応に対して、固有感覚を利用することで意識を向けていくことができるのです。
さてさて少し自分の話が入ってしまいましたが、なんとなく感覚というものがギターを弾くことにどんな影響があるか、わかってきたでしょうか?
もちろん、固有感覚が全て、というわけではありません。
いろんな機能をバランスよく使うことで人間は動けているからです。
固有感覚というものがあることを知り、利用していくことでカラダの状態へ意識が向き、動きの質は上がると思います!
もしわかりにくい部分がありましたら、どんな些細なことでも構いませんのでご質問やご意見、ご感想をいただけるととっても嬉しいです!
ツイッターのアカウントがありますのでぜひぜひそちらから、、、お待ちしています!!
次回あたりにいよいよ?みなさんが興味がありそうな?
フィンガリングについて手の構造とともに語っていければと思います。
それでは〜!





























