
無形の音を記録する発明・空気振動を捉えるという魔法
録音媒体の進化は我々の音楽生活に多大な影響を与えた。
1857年、レオン・スコット(仏)が発明した紙媒体への記録装置「フォノトグラフ」、1877年12/6(音楽の日)にエジソンが真鍮の円筒に「音溝を掘る」事で音を記録する「フォノグラム」、謂わば初期型のレコードの原理と同等の機械を発表した。
エジソンの発明から10年後、エミール・ベルリナーが収納の利便さを打ち出した円盤式記録装置「グラモフォン」を発明した。(ここまでWiki参照)

※グラモフォン(金沢蓄音器館様蔵)
これは後世のCDやDVD、BDやHDD等、水平記録媒体として受け継がれる事になる。 磁性体をプラスチックフィルムに塗布し、繰り返しの録音消去を可能とした記録媒体の登場は、音楽を楽しむ環境を大きく変えていく事になる。
プロのレコーディング現場では、2インチ幅のテープを用い、多チャンネルでの録音作業が可能となり、世界的なロック・バンドQUEENの名曲「ボヘミアン・ラプソディ」は、多重コーラスのリテイクを繰り返した結果、テープの磁性体が劣化し、向こう側の景色が透けて見えるようになり、後1テイクしか猶予が残されていないギリギリのラスト・テイクでレコーディングを終了させたとの伝説的逸話がある。
フレディ・マーキュリーのクラシック音楽への造詣が、究極の完成形を追い求めた結果である。
この努力が後世迄語り継がれるロックオペラの名曲「ボヘミアン・ラプソディ」を世に送り出す契機になった。
極私的音楽の愉しみ
1970年代のカセット・テープ興隆へと時代は変遷し、極私的音楽の楽しみ方が拡がっていく。 後にカセット・テープを用いたポータブル式音楽プレーヤーの「ウォークマン」等は屋内でしか楽しめなかった音楽を、見事屋外へ連れ出す事に成功し、若者達の圧倒的な支持を集めた。
だが、当時のヘッドフォンは軽量化を狙ったため(むきだしのウレタン素材)、少なからず音漏れを発生させ、人ごみの中でトラブルを生じさせた。
インナーイヤー式のステレオイヤホンはウォークマン発売当初市販されておらず、後に音漏れの問題を修正するかの如く、メーカー各社がこぞって採用するようになった。
更なる進化は止まらず、Apple社のiPodの登場と共に「アナログ情報だった音」を「デジタル化したデータ」へと変換し躯体のコンパクト化に成功。
このiPodの登場は後のiPhoneの音楽再生機能として受け継がれていく。
聴くだけの音楽から創造する音楽へ・個の進化
トリビア的前置きが長くなってしまったが、ここから後半へ向けて私の体験も含め、砕けたお話を勝手に進めていきたいと思う。
若き頃、英語の勉強をするためと親を説得し、ラジカセ(ラジオ付きカセットレコーダー)を友人達も親を騙し買い求め、好きな曲をレコードやエア・チェックからテープにまとめて録音し、名刺交換宜しく友人とやり取りする。
成長と共に聴くためにのみ存在していた音楽を、自ら制作してみたい欲求に駆られ、バイト代でステレオ内蔵マイクが搭載されているラジカセを2台購入し、「ピンポン録音」に熱を上げていく。
※シュガー・フィールズ様(代表: 原 朋信様)のYoutubeチャンネルでは過去のピンポン録音の体験が楽しく語られております。
ワウフラッターの個体差がどうしても避けられない宿命として残り、完成形のイメージ(特にピッチ及びテンポの大幅な変化)を逆引きして、ドンカマのテンポやギターやベースのピッチを微調整し対応させ録音するのは素人にはとても大変な作業であった。
基準音として曲の冒頭数秒間はドンカマやギターとベースの音を録音しておいた。
ラジカセのピンポン録音はテンポ・ピッチ共に早く高くなる傾向にあり、ある意味では実験録音の趣を持っていた。
加えて更なる試練を神は次々に与え賜うた。
プロ用のレコーダーと異なり、パンチインアウトが不可能なので、全て一発録りのスリリングな作業。
繰り返す内に演奏するスキルや集中力が勝手に磨かれるという思わぬ副産物。
そして一番如何ともし難いテープヒスの増加。
折角汗水流して録音した音が「シャー」という雑音に段々と埋もれていく。
和室の6畳間なので、微かに戸外の犬の鳴き声や子供達の嬌声も入ってしまう(笑)。
後にカセット・テープ式マルチトラック・レコーダーの登場。
私の食指が動かない理由はない。

※国産初のMTR 「TEAC 144 Portastudio」
国産初のカセット・テープ式マルチトラック・レコーダー「TEAC 144 Portastudio」をなけなしのバイト代をつぎ込んで購入、録音作業が格段にラクチンになった。
※この製品はDBXノイズリダクション搭載、ミキサー機能も付きサウンドメイクもピンポン録音に比較し格段に素晴らしかった。特に個体内部での編集作業が可能であった事が一番素晴らしかった。
元来A面とB面の各々2トラックをひっくり返して使うカセット・テープを一方通行にして4トラック録音、しかも倍速録音仕様の為、SN比は格段に向上した。
米国のロックシンガー、ブルース・スプリングスティーンのアルバム「ネブラスカ」はこのポータ・スタジオを使い彼の自宅で制作された。
果たして現代、デジタル技術の大進化と共に、音楽の楽しみ方は身近なものになり、しかもそれが安価で入手できるようになった。
プロだけに許された音楽制作がそのクオリティと共に市民権を得た瞬間である。
この進化無しには、現代のユーチューバーは存在し得なかっただろう。
結びに
浦島太郎が現代にタイムスリップしたらどう感じるだろうか?
鯛やヒラメの舞い踊りの酒宴での大騒ぎ、鉦や太鼓の大音量を高音質で歪まず映像と共に記録できるデジタルレコーダー。
ZOOM ( ズーム ) / Q8 ハンディビデオカメラレコーダー
記録媒体がSDカード等へ超小型化したMTR。
TASCAM ( タスカム ) / DP-32SD マルチトラックレコーダー
PC上で録音・編集できるDAWソフトウェアの進化。

業界標準のDAWソフトウェア「Pro Tools」※メーカーサイトより(https://www.avid.com/ja/pro-tools)
過去の記録を再生して太郎は己が姿をそこに認め、取り戻せない過去に思いを馳せその残酷さに一人涙するのではないだろうか。
記録媒体を口述や記述、伝承に頼るしかなかった太古の時代。
何時でも時代をクリアに遡る事のできる、デジタルメディアの記録装置はさしづめ現代の「玉手箱・タイムマシーン」だ。
溢れる創作意欲をリアルに記録し、音も記憶と共に掛け替えのない財産として後世に残したいと願う。
それがサウンドハウスさんには沢山用意されている。
否、膨大な楽器群を取り扱うサウンドハウスさんを「玉手箱」と呼ぶべきか?
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら





















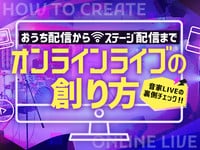 ライブ配信に必要な機材を徹底解説 オンラインライブの創り方
ライブ配信に必要な機材を徹底解説 オンラインライブの創り方
 厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集
厳選!人気のおすすめオーディオインターフェイス特集
 USB接続MIDIインターフェイス
USB接続MIDIインターフェイス
 配信・ポッドキャスト特集!(ライブ/動画/ゲーム実況)
配信・ポッドキャスト特集!(ライブ/動画/ゲーム実況)
 DTMに必要な機材
DTMに必要な機材
 DTM・DAW購入ガイド
DTM・DAW購入ガイド
















