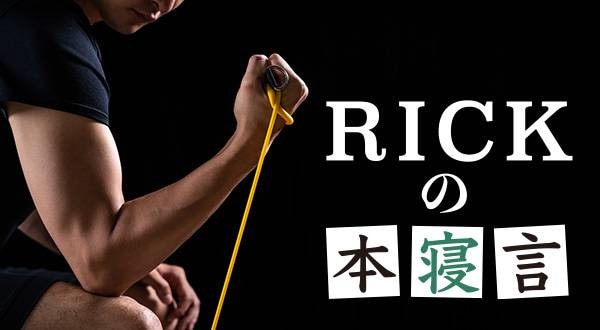巨大企業がカルテルなどの価格操作で暴利をむさぼることを禁止するアメリカの反トラスト法は、不公正な競争の抑止力として知られる。その流れを踏襲したであろう日本の公正取引委員会(公取)も、公正かつ自由な競争を促進することをモットーにした正義の味方というイメージがある。つい最近も、アマゾン社が取引先企業に対して圧力をかけて、国内トラック輸送コストの高騰などを理由に、一方的に協力金を求めたり、セール時の割引額を補填させたりすることが、優越的地位の濫用にあたるのではないかと、立入調査が入ったことは記憶に新しい。庶民にとって、公取はやはり正義の味方なのだ。

とは言え、ひとつわからないことがある。それはここ最近のポイント合戦だ。おそらく事の発端はヨドバシカメラの歴史から始まるのだろう。自分もよく「新宿西口駅前のヨドバシ」で買ったものだ。何しろ会員になると基本的に購入代金の10%を貯めることができ、それを次回の購入で使えるのだから、消費者にとっては朗報だ。当然競合他社も黙って見ているわけもなく、いつしか追随し、各社がポイントを提供するようになった。いや、ばらまく、と言った方が正しいだろう。よって一時期のケーズ電気のように、あくまで価格のみで勝負という考え方が、いつの間にか、鳴りを潜めてしまったようだ。

そのうえ顧客を取り込むために、自社のクレジットカード(クレカ)をプロモートする競争も勃発した。そして過度な競争のあまり、クレカを申し込むだけで、礼金のような数千円単位のお金が提供され、新規の顧客はそのお金を自由に使ってショッピングできるというオファーが今もって大々的に広告されている。クレカを申し込むだけでお金がもらえるのだから、これもまた庶民にとっては朗報だ。特に楽天のように自社グループで金融機関まで有している場合は、カード事業を含む金融業から多大なる利益を得ることも可能であり、クレカはネット通販系の企業にとって、ますます不可欠なツールになった。
しかし、ポイント合戦のいきつく所は、実質上の赤字販売だ。厳しい価格競争の結果、ネット通販大手が得ることのできる利益は、商品によってはほぼ、皆無になっているものがある。それでも赤字販売が避けられているのは、それがあからさまになると、不当取引として公取から刺されるからである。そこでポイントを上乗せして、より大きく実質上のディスカウントを提供する、という手法が昨今の常套手段となった。ポイント分を合算して考えれば赤字販売なのだが、競争に勝つためにはそんなことはおかまいなしと言わんばかりの、ポイント合戦が大流行している。

つまるところ、ポイント合戦の結末は中小規模の楽器店の消滅だ。何故ならポイントを加味すると、実質上は大幅な赤字で販売している商品が少なくないからだ。中小の楽器店はポイントをばらまくようなプロモーションを展開することは難しいし、ましてや赤字での販売は命取りになる。よって、大手企業の激しいポイント合戦の横行により、楽器店の生き残る道がほぼ途絶えてしまい、今や音楽教室などの物販以外のサービスに依存するしか手がなくなってしまったというのが現実だ。
ある時、公正取引員会に文書を投稿して聞いてみた。実質上の赤字販売が横行することを許してよいものか。これを放置するということは、ポイントをばらまき続けることのできる金持ち企業しか最終的に生き残れなくなり、多くの地域楽器店が壊滅してしまうことになると警鐘を鳴らした。しばらくすると、公取より書面で返事がきた。その主旨は、ポイントは値引きとは言えず、またそれが何にどう使われるかもわからないので、不当取引の対象にはならないということだった。つまりポイント合戦は公認のバトルとなったのだ。
サウンドハウスも2016年よりバトルに参戦して今日まで戦い続けている。他社は5倍、10倍20倍40倍と過激かつ、混みいったポイントプログラムを提供する最中、我が社はシンプルな10倍キャンペーンを中心に展開している。今やサウンドハウスも業界最大手として、今後は地方楽器店との共存を目指し、地域活性化のためにこれら楽器店を支援することを考えている。そんな思いとは裏腹に、いつの間にかポイント合戦に巻き込まれ、ふと気が付くと、日本列島から楽器店を消滅させる醜い競争に参戦しているのか、と思うと複雑な気持ちになる。May it never be….!北海道から与那国島、波照間島まで、楽器の音色がやまず、子供たちが楽器に触れることができる地域の楽器店がいつまでも存在することが自分の願いだ。そのために今、何をするべきか、考えている。