
オリジナル曲を作っているアマチュアミュージシャンのみなさんは普段どんなことを意識して曲作りをしていますか?
「人の心を動かす曲を作りたい」、「盛り上がる曲を作りたい」など様々かと思いますが、アマチュアだということを考慮して曲作りをしていますか?
ライブハウスなどにおいてプロと違うところは、ファンだから聞いてくれているわけではないお客さんも多い、ということです。
別なアーティストを見に来たお客さんだったり、友達だから見にきてくれただけだったりという人たちを相手にしなければなりません。
すでにワンマンライブができるほど多くのファンを獲得しているアマチュアを除き、ほとんどのアマチュアミュージシャンがこの状態ですよね。
つまり熱心に見てくれるお客さんというのは少ないので、短時間でも魅きつけるインパクトが重要になるわけです。 ではそのためにはどんなところに注意して曲作りをしていけばいいか見ていきましょう。
■ 全曲シングルを作るつもりで
プロのフルアルバムを聞くと、中盤から後半にかけていい意味での中だるみポイントがあります。
アルバムだからこそ存在する曲で、コアなファンだけが好む曲です。
こういった曲はライブの持ち時間が30分あるかないかのアマチュアミュージシャンが演奏するには少しリスキーな曲です。
もし、この曲を演奏中にたまたまホールに様子を見に来たお客さんがいたらもったいないことになってしまいます。
自分の本来の魅力を伝えきれないままそのお客さんは「面白くないな」と思って帰ってしまうかもしれません。
■ インパクトのある言葉で
ライブハウスで見たオリジナル曲を演奏するバンドの歌詞を覚えていますか?
おそらくほとんどの人が覚えていないでしょう。
爆音で聞きとりにくく、どんなテーマで歌っているかもわからないはずです。
そんな中、一言でもいいので聞き取りやすい言葉がキャッチーなメロディに乗せられたらお客さんの印象に強く残すことができます。
これはプロのミュージシャンもシングル曲などで意識して作るポイントでもあります。
例えば、ヒゲダンのPretenderはサビ出だしの「グッバイ」で注目を集め、その後はハイトーンで「君の運命の人は僕じゃない」と歌いますが、ヒゲダンファンじゃなくてもここだけは覚えているという人は多いですよね。
歌詞全体がよくわからなくてもなんとなく苦いラブソングなんだなということもすぐに伝わります。
あとはB’zのウルトラソウルなんかも特徴的ですよね。 なんだかよくわからないけどすごいパワーワードです。
■ 長さは3~4分で
70年代ロックのように延々とソロが長く、6分も7分もあるような曲はアマチュアには不向きです。
ほとんどの人が飽きます。
超絶技巧派バンドでそういったテクニックを見せ場としているならそれもアリですが、多くの歌モノではあまり受け入れられないでしょう。
全ての曲を3分ちょっと終わらせなければならないわけではありませんが、長い曲になる場合は飽きさせないアレンジを考える必要があります。
■ 新曲はほどほどに
別に新曲を作るのが悪いということではないし、むしろどんどん新しいものを生み出すのは成長に繋がります。
見せ場とする曲を持っていないなら名曲ができるまで作り続けるという根性は大切です。
しかし、ライブの度に新しい曲を生みだし、既存曲をないがしろにしていませんか?
曲は何百回、何千回と演奏するうちにどんどん洗練されていきます。
「そんなに演奏したら飽きる!」と思うかもしれませんが、サザンオールスターズがこれまでに【勝手にシンドバット】を何回演奏したか想像もつきませんよね。
だからプロミュージシャンは演奏も見せ方もうまいのです。
持ち曲の完成度を高めたりアレンジを加えたりすることも忘れないようにしましょう。
ちなみにアマチュアバンドのライブでは「じゃあ次は新曲です」というMCを耳にすることがよくあります。
初めて見る人にとっては新曲かどうかなんて知ったこっちゃないので不要なMCですね。
自分たちにとっては古い曲や飽きた曲でも、ライブハウスに偶然居合わせた人にとっては全てが新曲です。
常に全力で演奏し、既存曲も育てていってください。
■ レコーディングもほどほどに
MTRが主流だった頃と比べ、現在は低価格でレコーディングを行うことが可能になりました。
もちろん低価格というだけでなく、高音質で細かな編集もラクラクです。
いいことではあるのですが、これに頼り過ぎて実際の演奏能力に見合わない音源を出してしまう人が増えてきました。
バンドにはいないシンセパートの追加、ギターのオーバーダビングなどはまだいいほうでしょう。
音源と生演奏は別物と考えて音源のクオリティを挙げることは悪くありません。
しかし、ピッチ補正やタイミング補正、ピッチ補正のみで作られたコーラスなんかも加わると本来の実力とはかなりかけ離れた音源が出来上がってしまいます。
プロがこういった作業を行うのは現場でも再現できるか、またはそれに代わるアレンジでいい演奏ができるから問題はありません。
ところが実力以上の音源を作ってしまったアマチュアは悪い意味で生演奏とのギャップだけが残ります。
せっかく作った音源がTwitterやYouTubeなどで話題になりライブに人が見にきてくれたとしても、その生演奏を見た人たちはがっかりしてしまうでしょう。
自分をごまかすためのレコーディングに時間をかけるなら、そのぶん練習したほうがためになりますよね。
■ まとめ
以上がアマチュアミュージシャンに知っておいて欲しい曲の作り方でした。
言うまでもなく、著者自身もアマチュアですが自身の経験や人から聞いた話を元に書いてみました。
プロの仕事というのは私たちアマチュアにとって見本となるべき素晴らしいものも多いですが、アマチュアならではの戦略があるのも確かです。
プロからも学びつつ、自分のフィールドに合った戦略で勝負していきましょう。
コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら













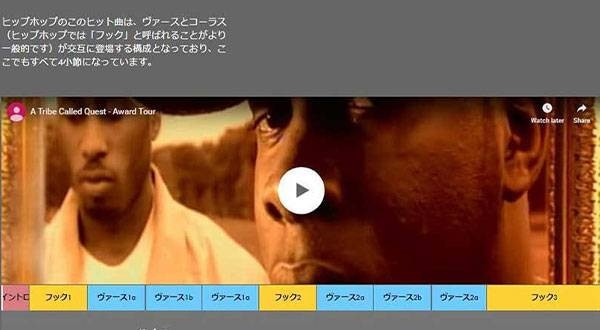
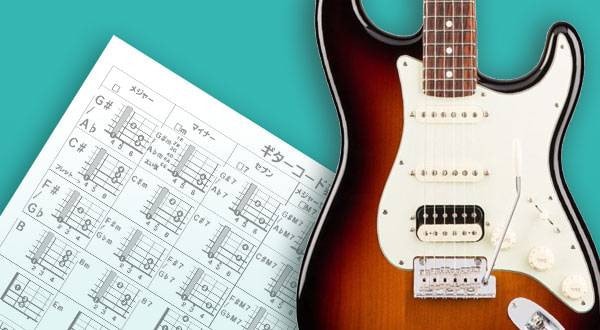

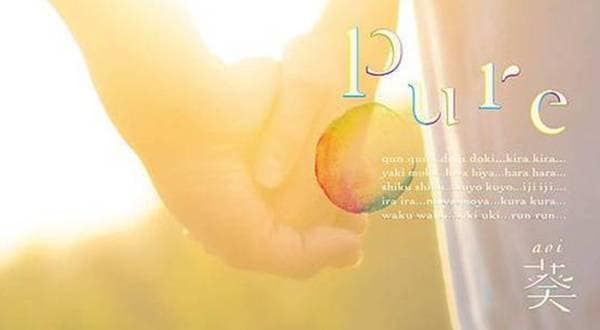
 DTMセール情報まとめ
DTMセール情報まとめ
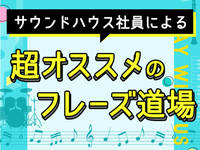 超オススメのフレーズ道場 キーボード
超オススメのフレーズ道場 キーボード
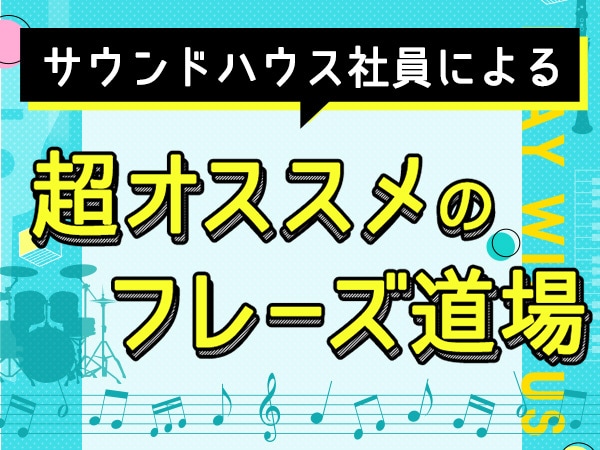 超オススメのフレーズ道場 ベース
超オススメのフレーズ道場 ベース
 ライブをしよう!
ライブをしよう!















