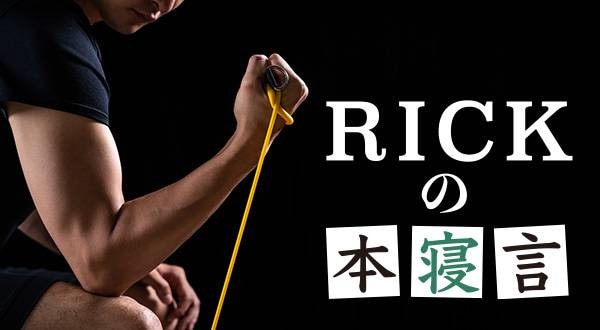お酒は人を楽しませ、悲しみを忘れさせ、心を浮き立たせ、人を幸せにすることができる。しかし落とし穴もあり、お酒は人を潰し、時には人を殺すこともできる。自分が小さい頃から、亡くなった父が口癖のように語っていたのを覚えている。「男をだめにするのは酒、タバコ、女」「この3つには気をつけろ!」と。これは正に一家の格言となり、自分の心の中に刻み込まれていった。
記憶の限り、自分の親族の中では、亡くなったお爺ちゃんだけが大酒飲みだった。いつも一升瓶を手元に置いていて、暇さえあれば飲んでいたように思う。よくよく考えてみると、75歳で亡くなる直前だったこともあり、いろいろな思いを巡らしながら、お酒を楽しんでいたのだろう。よって、大酒飲みと断定することは、間違いかもしれない。いずれにせよ、父親はそれほどお酒を飲まず、母親は全く飲まなかったので、そのDNAから察するに、自らのお酒に対する耐性はまあまあであり、決して大酒飲みの家系とは言えないだろう。
そんな自分が初めてお酒を飲んだのは中学生の時だ。その当時、同級生らとビールを手にしながら、「これがビールか。。。」と、苦くてまずい、と思いつつも、ビールを飲むことがとにかくかっこ良くも思えたのだった。そして密な飲み会が回を重ねるにつれて、だんだんみんなで飲むビール会が楽しくなってきたものだ。昭和の時代とは、そんなことくらいしか、週末の夜をみんなで楽しむことがなかったのかもしれない。
それからの自分の人生を振り返ってみると、お酒に溺れたような記憶は全くない。中高時代はテニスに打ち込み、ひたすら練習に励んでいたので、夜は疲れて寝てしまう日が多かった。アメリカの大学に入学してからは、思いの他、ビールを飲む量が増えてくる。1976年、USCという大学に入学した直後のキャンパス周辺の大パーティーには度肝を抜かされた。何しろ道路がブロックされてステージが構築され、著名なロックバンド、ビーチボーイズが野外コンサートを披露してくれたのだ。そのうえ、バッドワイザーというビールメーカーが生ビールの巨大なタンクをトラックでもってきてくださり、大学生に無料で飲んでもらったのだ。未成年の飲酒を気にする今日では信じられないような話だろうが、実話である。こうしてUSCの大学生はみんな、バッドワイザーのファンになった。無論、自分もそのうちの一人だった。
しかしながらそれでもお酒にはまることはなかった。高校時代からクリスチャンになったこともあり、大学時代では週末は教会、そしてアメリカでは毎日集会がある教会も多く、週3回は夜、教会に通っていた。よってお酒に溺れている暇などあろうはずがない。こうして大学時代も音楽をやりながら勉強にいそしみ、それでもお酒に浸ることはなかった。アメリカの大学は勉強家が多く、ストレスがひどくかかるが、それでもお酒に溺れなかったのは、信仰心あったが故のことと思う。
それから大学と大学院を卒業し、1985年からは仕事の絡みで、毎月アメリカと日本を往復するようになる。何しろアメリカで起業し、日本では教会の牧師までしていたので、それには大変な労力を要した。そして日ごろひどいストレスを抱えながらも、日米を行き来することになったのだ。良く我慢できたと自分ながら感心する。とはいえ、その過度なストレスの結果、1990年頃だったか、メニエール症候群で倒れ、初めて1週間の入院をすることになる。全治1年かかった。
さて、85年の話に戻ろう。当時、アメリカまでの航空券はエコノミークラスでおよそ5-700ドルぐらいではなかっただろうか。そんな時、朗報が訪れる。なんとANA、当時の全日空が1986年よりロスアンジェルスに向けて国際便の就航をスタートしたのだ。そして幸運にも教会の仲間数人が全日空の客室乗務員、つまりスチュワーデスとして働いていたのだ。そしてANAのフライトに誘われ、就航記念ということもあり、無料でビジネスクラスにアップグレードしてもらえるようになった。こんなラッキーな話はない、ということでいつしかビジネスクラスで日米を行き来するようになった。その後、アメリカン航空も追随して旅行会社にクーポンを配布し、エコノミーからビジネスクラスに無料でアップグレードできる仕組みが提供された。よって80年代はお金をかけずにビジネスクラスのフライトで行き来できることが多くなったのが嬉しい。
その結果、自分の人生にはちょっとした変化が起きてくることになる。ワインのたしなみ方を学ぶことになったのだ。ビジネスクラスでは必ずシャンパン、白ワイン、赤ワインがビールと一緒に選択肢として提供される。そこでただより得なものはないと、とりあえず何でも飲んでみることにした。赤、白、黄色、どのワイン見てもおいしいな!と思えるほど、どれもすんなりと飲むことができた。そしてある日、無料航空券を使ってJALのファーストクラスに乗れる幸運に恵まれた。そこで出されたワインが国産の甲州ワインだった。その素晴らしい味に絶句。そしていつしか日本ワインのファンにもなっていくことになる。こうして80年代後半より、ビールだけでなく、ワインドリンカーにもなった。
それから20年くらいは、ビールとワインくらいしか飲まなかったように思う。そもそもウィスキーやバーボンのように強いお酒は今でも美味しいと思えないし、カクテルのように甘いお酒も好みではない。あくまで食事と一緒に飲めるお酒ということで、まずはビールで口を潤し、その後、食材に合わせてビールかワインをいただく、というのを常としていた。ところが平成10年、お酒の嗜好性に変化がおきることになる。サウンドハウスを創業してから5年後の1998年、成田に最高級の日帰り天然施設、大和の湯をオープンした。その3階には寿司バー、紫苑を設立し、そこで寿司をつまみ、景色を見ながらお酒を楽しめるようにした。そしてお酒のメニューを見直す際に、初めて真剣に日本酒を飲み比べて、どの日本酒が美味しいかを見極めるようになった。それまで日本酒はほとんど飲んだことがなかったので、まずは口慣らしから始めたが、その味がわかるまでだいぶ時間を要することになる。
しかし日本酒もだんだんと味がわかってくると、その奥が深いことに感銘を受けた。そして2000年代からは、ビール、ワイン、日本酒の3本柱で自分の食卓がお酒で色付けられることになる。とはいえ、1993年に創業したサウンドハウスの激務は当初の想像を遥かに超えたレベルに達しており、お酒なんかに溺れている暇は到底なかった。また、自身の信仰心もあり、酔っぱらうことなかれ、という信条はもっていたので、それが幸いしたのか、お酒で潰れてしまうようなことはなかった。とにかく食事を楽しみながら、それと一緒に、お酒を味わうことが日々の楽しみとなってくる。
そんなライフスタイルがちょっとだけ変わった原因がコロナである。あの巣ごもりを余儀なく強いられたコロナ禍においては、とにかく家で仕事をしながらでもお酒をついつい飲んでしまう、という状況が多くなったのだ。そして気がつくと、飲酒量がほぼ倍増したのではないかと思えるほど、飲む量が多くなったような気がする。それでも健康診断では肝臓は守られていたので、何となく安心はしていた。が、やはり今でもちょっと心配はつのる。何しろそれまで2杯だけ、と心に決めて飲んでいたのだが、今や、最初にそう自分自身に約束しても、気が付くとずるずると3杯目、4杯目になっている。こりゃ、まずいぞ!
一番の心配は加齢による酒に対する耐性の変化だ。それまではワイン1本飲んでも平気で夜中まで仕事をしていた。飛行機の中では10時間、ぶっ続けでワインを楽しみながら仕事をしたこともある。ところが、歳をとってくるとそうは問屋が卸さない。何と、眠たくなって、落ちてしまうのだ!ふと気が付くと寝てしまっており、1-2時間後に目を覚ますことも最近では少なくない。これは衝撃的だった。お酒にはめっきり強いと自負していたのだが、もはやそうではなく、加齢の現象に負けてしまう自分がいたのだ。これにはもう手立てはない。歳相応にお酒の量を加減するしかないのだ。
これが自らの飲酒体験の歴史だ。何で、こんなつまらんことを書いているのか?それは、お酒に溺れてアル中になる人が、周囲に後を絶たないからだ。格言を覚えているだろうか。男をだめにするのは、「酒、たばこ、女」。その筆頭に酒がでてくる。酒には注意が必要なのだ。
最後に、酒に関わるほんまもんの格言をみんなに残そう。これらの格言は真実であり、誰しもが心に留めておくべき、感動の言葉でもある。
「酒は人をあざける者とし、濃い酒は人をあばれ者とする」 (箴言第20章1節)
「酒にふける者と、肉をたしなむ者とは貧しくなり、眠りをむさぼる者は、ぼろを身にまとうようになる。」(箴言第23章21節)
「酒に酔ってはいけない。それは乱行のもとである。」エペソ人への手紙第5章18節