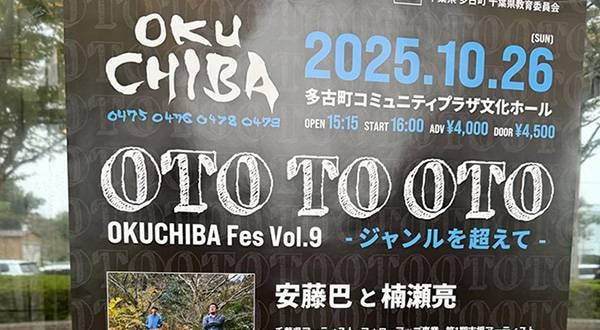10月27日、28日の週末は、earth garden “秋” 2018にぶらりお邪魔しました!
「オーガニック&エコロジカルなライフスタイルが、より身近なものになるように。自然と人との共生の意識が、より毎日の暮らしに根付くように。」そんな心温まるコンセプトのもと、シーズンごとに開催されている当イベント。ライブステージ、雑貨販売、出店がわんさかありつつも、どこかみんなホスピタリティに溢れていて・・・いいお天気の中、人がたくさん・・・
今回もいい発掘をすることができました!
Thank you(・u・) YOYOGI
earthgarden”秋”は「クラフトフェア」がテーマだったそうで、お手製キャンドルやワークショップもたくさんやってました。
そんななか、ありました。

民族楽器の村!
文字の丸みがたまりません。
この村で出会ったのは・・・

ででででん♪
こちらフレームドラムという楽器。起源は紀元前まで遡る古いものだそう。
メソポタミア文明の頃から脈々と続いてきたこの楽器の伝播範囲も広く (最近の研究ではBC5600頃からとも言われている)、 インド~中東~ヨーロッパ・・・など世界中に種々の形態で分布しています。またシャーマンドラムとしての分布はさらに広範囲に渡ります。古代では女性(女性神官)によって演奏された楽器でした。
By.日本フレームドラム協会
これ、写真では分かりにくいですが、サイズは大きめのタンバリンといったところ。
それぞれ縁に施されたテーピングの色と模様がエスニックでとってもかわいいです。枠の内側には金属のリングがたくさん付いており、とてもやさしい音がします。
手首のスナップを効かせつつ、リズミカルに叩くんですが、叩き方も持ち方も本当に人それぞれ!

これはなんと、店主自ら鹿の皮を加工して作ったというフレームドラム!
よく見ると細かく毛らしきものが。
ちなみに、この太鼓の加工を施す作業と、なめす(鞣す)という作業との違いについて、こんなふうに教えていただきました!
ーーーーこの加工した太鼓の皮を薬品に浸けて揉んだり叩いたりすると、衣服やバッグなどに使える柔らかい「なめし革」になります。漢字の記載もなめす前は「皮」、なめし後は「革」に変わります。「鞣す」は革と柔の2つで出来ているのはそのためです。靴、鞄などにも革の字が使われています。よく「皮をなめして太鼓を作られているのですね」と聞かれるのですが、柔らかい「革」は張りがなく太鼓には適さないので、自分が行う作業はなめしの手前の硬くて張りのある「皮」にする作業なのです。
やだもうすごいなるほど!!!!(・ω・)眼からうろこ
すごくわかりやすかったので、教えてもらったことを丸コピしました笑
これはバチで叩くのがおすすめだそう。
そのときの気温や湿度によってデリケートに状態が変わり、その時々で音色も変わってしまうんだとか。いやー深い。すごく単純ながらすごく深い。楽器が楽器たる所以を覗いた気がします。
さて、このフレームドラムたちの作り手さんは・・・

この方、久田祐三さん!盗撮みたいになっちゃった、すみません・・・orz
フレームドラム・ダラブッカ・口琴奏者。フレームドラム制作者。各種バンド・サポート等で東京中心に演奏活動中。またフレームドラム工房・音鼓知振としても制作・レッスン・WS・鹿皮の有効活用等を展開。
マルチすぎィ!(0ω0)
まあまあ鹿の皮を加工できるくらいですもんね、なんでもできますよそりゃ。
音鼓知振(ONKO CHISHIN)という名前も見事。好きです。いろんな演奏者といろんなライブも行っていらっしゃるので、興味のあるかたはぜひぜひチェックしてみてください!
フレームドラム工房・音鼓知振
なるほどな画像もたくさんアップされていて楽しいです(^^)

大量の本皮シェイカー。たくさんあってめっちゃかわいかったです(*´ω`*)
フレームドラムを作りたくなっちゃった方はこちら、久田さんがフレームドラムの作り方を解説してくださっているのでぜひ参考にどうぞ!
フレームドラムができるまで