事の発端は約15年ほど前かな?
突如アンプ業界に革命が起こった。
MarshallやBoogieやVoxの音を簡単に即座に再現してしまうプロファイリングアンプというものが発売されるらしいとの話。
そう、Kemperが登場したのだ。
Kemper Profiling Amplifier ( ケンパープロファイリングアンプリファイヤー ) / HEAD Black
ある人は「これで真空管アンプの時代は終わったな、、、」と思い、またある人は「本当かな?本当に同じ音が出るのかな?」と疑問に思い、私は「、、、、、なにそれ?」という状態であった。
よくよく聞くと、アンプの回路構成や部品などの、音を決定する要素は何ひとつ必要なくて、単純にアンプからの出音を分析してその音を出せる状態にするアンプなんだと聞かされた。
一部の人たちには爆発的に支持されたようだが、最初から私は否定派だった(今でも)。
私が否定する理由はただ一つ、「コピーは本物には勝てぬ!!」と思っているから。
実際、世の中に出回ったときに音を聞く機会があった。
Fender の古いチャンプの音をプロファイルして出してもらったがまさに爆笑物だった。
まあ、やはりこの手のアンプの限界を目の当たりにして安心した次第。
真空管アンプの音を決定する要素は出音だけにあらず!
真空管の劣化具合や、トランスの内部温度、古いカップリングコンデンサーからの漏れ電流や、電解コンデンサーの容量変動など、限りなく存在する。
今出た音が全く同じ状態で1時間後に出る保証などどこにもない。
あれから15年ほど過ぎたが、やはり私が最初に思った通りギターアンプ業界を席捲するまではいかなかったようだ。
持ち運びや手軽さで重宝することはあるようで、現在でも販売はされているが一時の勢いはすっかり影を潜めている。
そういう真空管アンプも実は絶滅寸前まで追い詰められたことがあるのを知っているだろうか?
絶滅寸前になった原因は「真空管が無い」だった。
当時(1980年初頭)国内、海外共に真空管を製造していたメーカーが軒並み生産を終了した。
秋葉原に出回っていたのは生産終了前に大量にストックしていた在庫品だ。
なぜ真空管は生産されなくなったのか?
答えはただ一つ「需要がなくなった」ことに尽きる。
高級オーディオやコンピューター、通信機などの部品として主役を張っていた真空管はトランジスターやOP-AMPの出現で全く立場がなくなってしまった。
あらゆるメーカーが真空管を使用した機器の製造を終了したが、細々ながら需要があったのがギターアンプ業界だ。
真空管がなくなっても何とか生産を継続したMarshall やBoogie 、Ampegなどの海外メーカーには頭を下げるしかない。
特にMarshallはJCM-800シリーズとJCM-900シリーズの切り替え時期に真空管不足に陥り、Marshall の代名詞とも言えるEL-34というパワー管を品不足の為採用できず、5881(6L6GC)というパワー管を使用しJCM-900シリーズを世に送り続けた。
やがてギターアンプ業界での需要がそれなりにある事を知った国で生産が始まり、現在は中国、ロシア、スロバキアなどで生産中だ。
特にスロバキアで生産されているJ/Jエレクトロ二クスは素晴らしい。
名門ブランドTESLAの生産設備を使用して、当時以上の品質を保ったものを作り続けている。
JJ ELECTRONIC ( ジェイジェイエレクトロニック ) / EL34
JJ ELECTRONIC ( ジェイジェイエレクトロニック ) / ECC83S
そして音だ。
昔購入したTELEFUNKENのEL-34(空き巣に入られ盗まれてしまった)の音を知っている私としては、現在の真空管は少し明るくて高音がきついイメージだが、トランジスターアンプ、ましてやデジタルアンプ、などとは比べ物にならないと思っている。
圧倒的な音圧と、音の分厚さ、歪ませた際の粘りと湿り気。
やはりこの音はデジタルや、トランジスターアンプでは再現できまい。
本物はやはり一味も二味も違う、と今夜もMesa/Boogie を鳴らしながら思っている。
しかし、実はトランジスターアンプも嫌いじゃなくて、YAMAHA のFシリーズやRolandのJCシリーズなどはエフェクターを使用する時などよくお世話になる。
次回のブログは大好評の1話完結のDIYの第2弾を考えてます。
お楽しみに。
















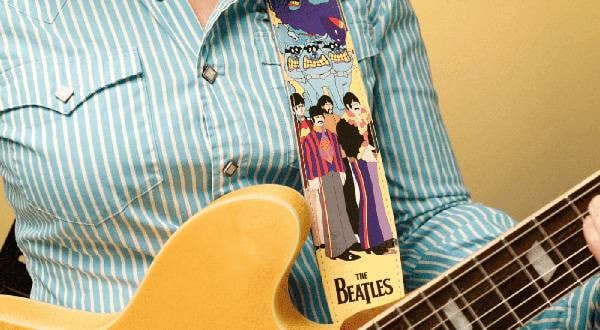



![The Road to Your Complete DIY: 2024 First Edition: Yet Another Special Feature on Tube Amps [EL-34 vs. 6L6GC]](/contents/uploads/thumbs/2/2024/4/20240415_2_26543_1.jpg)

![[2025 Edition] Recommended Guitar Amps at Sound House!](/contents/uploads/thumbs/2/2023/11/20231107_2_24499_1.jpg)


 ギターパーツの沼
ギターパーツの沼
 真空管について
真空管について
 ギターアンプ スタックタイプ編
ギターアンプ スタックタイプ編
 ギターアンプ コンボタイプ編
ギターアンプ コンボタイプ編
 ギターの種類
ギターの種類
 ギター演奏に必要なものは?
ギター演奏に必要なものは?















