この半世紀ぐらいで、音楽における低音域の重要度が増してきて、楽器も、より低い方へ拡張する方向にあります。これらの現象は楽器の発展というよりは、重低音を鳴らすための再生装置、特にスピーカーの発展が牽引しているようです。
■ アコースティック楽器の最低音
楽器の最低音として実用的に使える音程は、コントラバス、チューバのE1(41Hz)でしょう。欲張ったところではピアノのA0(27.5Hz)がありますが、実際の曲でA0を使うことは稀だと思います。さらに低いパイプオルガンもありますが例外扱いしても問題ないでしょう。リスナーに音程として届けやすい低音は、やはりE1ぐらいのように思います。欲張ってもD1(37Hz)ぐらいで充分のような気がします。
■ 倍音で音程を認識
ベースの低音は音程として認識しているのは基音ではなく1オクターブ上、もしくはそれ以上の倍音です。最低音の基音をサイン波として鳴らすと音は聞こえますが、大抵の人は音程は分からないと思います。言葉で説明しても伝わりにくいので短い動画を作ってみました。フレーズを弾いていますが、シンセベースとサイン波を交互に演奏しています。スピーカーで小音量で聞いている場合は、サイン波になると突然聞こえなくなったと思うぐらい分かりにくくなります。弾いているフレーズの最低音はE1(41Hz)です。人間の耳は、低音になればなるほど感度が悪くなるので、音量と低音はセットで考える必要があります。
■ 可聴域は20Hzから
人間は20Hzから音として聞こえると言われています。20Hzの音はD#0となります。ピアノのA0(27.5Hz)のさらに3音半低い音です。この音をそれなりの音量でサイン波で鳴らしても、何か低い音が聞こえるという程度です。ピアノ最低音のA0(27.5Hz)もサイン波で聴くと音が鳴っているのは分かるけど、ボリュームが足りない感じに聞こえるし、そもそも音程が分かりません。27.5Hzというのは1秒間に27.5回の振動があるということです。音程を聞き分けるには例えば、A0の27.5回と半音上のA#0の29回の違いを正確に区別できる必要があります。これぐらい振動数が少ないと、人間の耳には同じようにしか聞こえないわけです。音程を聞き取るには、ある程度高い倍音が含まれている必要があるのです。
■ 打楽器の低音
音程感がない打楽器などの音であれば、地響きのような低音も歓迎されます。オーケストラのグランカッサ(大太鼓)の役割は迫力という演出です。迫力には大きな音と重低音が不可欠です。生演奏などの大きな音では、耳で聞くというよりは、体で感じる振動が重要になってきます。自宅で気楽に再現する音ではないです。この打楽器の重低音に関しては、効果音に近いですから音楽的には、ある程度妥協しても大きな問題はないといえます。よほど大きな音を出さない限り、打ち上げ花火をテレビで見るような物足りなさを感じてしまいますが仕方ないことです。
■ ベース
音程のある低音を担うのは、多くのジャンルにおいてベースとなります。ベースの低音は音楽を支えるための低音ですから、ちゃんと音程として聞こえることが条件となります。
ベースを担う楽器はいくつかありますが、エレクトリックベースが現在の主役と言えそうです。エレクトリックベースは、ギターのような形をしていますが、役割としてはコントラバスを継承しています。音域やチューニングは、コントラバスそのものです。当然ですが最低音はE1でした。しかし80年代にもなると、より低い音が求められるようになります。これはシンセサイザーによるシンセベースがポピュラー音楽で使われていたという背景が大きいと思います。シンセベースは再生装置さえしっかりしていれば、E1より低い音を出すことは難しいことではないのです。また鍵盤奏者が弾いていたこともあって、ピアノ感覚で、E1より低い音を平気で使っていました。そういった楽曲をエレクトリックベースで演奏する場合、当然E1よりも低い音が要求されるわけです。 エレクトリックベースは、E1より低い音を実現するために、弦を追加する方向に進化します。従来の4弦ベースに対して1~2本弦が増えたので多弦ベース、もしくは5弦ベース、6弦ベースと呼ばれます。最低音はB0(31Hz)となります。プロのベーシストは渡された譜面通り弾く必要もあることから、何が来ても対応できるようにと多弦ベースを使う人は多くなりました。
■ 多弦ベースの開発
実際エレクトリックベースの開発において、多弦化は、太い弦を一本追加すればよいという単純な話ではありません。低い音をしっかり鳴らすということは、本体がしっかりしていないと、鳴らしきれないものです。ベースは弦が太く張力が強いため、ネックにかかる負担はかなりのものです。今現在のベースのほとんどは、多弦に限らず、本体を寝かせるだけで、自重でチューニングが簡単に狂ってしまいます。このような状態では低い振動ではネック、本体共に暴れてしまって、芯のある音は望めません。とても張力に見合う構造とは言えない状態です。ヘッドにおもりを付けると音が良くなるという話がありますが、あれはネックの暴れが抑制されているだけです。本来はネック強度を大幅に上げる必要があります。エレクトリックベースまだまだ発展途上と言えるでしょう。
■ 再生装置
民生オーディオ機器も高性能化して、一般家庭でも重低音を鳴らせるようになってきましたが、スピーカーで音楽を聞くリスナーは昔より減っているように思います。最近は大型スピーカーは流行らないし、大音量で聞けるリスナーも少ないと思いますので、ベースの最低音をきちんと再生できていないでしょう。聞こえているのはおそらく倍音だけです。
むしろ最近ではMP3をヘッドフォンで聞くリスナーの方が多いと思います。それなりのヘッドフォンであれば低域再生能力も優れているので、30Hzぐらいでも鳴らすことができます。ただ本来の重低音は体で振動を感じるというのが醍醐味ですので、やはりヘッドフォンで聞く低音は物足りなく感じます。

コラム「sound&person」は、皆様からの投稿によって成り立っています。
投稿についての詳細はこちら











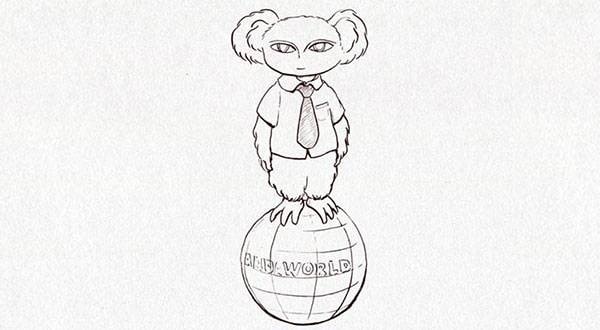
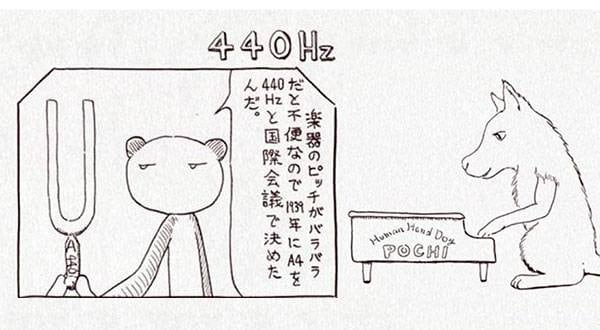

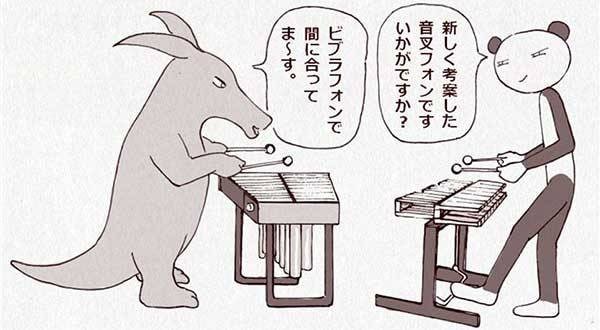


 お化けを倒してサウンドGET!
お化けを倒してサウンドGET!
 バンドあるある相談
バンドあるある相談
 サウンドハウス社員が選ぶ 『おもしろ商品』はコレだ!
サウンドハウス社員が選ぶ 『おもしろ商品』はコレだ!
 ○○やってみた!
○○やってみた!
 最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信
最新コラム&動画をCheck!! OTOYA通信
 サウンドハウス虎の巻 !
サウンドハウス虎の巻 !














