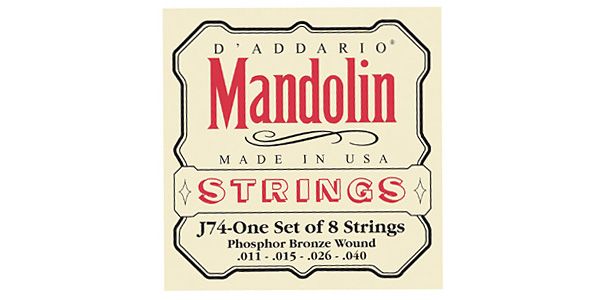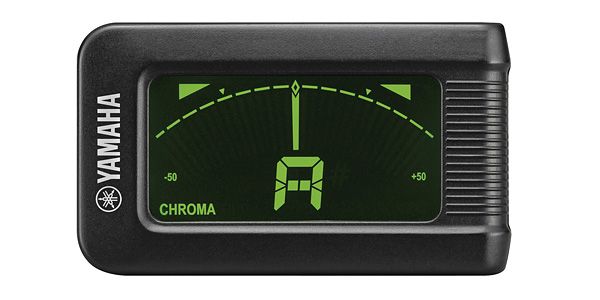- サウンドハウス虎の巻!
- マンドリン初心者講座
- マンドリンの各部名称
マンドリンの各部名称

マンドリンの各部名称
マンドリンを始めるにあたって、まずはマンドリンの各部名称をおさえておきましょう。フラットマンドリン、クラシックマンドリンで共通の部位がほとんどです。
ヘッド
ネックの先端部分。クラシックマンドリンのヘッドには、ナポリ型とローマ型の2種類の形状があります。
クラシックマンドリン ナポリ型

クラシックマンドリン ローマ型

ペグ
弦の先端を巻きつけるパーツ。つまみを回して弦の張りを調整します。弦4本ずつで左右に分かれています。

ナット
指板とヘッドの境目にあるパーツ。弦が通る位置に溝が彫ってあり、弦の間隔を保持して支える役割があります。開放弦の音(フレットを押さえないで弾いたときの音)は、ナットが弦振動の支点となります。

ネック
弦が張られた棹の部分。太さや形状、材質、塗装の仕上げによって弾き心地が変わります。

指板(フィンガーボード)
ネックの表面の板。左手の指で押さえて音の高さを決める部分です。

フレット
音程を定めるために指板に打ちつけられた金属。1フレットごとに半音ずつ変化します。ヘッドに近い側から、1フレット、2フレット、…と呼ばれます。

ポジションマーク
指板上の位置を分かりやすくするために、指板表面や側面につけられた目印。ドット、ブロック、スノーフレーク、キャッツアイなど、モデルによって様々なマークがあります。

ボディ
弦の振動が共鳴する部分。材質や形状によって音色が大きく変わります。フラットマンドリンには、AスタイルとFスタイルの2種類の形状があります。クラシックマンドリンのボディ裏側は細い板を複数貼り合わせて作られており、半球状に膨らんでいます。
フラットマンドリン Aスタイル

フラットマンドリン Fスタイル

クラシックマンドリン

サウンドホール
ボディ内の共鳴を外に出すための穴。様々な形状があり、フラットマンドリンはfホール、クラシックマンドリンはラウンドホールかオーバルホールが一般的です。
- ラウンドホール
- 円形
- オーバルホール
- 楕円形
- fホール
- アルファベットのfの形
フラットマンドリン fホール

クラシックマンドリン オーバルホール

ピックガード
演奏時にピックがぶつかってボディが傷つくことを防ぐためのパーツ。
フラットマンドリンではフローティングタイプが多く、ピックガードがついていない楽器もあります。
クラシックマンドリンではボディのトップに埋め込まれて一体になっており、形状や素材はモデルによって異なります。装飾としての役割も大きく、楽器の個性を際立たせます。
フラットマンドリン

クラシックマンドリン

ブリッジ
弦を支え、弦振動をボディに伝えるパーツ。固定されておらず、位置を調整できます。

アームガード
腕を支えるとともに、腕が楽器表面や弦に触れないよう保護する板。フラットマンドリンには通常つけられておらず、クラシックマンドリン特有のパーツです。大きさやデザインは、モデルによって様々です。

テールピース
弦の端を留める部分。弦の末端についている輪を、テールピースに取りつけられたピンにかけます。フラットマンドリンではボディの表面下部、クラシックマンドリンではボディの下側面に位置します。フラットマンドリンのテールピースにはカバーがつけられています。
フラットマンドリン

クラシックマンドリン

マンドリンカテゴリー
関連記事

マンドリンってどんな楽器?

これから始める人におすすめのマンドリン2種、徹底比較!

【フラットマンドリン】PLAYTECH PFM10F買ってみた

吹奏楽の有名曲をマンドリンで演奏すると…!?

姿勢の歪みが心配なマンドリニスト必見!「エルゴプレイ マンドリン用」の使い方とメリット・デメリット

マンドリン界の未来の大器! ジャパン・スーパーユース・マンドリンオーケストラ ~ 前編 ~

忙しい日々に癒しを!おすすめのマンドリン曲3選

マンドリンとその仲間の楽器を紹介します!

クラシックマンドリンとフラットマンドリンを比べてみました!

SUPER LIGHT(スーパーライト)マンドリンケースの魅力とは…?

鼈甲ピック派のマンドリニストへ!【自作ウルテムピックのすすめ】

SKBフラットマンドリンケースの魅力とは…?
カテゴリーから探す
-
 大幅値下げ市
大幅値下げ市
-
 アウトレット
アウトレット
-
 新商品
新商品
-
 初心者セット
初心者セット
-
 巣ごもり・テレワーク
巣ごもり・テレワーク
-
 配信機材
配信機材
-
 ヘッドホン・イヤホン
ヘッドホン・イヤホン
-
 マイク
マイク
-
 ワイヤレス
ワイヤレス
-
 スピーカー
スピーカー
-
 パワーアンプ
パワーアンプ
-
 ミキサー
ミキサー
-
 プロセッサー
プロセッサー
-
 ポータブルPAシステム
ポータブルPAシステム
-
 レコーダー
レコーダー
-
 カラオケ
カラオケ
-
 ギター
ギター
- ブランドから探す
- エレキギター
- アコースティックギター
- ギターアンプ
-
ギターエフェクター
- ギター用プリアンプ
- オーバードライブ/ブースター
- ペダルチューナー
- ディストーション
- ファズ
- ワウペダル/オートワウ
- アンプ/キャビネットシミュ
- ギター・ベース用ワイヤレス
- ノイズリダクション/ノイズゲート
- イコライザー
- コンプレッサー
- コーラス/フランジャー
- フェイザー
- トレモロ/ビブラート
- オクターバー/ピッチシフター
- ディレイ
- リバーブ
- アコースティックシミュレーター
- ルーパー
- ループスイッチャー
- マルチエフェクター
- ギターシンセサイザー
- ボリューム/エクスプレッション
- フットコントローラー/セレクター
- その他エフェクター
- パワーサプライ
- アコギ用DI/プリアンプ
- アコギ用エフェクター
- エフェクター用ケース
- 乾電池
- エフェクターアクセサリー
- iOS用ギターエフェクター
- ピック
- ギター/ベース用ストラップ
- ギター弦
- ギター用アクセサリー
- ギターケース
- ギターピックアップ
- ギターパーツ
- メンテナンスグッズ
-
 ベース
ベース
-
 ウクレレ
ウクレレ
-
 ドラム・パーカッション
ドラム・パーカッション
-
 ピアノ・シンセサイザー
ピアノ・シンセサイザー
-
 管楽器
管楽器
-
 弦楽器
弦楽器
-
 和楽器
和楽器
-
 ハーモニカ・その他楽器
ハーモニカ・その他楽器
-
 DTM・DAW
DTM・DAW
-
 DJ & VJ
DJ & VJ
-
 スタンド各種
スタンド各種
-
 ケーブル・コネクター
ケーブル・コネクター
-
 ラック・ケース
ラック・ケース
-
 照明
照明
-
 ステージ・トラス
ステージ・トラス
-
 映像機器
映像機器
-
 パソコン・周辺機器
パソコン・周辺機器
-
 電源周辺機器
電源周辺機器
-
 スタジオ家具・吸音材
スタジオ家具・吸音材
-
 日用品・生活雑貨
日用品・生活雑貨
-
 お酒
お酒
ブランドから探す
ブランド一覧を見るアフターサービス
- 成田コールセンター
- TEL. 0476-89-1111
- FAX. 0476-89-2222
- 徳島コールセンター
- TEL. 0885-38-1111
- FAX. 0885-38-1100
© Sound House