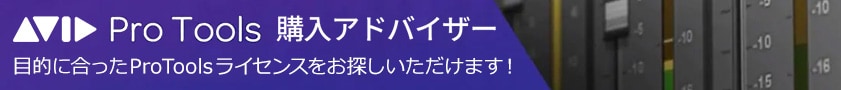- サウンドハウス虎の巻!
- DTM初心者講座
- DAW (デジタル・オーディオ・ワークステーション)とは?
DAW (デジタル・オーディオ・ワークステーション)とは?
DAW (デジタル・オーディオ・ワークステーション)とは?
目次
DAW とは
DAW (デジタル・オーディオ・ワークステーション、Digital Audio Workstation)とは、PC上で作曲や録音、ミックスなど幅広く制作を行うためのソフトウェアです。「音楽制作ソフトウェア」「録音ソフトウェア」と呼ばれる方をすることもあります。
DTM(デスクトップ・ミュージック)をするうえでもスタートラインと言えるソフトウェアです。なお、DTMは和製英語であり、海外ではDAW自体が作曲を表す場合もあります。
パソコンに元から付属するソフトウェアを利用して録音することもできますが、DAWでは多重録音をはじめ、リバーブやノイズ除去など細かな調整を加えることが可能です。ソフトシンセなどのソフトウェア音源を導入し、自分の思い描いた楽曲を制作することもできます。
DAW でできること
- 音源の録音データを保存できる
- 多重録音ができる
- 作曲・編曲ができる
- ミックスやマスタリングを行い、楽曲を仕上げることができる
DAW の種類
各DAWソフトウェアにはそれぞれ特徴があります。近年ではどのDAWを選んでも同等の機能を有していることも増えてきましたが、各ソフトウェアの特徴を押さえることで、購入の足掛かりにもなることでしょう。
ここでは特に有名な6つのソフトウェアをご紹介します。
STEINBERG / Cubase
AVID / Pro Tools

AVID(アビッド)は、アメリカ発の映像・音響機器メーカーです。なかでもPro Tools(プロツールス)はプロの現場で使用されることの多いDAWとして超定番のソフトウェア。テレビ、映画、コマーシャルなど、Pro Toolsの操作を要求される場面の多い職種もあり、個人で楽しむ際にもメイン/サブ問わず選ばれることが多くあります。
またPro Toolsは、オーディオシステム全体を指して使われることも。AVIDの提供するオーディオインターフェイスや、子会社であるDigidesignケーブルなどを併用した一体型の環境も「Pro Tools システム」や「Pro Tools HDシステム」と呼ばれます。
2022年現在はサブスクリプションの導入により、新規導入する場合は1年ごとに契約を更新する仕組みとなりました。必要なライセンスは「Pro Tools 購入アドバイザー」からお探しいただけます。
PRESONUS / Studio One

PRESONUS(プレソナス)は、アメリカにて誕生したレコーディング機器などを幅広く手掛けるメーカー。なかでもDAWであるStudio One(スタジオワン)は、ドイツの敏腕プログラマーがデザインした次世代の64 bit DAWとして人気を博しています。
DAW定番の機能はもちろんのこと、バージョンアップのタイミングでは、今までに無いようなアイデアを次々と生み出し、ユーザーを魅了しています。さらにバージョン5からはライブで使用することを想定した「ショーページ」機能が追加*され、さらに幅広いユーザーに使用されるソフトウェアとなりました。
*ショーページはProfessionalグレードのみに搭載
そしてフリー版であるStudio One Primeが配布されていることも注目ポイントです。一般的なDAWのデモ版は使用期間に制限があることが多いのに対し、Studio One Primeは無償のまま使い続けることも可能。Studio One Primeで楽曲制作を始めて、後から必要に応じて製品版へアップグレードしていくことも可能です。
ABLETON / Live

ABLETON(エイブルトン)はドイツ発のDTM関連製品を取り扱う気鋭のメーカー。Live(ライブ)は他のDAWとは異なり、アレンジメントビューとセッションビューの2画面を使い楽曲を組み立てていく方法を採用しています。
直感的な操作が可能なため、ライブパフォーマンスを主軸としたアーティストに使用されることも多いソフトウェアです。
楽曲制作の流れは、セッションビューで曲の構想を作り、作成したループをアレンジビューに貼り付けてインスピレーションを形にしていきます。その作曲方法からもヒップホップやEDMなど、ループを主体としたジャンルで特に重宝されています。最上位版のSuiteグレードには、インストゥルメントやエフェクト・ツールといった、ライブパフォーマンスやビジュアル表現などで使用するデバイスを自作可能な「MAX for Live」を搭載。まさにパフォーマンスに適したDAWと言えるでしょう。
IMAGE-LINE / FL STUDIO

IMAGE-LINE(イメージライン)はベルギーで生まれたソフトウェア・メーカー。FL STUDIO(エフエルスタジオ)は、パターン入力によるループミュージックの制作を得意とするDAWです。国内ではFL(エフエル)と呼ばれることも。その独特な入力方法から、EDMなど電子音楽を手掛けるユーザーから絶大な支持を集めています。
さらに、FL STUDIO自体をVSTプラグインとして使用できるため、既に他のDAWを所有されている方にもおすすめです。
エフェクトチェーンによって複数トラックへのエフェクト適用が視覚的に分かりやすく、トラック作成において煩雑になりがちな部分をすっきり整理できます。数あるDAWの中でも最高のピアノロールのひとつとして評価されているほど簡単な操作も魅力的です。
なかでも特筆すべきは「永年アップデート無料」であること。一般的なDAWは、バージョンアップの際に有償でアップデート版を購入する必要がありますが、FL STUDIOは一度購入してしまえば、その後のアップデートがすべて無料で入手可能です。
MOTU / Digital Performer (DP)

MOTU(モツ)は、高品質なDTM機器を手掛けるアメリカの老舗メーカー。日本では略称で親しまれていますが、正式にはMark of the Unicorn(マーク・オブ・ザ・ユニコーン)社と言います。Digital Performer(デジタルパフォーマー)は、1985年に発売された「Performer」から進化を続ける歴史あるDAWソフトウェア。『DP』や『デジパフォ』と呼ばれることもあります。シーケンサー時代の長所を残しつつ、MOTU社らしい高品位のオーディオ録音/編集にも対応するプロフェッショナルなDAWです。
オーディオデータをMIDIノートに変換する機能を搭載しているため、耳コピを行う際にも役立ちます。検知の仕方はモノ/ポリ/ドラムループとパーカッシブ・オーディオの3種類。クリップトリガーによってMPCのような動作をさせることも可能。まさにワンランク上の楽曲制作ソフトウェアと言えるでしょう。
OSとは?スペックとは?
DAWを選ぶときには、「動作環境を確認してください」、「スペック欄を参照してください」などと記載されていることも多いですが、実際にはOSやHDDなど確認事項が多い!!はじめてソフトウェア製品をお選びいただくにはハードルが高いのも事実です。
ここでは「動作環境」のなかで、よく確認した方が良いポイントに絞ってお伝えします。
OS
OSとは、「Operating System (オペレーティングシステム)」の略で、パソコンを動作させる基本となるソフトウェアを指します。個人向けコンピューターにおいて、広く使用されているものは「Microsoft / Windows OS」または「Apple / mac OS(Macintosh)」の2種類。他に利用者の多いLinuxや、近年GoogleのリリースしているChrome OSも存在しますが、DTMを行うにあたっては対応製品が多くないため、あまりおすすめできません。
またOSは常にバージョンアップを続けており、DAWの動作環境もアップデートされます。ここで気を付けたいのが、「アップデートしたばかりの最新OSではDAWソフトウェアが動作しない場合がある」ということ。OSのアップデートが告知された際には、使用しているDAWの動作環境を必ずチェックするのが重要です。
CPU
CPUとはコンピューターにおける、最も重要な処理装置です。パソコンが動作するための主要パーツの一つであり、この性能がDAWの挙動を大きく左右します。
老舗であるIntelや新進気鋭のAMD、2019年頃よりmacに搭載され始めたAppleシリコン(M1やM2)が有名で、たいていDAW動作環境にはこの3メーカーの記載があります。また各メーカーの中でも数多く種類があるため、製品名だけでなくいつ発売されたどのバージョンのCPUなのかも確認すべきポイント。自作PCを除き、購入したPCの型番から搭載されているCPUを確認することが可能です。
さらにCPUのコア数が問われることもあります。CPUにおけるコアとは、実際に処理を行う頭脳の数、と想像してください。一般に作業する人数として例えられることも多くあります。こちらも多くの場合は購入したPCの型番からチェックできます。
RAM
RAMとはPCが何かを処理するときに使われる作業用メモリのことを指します。CPUを作業者とするなら、RAMはデスクの広さと例えられることが多く、PCの作業効率にも繋がります。近年のDAWでは4GBもしくは8GB以上を最低限必要とすることが増えているため、この点もPCの型番などから確認しましょう。
ディスク容量
PCに保存できるファイルの容量を指します。HDDもしくはSSDと表記されている場合もあります。
インストール時に要求される空き容量と、実際に動作させる際に必要な容量は異なります。加えて制作していくことで発生するデータによって徐々に空き容量は減っていきますので、PCを購入するときにはなるべく大きい容量を選択しておきましょう。
オーディオデバイス
PCが音声を処理する際に使用するデバイス(機器)のことです。最近ではWindows / Macともに内蔵されていますが、専用デバイスの使用をおすすめします。遅延や音質、ノイズ改善に大きく関与します。
DTMにおいてはオーディオインターフェイスがその役割となります。Windowsでは基本的にはASIO対応オーディオデバイスが推奨されます。よくお問い合わせをいただきますが、専用ドライバーをインストールするタイプのオーディオインターフェイスは、殆どの場合ASIOに対応しています。
グラフィックボード、ディスプレイ解像度
グラフィックボード、通称グラボ。ディスプレイに映像を映すためのパーツです。組みあがっているPCを購入する場合は特に気にする必要はありませんが、自作PCの場合はある程度のスペックが必要になるため、各DAWメーカー推奨されている以上のスペックのものを購入するのがベターです。
上記項目ほどではありませんが、以下の内容も押さえておきましょう。
32bit? 64bit?
bitとは、PCが計算するときの許容量のことを指します。この計算をする場所がCPU(中央演算処理装置)というわけです。
近年のPCは処理能力が進化したことにより、ほぼすべて64bitのCPUを積んでいます。OSもそれぞれ32bit版、64bit版とあり、使用するソフトウェアに合わせて選びましょう。
特に最近では64bitOSのみ対応しているというDAWや音源、プラグインも増えていますので、64bitOSを選択するのが無難です。
Rosetta? ネイティブ? (macOSを使う方のみ)
Rosettaとは、Appleシリコンを搭載したmacに対して、IntelCPU向けに開発されたソフトウェアを実行できるようにするための仲介アプリケーションです。詳しくはAppleのサポートページをご参照ください。
反対にネイティブ(Native)はその名の通りAppleシリコンに純正対応しているソフトウェアのことを指します。一般的にはネイティブアプリの方が早く動作するため、可能であればネイティブで動かしたいところですが、DAWをネイティブ動作させる場合は、導入しているプラグインすべてがネイティブ動作に対応している必要があるので注意してください。
OSのアップデートはするべき? 最新版を使った方が良い? (主にmacOSを使う方向け)
OSのバージョンはできる限り新しいバージョンにしておくのがおすすめです。ただし、最新バージョンがリリースされてすぐにはアップデートしないことをお勧めします。
OSの項目でも記載した通りソフトウアが最新OSに対応していない場合があります最悪の場合ソフトウアが動作しないことも。OSをアップデートする前には必ず使用ソフトウェアの動作環境をチェックしましょう。